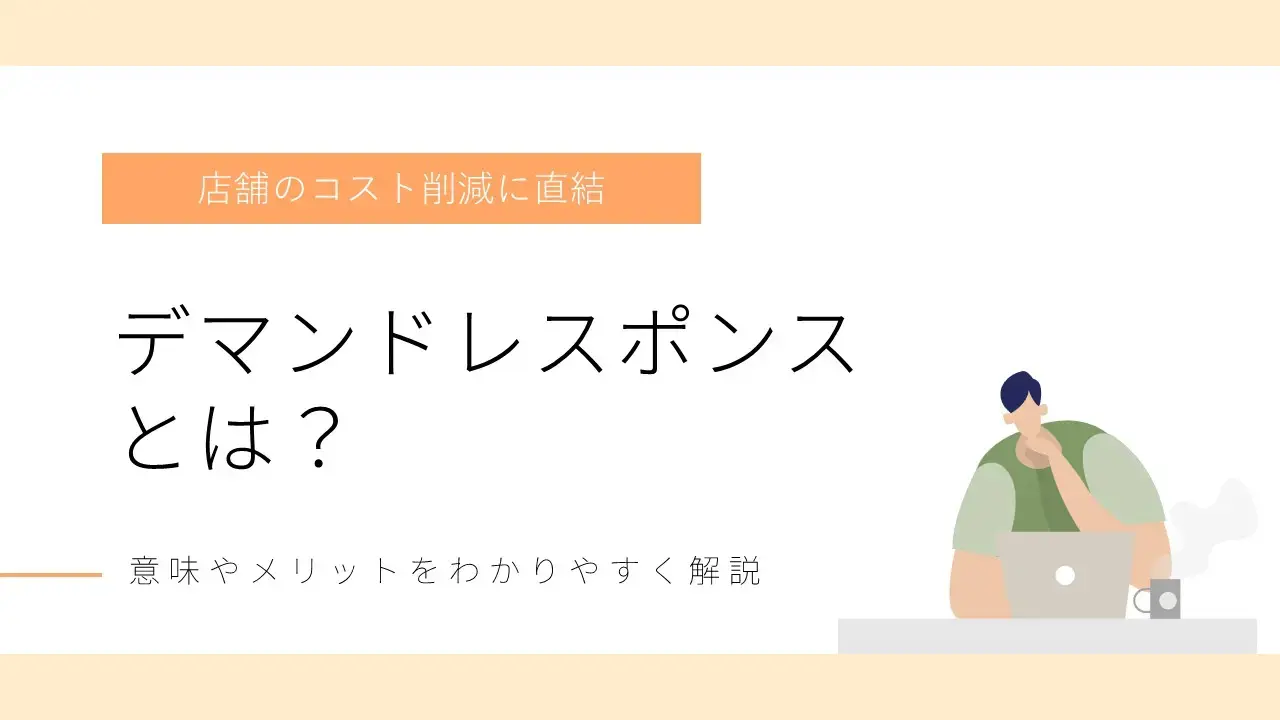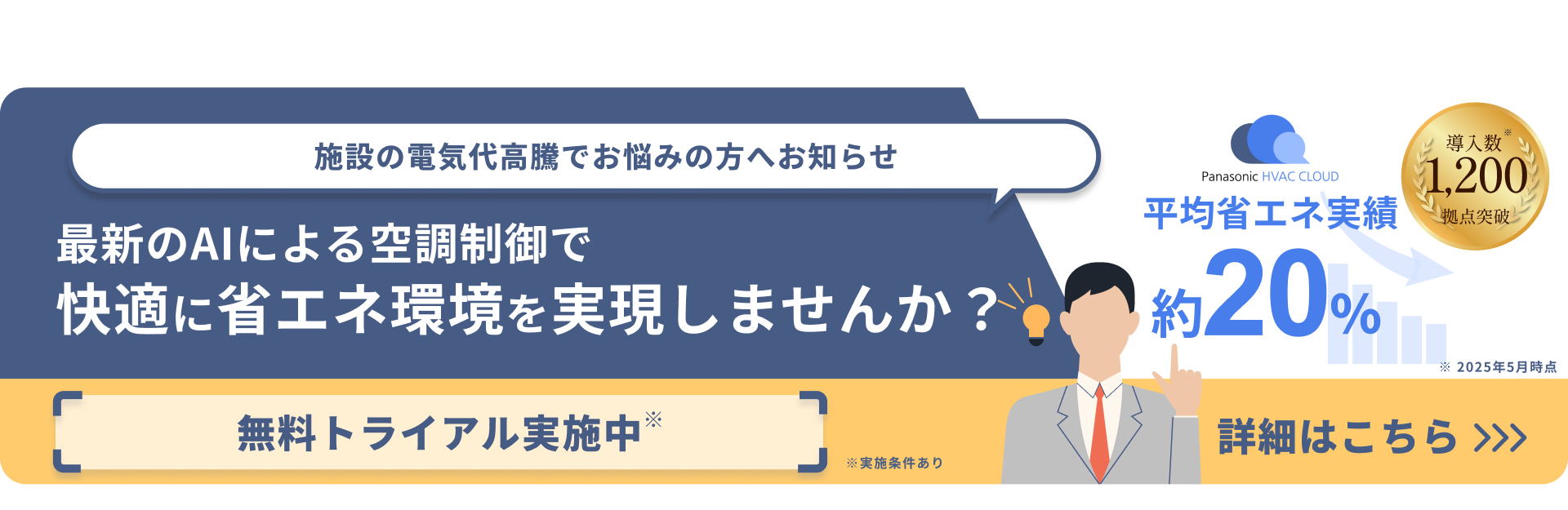近年、「デマンドレスポンス(DR)」という言葉を耳にする機会が増えています。
デマンドレスポンスとは、電力需要が高まった際に需要家が電気の使用量を調整し、需給のバランスを保つ仕組みです。再生可能エネルギーの普及やエネルギーコストの高騰にともない、デマンドレスポンスによる電力供給の安定化と効率的なエネルギー活用の重要性が増しています。
本記事では、デマンドレスポンスの基本的な意味から種類、参加するメリット・デメリットまで、わかりやすく解説します。
デマンドレスポンス(DR)の意味と必要性
デマンドレスポンス(DR)とは、需要家(電気を使用するビルや工場、店舗、施設など)が電力使用量を調整する仕組みです。電力需要が高まったときには消費を抑え、逆に電力が余っているときには積極的に利用することで需給バランスを整えます。
この取り組みが求められる背景には、電力システムの特性があります。電気は、供給量と需要量が一致していないと品質(周波数)が乱れ、大規模停電などのリスクにつながります。
そこで電力会社は発電計画を基に、需要の変動に応じて生産と供給を調整しています。ただし、大量の電気を貯めることは難しく、大量の蓄電池が必要になることから現実的ではありません。

また、近年は、地球温暖化防止を目的に、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギー導入が進んでいます。しかし、これらの再生可能エネルギーは天候によって発電量が増減する性質を持ち、火力発電のような従来の方法のように需要に合わせて自在に制御できません。
そのため、需要の高まりによる電力不足や、逆に再エネ由来による電気が無駄になってしまう事態も発生しています。

これらの課題を解決し、「電力供給の安定化」と「再生可能エネルギーの有効活用」を図るには、供給側だけでなく需要家による調整が必要になっており、デマンドレスポンスの必要性が高まっています。

デマンドレスポンス(DR)の種類
デマンドレスポンスは、参加する仕組みと、電力を調整する手法によって分類できます。それぞれの特徴を理解し、自社に最適なデマンドレスポンスの活用方法を検討してください。
デマンドレスポンスに参加する仕組み
デマンドレスポンスへの参加方法は、主に以下の2つです。
- 電気料金型デマンドレスポンス
- インセンティブ型デマンドレスポンス
電気料金型デマンドレスポンス
電気料金型デマンドレスポンスは、需要が増加するピーク時の電気料金を値上げすることで、需要家に電力使用を控えることを促す仕組みです。
電気料金が高くなることで、需要家は空調や照明、設備の運転を調整したり、生産スケジュールをずらしたりして電力消費を減らすことが期待されます。市場原理を活用したシンプルな手法であり、需要家が自主的に判断して対応できる点が特徴です。
インセンティブ型デマンドレスポンス
インセンティブ型デマンドレスポンスは、あらかじめアグリゲーター(※)や電力会社と契約を結び、電力需要の調整依頼を受けた際に対応することで報酬を受け取る仕組みです。
契約しているアグリゲーターや電力会社からの要請に応じて、電力がひっ迫する時間帯には節電を行い、逆に余剰電力がある時間帯には消費を増やす対応を行います。その達成状況に応じて、需要家は報酬を受け取ることができます。

なかには、デマンドレスポンスの実施有無に限らず、待機料金として報酬が支払われるケースもあります。調整依頼を受けた際の対応方法については、需要家が手動で設備等を制御するほか、設備等を自動調整するサービスを提供している場合もあります。
※「アグリゲーター」=電力会社と需要家のあいだに入って電力需要を管理・調整する事業者
電力需要を調整する手法
電力需要の調整は、需要を減らすか増やすかによって、次の2種類に分類できます。
- 下げDR
- 上げDR
下げDR
下げDRとは、電気の需要量を減らすことです。供給不足のリスクが高まった際、電力会社等からの要請に基づき、あるいは需要家自ら電力使用量を抑制します。
■「下げDR」の具体例
|
|
空調や照明などの設備の運転を調整・停止することで、電力需要を抑制する <例> ・冷房の設定温度を上げる ・冷房の運転をオフにする ・部分的に照明をオフにする |
|
|
生産設備の稼働時間をずらすことで、電力需要を抑制する |
|
|
蓄電池に貯めておいた電気を使い、電力会社からの電力供給を減らすことで、需要を減らす |
上げDR
上げDRとは、電気の需要量を増加させることです。需要量よりも供給量が上回ることが予想された際に、電力会社等から需要の増加を要請され、需要家は電力使用量を増やす取り組みを行います。
■「上げDR」の具体例
|
|
生産設備の稼働を増やすことで、電力需要を増加させる |
|
|
蓄電池や電気自動車を充電することで、電力需要を増加させる |
デマンドレスポンス(DR)に参加するメリット
デマンドレスポンスに参加することで、事業者は以下のようなメリットを享受できます。
- 電気代の削減につながる
- 電気の使い方を見直すきっかけになる
- 社会貢献につながる
ひとつずつ見ていきましょう。
電気代の削減につながる
下げDRの実施によって電力使用量を抑制できれば、電気代の削減につながります。電気料金型デマンドレスポンスなら、ピーク時の電力使用を控えることで、料金が高騰する時間帯のコストを抑えることが可能です。
また、インセンティブ型デマンドレスポンスなら、電気代の削減効果に加えて、待機・要請に応じた協力に対して報酬を受け取ることもできるでしょう。
電気の使い方を見直すきっかけになる
デマンドレスポンスへの参加は、日常の電力使用を意識するきっかけになります。
現代の生活では電気が当たり前のように使えますが、それは供給側が常に需給バランスを維持しているおかげです。しかし、地球温暖化対策として推進されている再生可能エネルギーは天候の影響を受けやすく、供給側だけで需給を安定させることは難しくなっています。こうした背景を知り、周知することで、電気の使い方を見直す意義が明確になり、社内全体での取り組み推進につながります。
さらに、デマンドレスポンスによって電気料金や電力使用量のデータを確認する習慣が生まれれば、無駄に稼働している設備や消費パターンを発見でき、日常の業務や生活の中で改善策を考える場面も増えるでしょう。
社会貢献につながる
電力の使い方の工夫は、電力の安定供給や地球環境の保護という大きな社会貢献につながります。
例えば、電力がひっ迫しそうなときに節電することで、その電力会社が管轄する地域一体の停電リスクを減らすことができるでしょう。また、再エネ由来の電気を有効活用することで火力発電に頼る必要性が減り、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を抑えられ、カーボンニュートラルや脱炭素に貢献します。
デマンドレスポンス(DR)に参加するデメリット・注意点
デマンドレスポンスには多くのメリットがある一方で、以下のようなデメリットや注意点も存在します。
- 体制を構築するためのコストや手間がかかる場合がある
- 無理な節電にならないように注意が必要
- インセンティブ型は参加の条件がある
これらの課題を事前に理解し、適切な対策を講じることで、デマンドレスポンスの効果を最大限に活用できるでしょう。
体制を構築するためのコストや手間がかかる場合がある
一般的に、デマンドレスポンスに参加すること自体には費用はかかりません。しかし、効果を最大限に得るには体制を整える必要があります。
例えば、デマンドレスポンスを実施する際には、どの設備の制御を行うかを考える必要があります。しかし、従来では月々の電気料金の請求書に書かれた建物全体の使用量しか把握できず、設備ごとのエネルギーの使用状況を把握することはできませんでした。感覚的に制御するケースもありますが、それでは空調の停止といった無理な節電につながる恐れがあります。
そこで役立つのが、エネルギー使用状況を可視化・最適化できる「エネルギーマネジメントシステム(EMS)」です。EMSを導入すれば、「いつ」「どこで」「どれくらい」「どのように」電力が使用されているかを具体的に把握でき、データに基づいたデマンドレスポンスが可能です。ただし、EMSの導入には初期費用や運用の負担が発生します。
さらに、デマンドレスポンスに対応するための運用ルールの策定や従業員への周知、制御する機器の選定など、事前準備や管理にも一定の手間もかかります。とはいえ、長期的に見れば効率的な電力運用やコスト削減につながるでしょう。
無理な節電にならないように注意が必要
下げDRを行う際、電力を「ただ減らす」ことだけに意識を向けてしまうと、無理な節電になりかねません。
例えば、空調や換気設備を停止すれば電力使用量は減りますが、温度や湿度、空気環境が悪化し、従業員の健康被害や作業効率の低下につながるリスクがあります。電力使用量を抑制する際は「必要な機能まで削る」のではなく、「不要な稼働(ムダ)を取り除く」という視点が重要です。
この課題を解決するには、GHP(ガスヒートポンプエアコン)とEHP(電気ヒートポンプエアコン)の両方を搭載したパナソニックの「一体型ハイブリット空調 スマートマルチ」が有効です。
多彩な運転モードのうち中央監視モードでは、下げDR要請に応じて「ガス優先運転」または「ガス単独運転」へ切り替えることで、空調を止めずに消費電力を大幅に抑制できます。「ガス優先運転」はEHPとGHPを併用しつつGHP主体で運転、「ガス単独運転」はEHPを停止しGHPのみで運転するモードです。
これにより、空調を停止することなく電力使用量を低減できるため、従業員の健康や作業効率を維持しながらDRへ柔軟に対応し、無理のない節電が可能です。
このような空調機器によるDR対応に加え、日々の運用における省エネも併せて図ることで、電力コストのさらなる削減と安定的な電力使用につながります。
また、パナソニックの省エネマネジメントサービス「Panasonic HVAC CLOUD」も、空調の快適性と省エネ性を両立することができる有効なソリューションです。AIが施設情報・空調設定・気象情報・時刻情報等を学習し、自動で温度制御を行うため、快適性を損なわずに従来の手動調整に比べて約20%(※)の空調消費電力量削減を実現します。さらに、空調機器本体以外に必要なのはアダプターとLTEルーターのみで、複数拠点の一括管理にも対応しているため、導入コストや管理工数を抑えられます。
※1年間、関東地方の2つの異なる物販店舗(約1,000㎡)の施設で検証。「設定温度自動リターン」機能(一定時間で指定した温度設定に戻る機能)との比較。
インセンティブ型は参加の条件がある
インセンティブ型のデマンドレスポンスは、参加するために一定の条件を満たす必要があります。例えば、「〇~〇時のあいだにデマンドレスポンスに参加できること」「一定時間停止できる設備を保有していること」や「自家発電設備を持っていること」といったものです。
常時稼働を続けなければならない設備しかない事業所などは参加が難しいでしょう。
まとめ
デマンドレスポンス(DR)とは、需要家が電力使用量を調整することで、電力の需給バランスを保つ取り組みです。再生可能エネルギーの普及により従来の供給側中心の調整では限界があり、デマンドレスポンスの必要性が高まっています。参加形態には電気料金型とインセンティブ型があり、調整手法には下げDRと上げDRがあります。
デマンドレスポンスを実施することで、電気代削減や、エネルギー使用の見直し、社会貢献などが可能です。ただし、体制構築のコストや無理な節電への注意が必要です。
パナソニックの提供する「Panasonic HVAC CLOUD」は、AI制御により快適性を保ちながら効率的な空調消費電力量削減を実現。デマンドレスポンスの活用を空調面からサポートします。