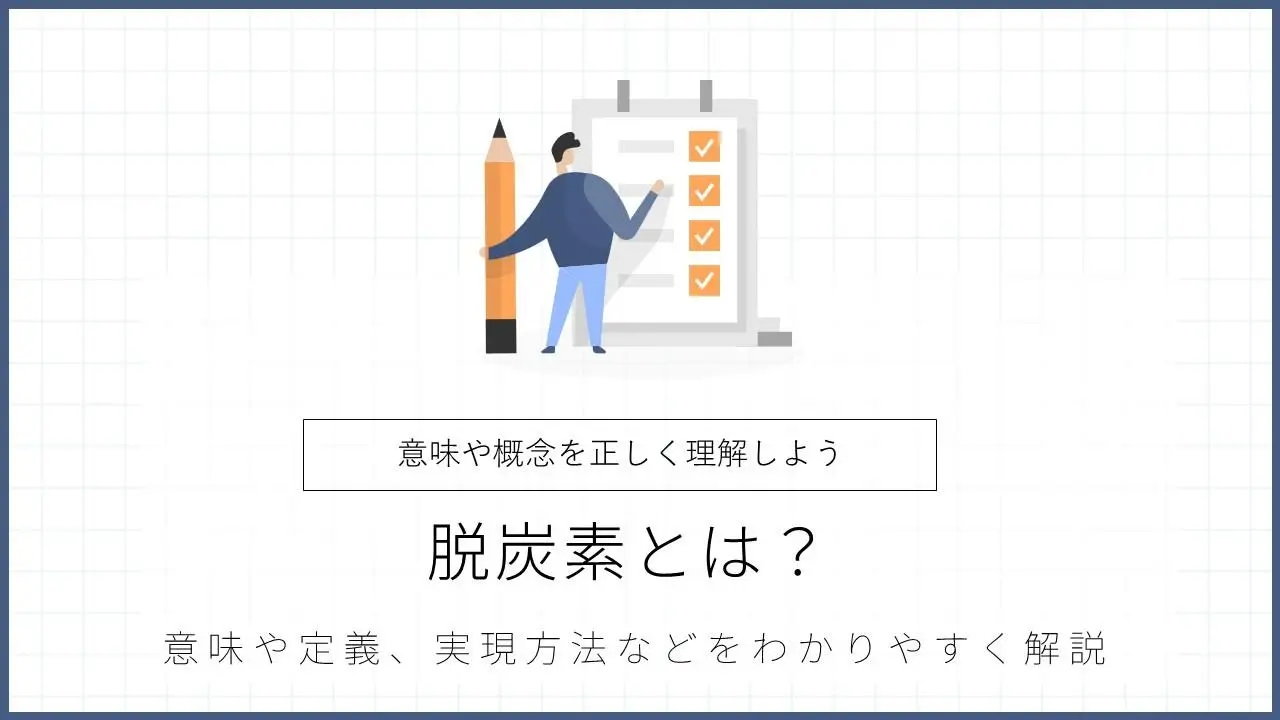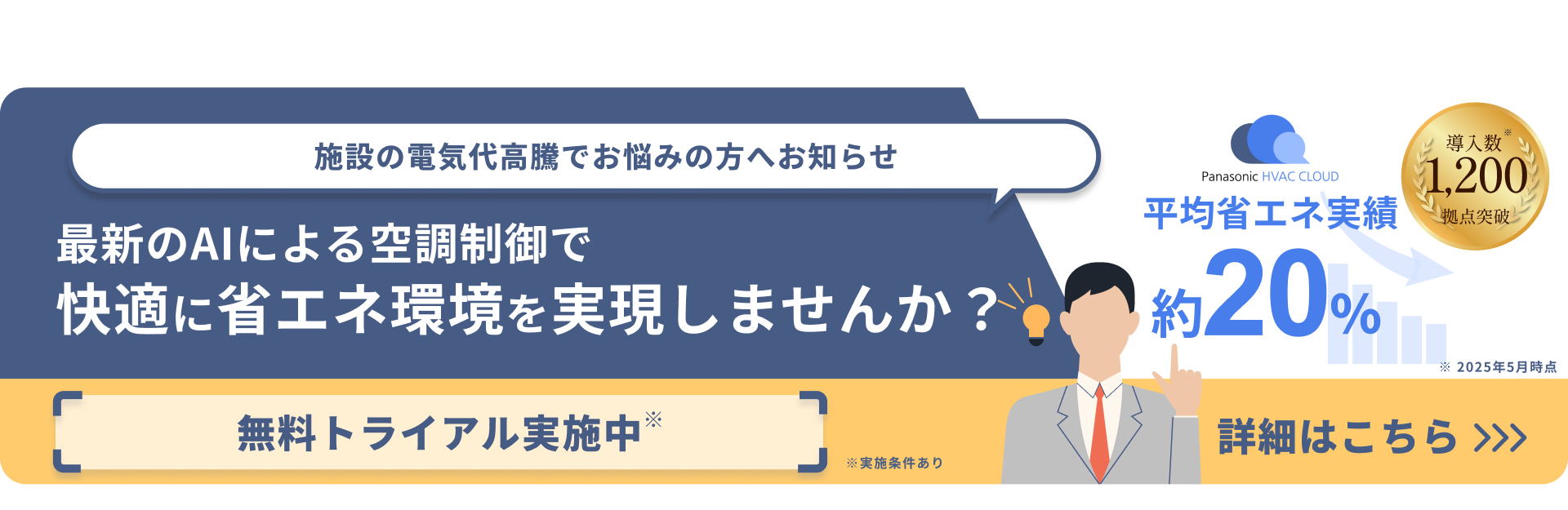近年「脱炭素」という言葉を耳にする機会が増えました。しかし、その意味や実現方法を正確に説明できる方は少ないかもしれません。脱炭素は地球温暖化対策として国際的に重要視されている概念であり、企業経営においても無視できない課題となっています。
本記事では、脱炭素とは何かという基本的な定義から、カーボンニュートラルとの違いや企業が脱炭素化を実施するメリット、実現に向けた具体的な取り組み方法まで、わかりやすく解説します。
まずは排出量をできる限り減らし、それでも避けられない排出分については、吸収や除去などで埋め合わせを行うというのが一般的な脱炭素の考え方です。
カーボンニュートラルとの違い
本来の意味での脱炭素は、CO2(二酸化炭素)を対象とし、排出量を削減してゼロにすることを意味します。一方、カーボンニュートラルは、CO2に加えてメタンやフロン類などを含む温室効果ガスの削減と吸収・除去によって「中立(ニュートラル)」することを意味します。
とはいえ、日本で排出する温室効果ガスの約9割をCO2が占めているため、脱炭素とカーボンニュートラルを同義として扱うケースがほとんどです。
■温室効果ガスの種類
- CO2(二酸化炭素)⇨日本で排出する温室効果ガスの約9割を占める
- メタン
- 一酸化二窒素
- フロンガス(ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六フッ化硫黄、三フッ化窒素)
脱炭素に関連する言葉の意味
脱炭素に関連する言葉として、以下のようなものがあります。
|
脱炭素社会 |
温室効果ガスの排出量が正味ゼロになった社会 |
|
脱炭素先行地域 |
環境省による「地域脱炭素ロードマップ」に基づき、2030年度目標(温室効果ガスの排出量を2013年比で46%削減)を達成するための取り組みを地域特性に応じて先行して実施する地域 |
|
脱炭素ドミノ |
脱炭素先行地域をモデルとして、その取り組みをドミノ倒しのように全国に広げていこうという考え方 |
|
脱炭素経営 |
気候変動の視点を取り入れた企業経営 |
脱炭素化が進んでいる理由
脱炭素化が急速に進んでいる背景には、温室効果ガスがもたらす地球温暖化の深刻化があります。この状況を受けて、2015年には「パリ協定」が採択され、世界共通の目標として平均気温の上昇を2℃未満、できる限り1.5℃に抑えることが合意されました。
これにより、各国で脱炭素化の動きが本格化しています。
温室効果ガスによる温暖化の進行
しかし、産業の発展や生活の変化により、温室効果ガスの排出量が増加しました。これまで海や森林によって保たれていた排出と吸収のバランスが崩れ、大気中に熱が溜まりやすい状態になっています。

実際、2020年時点で産業革命前に比べて約1.1℃上昇しており、猛暑、洪水、干ばつなど深刻な影響が各地で現れています。この状況は単なる気候変動を超え、人類の生存基盤を脅かす「気候危機」とまで呼ばれています。
将来の世代が安心して暮らせる社会を守るためにも、温室効果ガスの削減は急務といえるでしょう。
パリ協定での世界共通目標の合意
気候変動という地球規模の課題に対し、国際的な枠組みとして2015年に「パリ協定」が採択されました。日本を含む世界120以上の国と地域が以下の共通目標に合意したことで、脱炭素社会の実現に向けた取り組みが本格化しました。
- 世界的な平均気温上昇を工業化以前に比べて2℃より十分低く保つとともに(2℃目標)、1.5℃に抑える努力を追求すること(1.5℃目標)
- 今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均衡を達成すること
さらに、国連の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」による「1.5℃特別報告書」では、世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて1.5℃以内に抑えるためには、2050年ごろまでに脱炭素を実現する必要があると報告しています。それを受けて、日本政府は2050年のカーボンニュートラル・脱炭素社会の実現をめざすと宣言しました。
さらに、中間目標として、2030年度までに2013年度比で温室効果ガスの排出量を46%削減する方針を掲げ、具体的な取り組みが進められています。
脱炭素社会をめざす方法
温室効果ガスの約9割をCO2が占めるということをふまえると、脱炭素化を実現するにはCO2削減に取り組むことが効果的です。中でも、CO2の排出量が最も多いのが「エネルギー転換部門」で、全体の約38.3%を占めています。ここでの排出源は主に電気をつくる火力発電所です。
引用:4-04 日本の部門別二酸化炭素排出量(2023年度)
また、産業部門や運輸部門、その他部門などの分野においても、それぞれ電力使用に伴うCO2排出量が含まれています。そのため、CO2削減を進めるには、電力使用量の削減が非常に大きな役割を果たします。
以下に、電力使用量の削減をはじめとした、脱炭素化に役立つ具体的な取り組み例をまとめました。
|
脱炭素化の一例 |
詳細 |
|
既設機器のエネルギーの使い方を見直す |
使っていない部屋の照明や空調を消す、無理のない範囲で空調の設定を調整するなど |
|
省エネ設備の導入・更新 |
蛍光灯からLED照明に替えるなど |
|
再エネ設備の導入・再エネ電力の購入 |
CO2を排出しない太陽光発電や風力発電などの再エネ設備を導入、または再生可能エネルギーを調達できる電力プランに切り替える |
|
環境負荷を考慮した移動手段の選択 |
自転車や徒歩での移動、ガソリン車からEV車への乗り換え |
|
カーボン・オフセットの活用 |
温室効果ガスの削減に努めたうえで、どうしても排出を避けられない分を、排出量に見合った削減活動に投資することで埋め合わせようとする取り組み |
どれから手を付ければよいか迷う場合は、まずはすぐに実行できる行動から始め、徐々に取り組みを広げていくことが大切です。例えば、使っていない部屋の照明や空調をこまめに切る、車の利用を控えて公共交通機関を使うなどは今日からでも実践できます。
とくに、事務所やビル、商業施設などでは、業務用エアコンが最も大きなエネルギー消費を占めるため、空調を中心とした省エネ対策はCO2削減効果が大きいといえます。
省エネ対策をさらに効率よく進めるために、設備やシステムを導入するという方法もあります。
例えばパナソニックの「Panasonic HVAC CLOUD」は、AIが空調の設定温度を自動制御する省エネマネジメントサービスです。従来の人による設定温度調整と比較して約20%の空調消費電力量の削減効果(※)を確認しています。システム導入時に空調機器本体以外で必要なのはアダプターとLTEルーターのみのため、安価なコストで導入が可能です。クラウドサービスのため、複数拠点(店舗A・店舗B・店舗Cなど)の一括管理にも対応しており、管理工数も抑えられるのが魅力です。
※1年間、関東地方の2つの異なる物販店舗(約1,000㎡)の施設で検証。「設定温度自動リターン」機能(一定時間で指定した温度設定に戻る機能)との比較。
脱炭素化を実施するメリット
カーボンニュートラルを目指すには、設備投資や業務フローの見直しなど、一定の手間やコストがかかります。しかし、それを上回る多くの経営上のメリットがあります。
- 設備の省エネ化や業務プロセスの改善によりエネルギー使用量が減り、長期的なエネルギーコスト削減につながる
- 環境意識が高まっている昨今、脱炭素への取り組みが取引先との関係性の構築や新たな取引先の獲得に結びつく
- 行政やメディアから先進的な事例として紹介されることで、自社の知名度や認知度の向上が期待できる
- ESGなど非財務情報の重要性が増しているため、取り組みを進めることで資金調達が有利になる
- 社会的責任を果たす企業を選ぶ動きが広がっており、社員のモチベーション向上や人材の採用強化に寄与する
まとめ
脱炭素とは、温室効果ガスの排出量を正味ゼロにすることを指し、地球温暖化対策として必要不可欠な取り組みです。カーボンニュートラルとよく似た言葉ですが、定義上は異なる概念です。ただし、日本では温室効果ガスの約9割をCO2が占めていることから、同義として扱われることが一般的になっています。
脱炭素化を進めるうえで有効なのが、電力使用量の削減です。とくに空調は事務所やビルで最大のエネルギー消費を占めるため、省エネ対策の中心として取り組む価値があります。パナソニックの「Panasonic HVAC CLOUD」のようなAIを活用したシステムを活用すれば、手間をかけずに効率的な省エネを実現できます。
脱炭素への取り組みは、コスト削減だけでなく、企業価値の向上や競争力の強化にもつながる重要な経営戦略といえるでしょう。