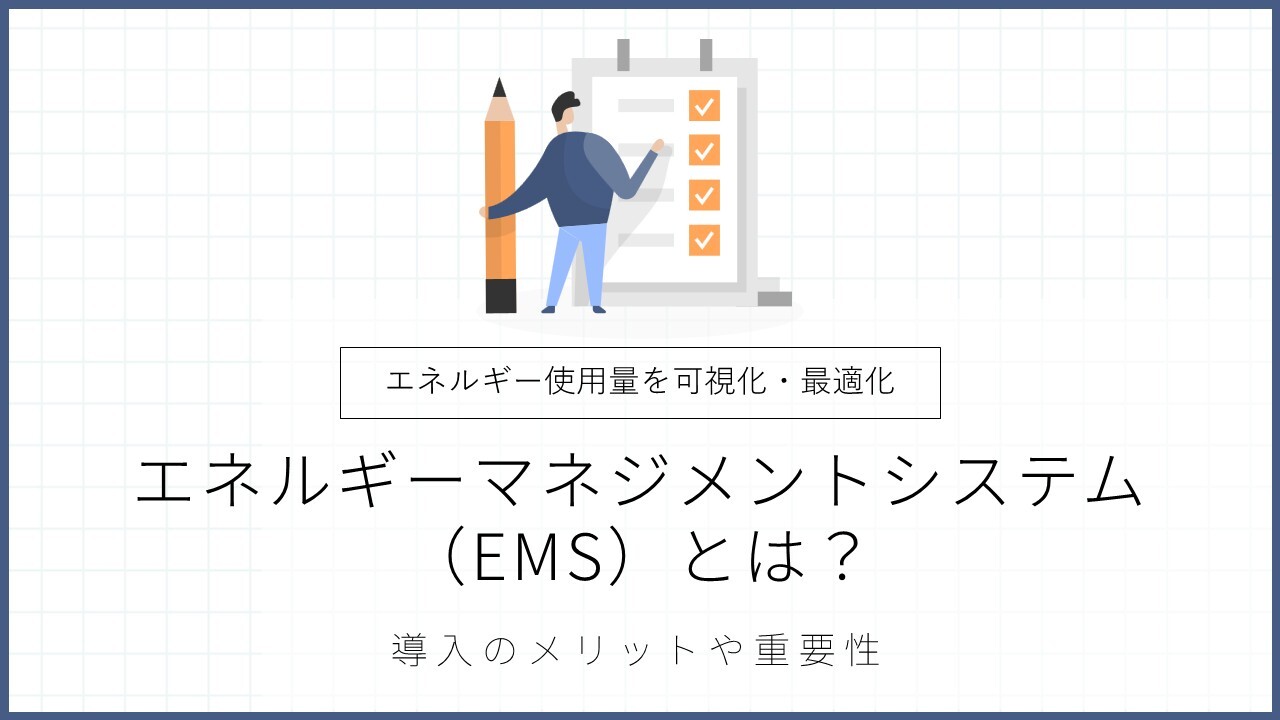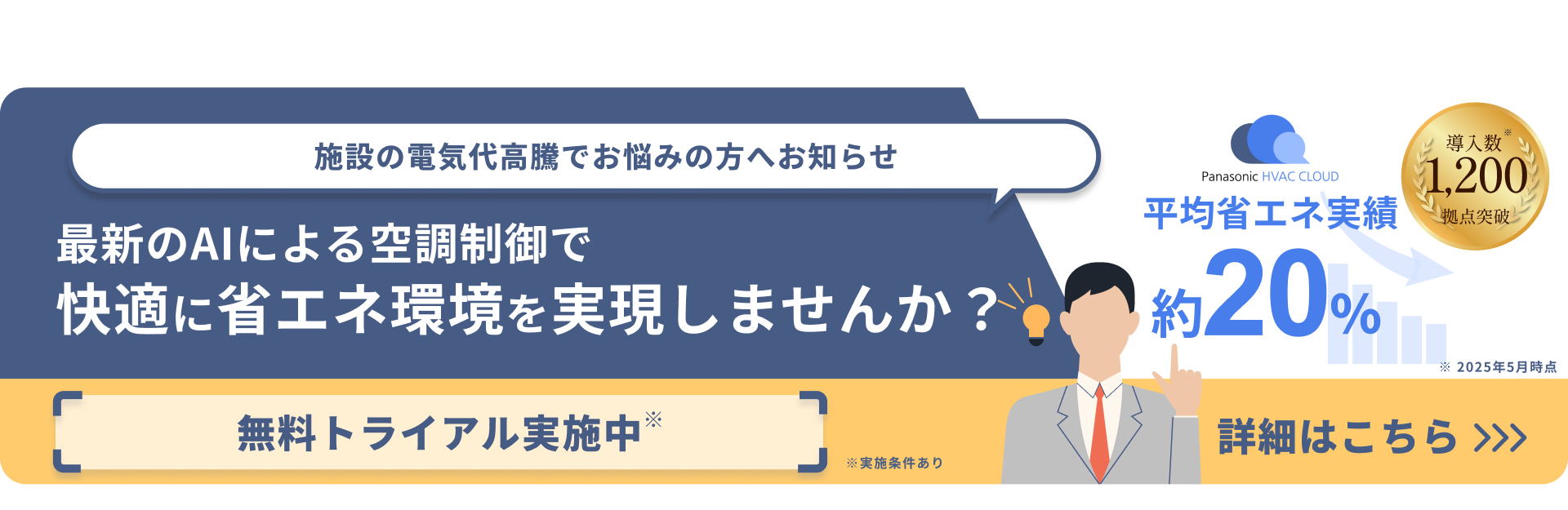エネルギーマネジメントシステム(EMS)とは、エネルギーの使用状況を「見える化」することで、エネルギー運用の最適化を図るシステムです。
エネルギーの使用状況を把握することで、ムダなエネルギーの特定と、そのデータに基づいた省エネ対策を講じることによる電気料金の削減が可能になります。また、経年劣化やトラブルの釣行の早期発見、環境負荷の低減もメリットといえるでしょう。
さらに、エネルギーマネジメントシステムは「エネルギーの安定供給」と「脱炭素社会の実現」という、国が掲げる重要な目標の達成にも大きな役割を果たします。
本記事では、エネルギーマネジメントシステムの基本的な仕組みや、導入のメリット、そして課題、導入事例などを紹介します。
この記事で
わかること
- エネルギーマネジメントシステムとは何か
- エネルギーマネジメントシステム導入のメリット
- エネルギーマネジメントシステムの導入事例
エネルギーマネジメントシステムとは
エネルギーマネジメントシステム(EMS)とは、情報通信技術(ICT)を活用してエネルギーの使用状況を可視化・最適化するシステムのことです。
建物で使われているエネルギーの使用状況に応じて設備(空調や照明など)の運転を制御し、省エネとコスト削減を図ります。
具体的な仕組みとしては以下の3つのステップで構成されています。
1.情報収集
建物に設置された人感センサーや温度・湿度センサー、カメラ、エネルギー機器等からエネルギーの使用状況を収集・蓄積する
2.分析
収集・蓄積したデータの分析を行い、今後の需要を予測
3.制御
エネルギー需要の予測などをもとに、空調や照明などの設備の運転を手動または自動で制御(自動制御の可否はシステムによる)
エネルギーマネジメントシステムの導入によって具体的にどのようなことが実現できるのか、詳しく見ていきましょう。
「エネルギーの使用状況を把握」できる
従来、エネルギーの使用状況を把握するには、月々のガス・電気料金の請求書に書かれた建物全体の使用量をもとに判断するしかありませんでした。
しかし、エネルギーマネジメントシステムを導入すれば、「いつ」「どこで」「どれくらい」「どのように」エネルギーを使用しているのかを具体的に確認することが可能です。
これにより、以下のようなことが可能になります。
1.エネルギーのムダを特定できる
2.データに基づいた省エネ対策を講じることができる
3.「把握」と「改善」を繰り返すことでエネルギーコストの削減ができる
4.設備の劣化や不具合の早期発見ができる
①エネルギーの「ムダ」を特定できる

省エネ化を進めるうえで、まず重要なのが、エネルギー使用状況の「見える化」です。やみくもに省エネ対策を講じても、十分な効果が得られなかったり、コストがかかりすぎたりするためです。
②データに基づいた省エネ対策を講じることができる
例えば、空調の消し忘れで不要な電力消費が発生している場合、タイマー設定を行うなどして無駄な消費を抑えることが可能です(自動制御のシステムなら自動で調整)。
このような運用の見直しにより、電力使用量やピーク電力を抑制し、電気料金の削減を図れます。
③「把握」と「改善」を繰り返すことでエネルギーコストの削減ができる
「把握」と「改善」を繰り返すことで、一時的な省エネ対策にとどまらず、長期的かつ継続的にエネルギーコストの削減につなげられます。エネルギーコストの抑制には継続した運用改善が有効です。

④設備の劣化や不具合の早期発見ができる
電力使用量の急激な上昇や異常な消費パターンを発見することで、経年劣化やトラブルの兆候を事前に察知し、突然の故障による影響を未然に防ぐことができます。老朽化や不具合により稼働率が低下した機器の特定も容易になるでしょう。
「環境負荷低減への貢献」ができる
エネルギーマネジメントシステムによる効率的な運用によってエネルギーのムダを削減すれば、CO2排出量の削減にも貢献できます。持続可能な社会を支える取り組みとして評価され、企業としての信頼獲得につながるでしょう。
また、消費エネルギーに基づいてCO2排出量を算定することが可能となり、具体的な省エネ化の効果を数値で示すことができます。この視覚的なデータは、省エネ施策の効果を関係者に報告する際にも役立つはずです。
「室内環境を損なわずに省エネ」ができる
通常、「省エネ」というと、温度設定を低くしたり、空調の使用を制限したりするなどの「我慢」や「妥協」が伴うイメージがあるかもしれません。
しかし、エネルギーマネジメントシステムは、エネルギーの「ムダ」を削減することで省エネを実現するシステムです。
データに基づいて設備の使用状況を最適化し、無駄なエネルギー消費を防ぎます。そのため、室内環境の快適さを損なうことなく、効率的な省エネが可能となるのです。
エネルギーマネジメントシステムの種類
エネルギーマネジメントシステムは、エネルギーの最適化を図るという基本的な仕組みは同じですが、対象とする建物や適用範囲に応じて種類があります。
詳しくは以下の表にまとめました。
|
EMSの種類 |
対象 |
詳細 |
|
BEMS (Bilding Energy Management System) |
ビル等 |
商業ビルなどの、受変電設備、空調・衛生設備、照明設備のエネルギー最適化を図るシステム |
|
FEMS (Factory Energy Management System) |
工場 |
BEMSの適用範囲に加え、生産設備のエネルギー最適化を図るシステム |
|
HEMS (Home Energy Management System) |
一般家庭 |
家庭内で使用する設備のエネルギー最適化を図るシステム |
|
MEMS (Mansion Energy Management System) |
マンション |
マンション内で使用する設備のエネルギー最適化を、導入拠点または遠隔で行うシステム |
|
CEMS (Community Energy Management System) |
地域全体 |
地域内のビルや家庭、工場などをITネットワークなどでつなぎ、地域全体のエネルギー最適化を図るシステム。また太陽光発電や風力発電を活用し、電力需要の予測に基づいて供給量を調整することもある。 |
エネルギーマネジメントシステムが注目されている背景
エネルギーマネジメントシステムが注目される背景には、国が掲げる「エネルギーの安定供給」「脱炭素社会の実現」という2つの社会的目標と、昨今の「電気代の高騰」が関わっています。
日本はエネルギー自給率が低く、多くのエネルギーを海外から輸入しているのが現状です。
供給が滞れば経済活動や国民生活に大きな影響を及ぼすため、国はこれまでも省エネ政策や再生可能エネルギーの普及に取り組んできました。しかし、依然として石油や石炭、天然ガスといった化石燃料への依存度は80.8%(※1)と高いままです。
加えて、化石燃料は地球温暖化の一因であるCO2を排出します。CO2排出量の割合を部門別に見ると「業務その他部門」が全体の19%を占め、そのうちの約7割が電力消費に由来しているのです。
したがって、「エネルギーの安定供給」と「脱炭素社会の実現」を実現するには、エネルギーの消費量を減らすことが不可欠です。
そこで国は、限りある資源と環境を守るために、エネルギーマネジメントシステムの本格的な普及に取り組み、エネルギーの削減・効率的な運用を目指しているのです(※3)。
また、東日本大震災によって電力供給のバランスが崩れ、電気代が高騰したことも、エネルギーマネジメントシステムの導入が進んだ要因となっています。
これをきっかけに、省エネや電気代削減の取り組みの一環として、多くの企業がエネルギーマネジメントシステムを導入するようになりました。
さらに、近年の電気代の高騰を受け、エネルギーマネジメントシステムは再び注目を集めています。
(※1)出典:令和5年度(2023年度)エネルギー需給実績を取りまとめました(速報)|経済産業省
(※2)出典:2022年度(令和4年度) 温室効果ガス排出・吸収量について|環境省
(※3)出典:「スマートエネルギーマネジメントシステムの構築」|内閣府
エネルギーマネジメントシステム導入の課題と解決策
エネルギーマネジメントシステムの導入による経済性・社会的評価によるメリットや必要性は高いものの、実際には以下のような理由で実施が難しいケースもあるでしょう。
|
資金調達力 |
省エネのための初期投資が調達できない |
|
リスク |
先のことはよくわからないため、短期間に投資回収できる省エネしか実施しない |
|
情報不足 |
どうすれば省エネできるかについて情報が不足 |
|
動機の不一致 |
オーナー・テナント問題など、主体間の思惑が一致しないため、省エネが進まない |
|
定合理性 |
時間や気持ちの余裕がなく、検討能力にも限界があるため、最適な選択が出来ない |
|
隠れた費用 |
見過ごされやすい費用の存在(取引費用、機会費用) |
|
惰性 |
従来からのやり方を変えることへの抵抗 |
|
関心・意識 |
省エネへの関心が欠けていると、省エネが進まない |
|
組織構造 |
組織の縦割り構造などのために、すべき対策はわかっているのに、省エネが進まない |
|
施工の難易度 |
既築の建物に後からシステムを導入する場合、施工面で難易度が高くなることがある |
引用:エネルギーマネジメントの全体像|経済産業省
既築建物への施工が難しいという課題に対しては、パナソニックの「Pnasonic HVAC CLOUD」が効果的です。シンプルな機器構成とクラウドベースの仕組みにより、後付け設置が容易であることが特徴です。
省施工でエネルギーマネジメントシステムの導入が実現できます。
エネルギーマネジメントシステムの導入におけるよくある課題として、コスト面と技術面が挙げられます。
とくに中小規模の建物では、大規模な建物と同じシステムを導入しても費用対効果が低く、運用するための専門技術者が不足していることが多いため、導入に対してハードルが高いと感じる場合が少なくありません。コスト面の課題を解決するためには、導入前に十分な試算を行い、費用対効果をよく検討することが重要です。
また、初期費用の負担軽減に効果的な補助金の活用も欠かせません。例えば、令和7年度には「再生可能エネルギー導入拡大に向けた分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金」や「エネルギー構造高度化・転換理解促進事業」などの補助金が提供されています。
さらに、初期投資の回収や運用の難易度が高くならないよう、建物の規模や使いやすさにも考慮してシステムを選ぶことが大切です。
パナソニックでは、コスト面や技術面での課題に応えるため、高圧小口需要家向けに、使いやすさとコスト面を見直した「Emanage(エマネージ)」を提供しています。
エネルギーマネジメントの導入事例

エネルギーマネジメントシステムの導入事例として、パナソニック関東設備株式会社を紹介します。
パナソニックでは、持続可能な社会の実現に向けて、省エネルギー機器の開発やシステムの提供を進めるとともに、当社の拠点における省エネ化にも積極的に取り組んでいます。その一環として、新社屋に高効率機器の導入とエネルギーマネジメントシステムの導入を実施しました。
パナソニックの「Panasonic HVAC CLOUD」はAIを活用したエネルギーマネジメントシステムで、空調の消費電力量を約20%削減した実績(※)があります。
また、デジタルサイネージを設置することで、エネルギー使用状況を視覚的に把握しやすくし、従業員一人ひとりの省エネ意識の向上にもつながっています。
(※)1年間、関東地方の2つの異なる物販店舗(約1,000㎡)の施設で検証。「設定温度自動リターン」機能(一定時間で指定した温度設定に戻る機能)との比較。
まとめ
エネルギーマネジメントシステムは、エネルギーの使用状況を「見える化」することで、エネルギー運用の最適化を図るシステムです。
省エネを進める第一歩は、まずエネルギーの使用状況を「見える化」し、どこにムダがあるのかを把握することから始まります。エネルギーマネジメントシステムを導入することで、エネルギーの使用状況を具体的に把握できるようになるため、適切な省エネ対策を講じることが可能です。さらに、「把握」と「改善」を繰り返すことで、継続的なエネルギー削減につながり、省エネ効果の向上も期待できるでしょう。
このような取り組みは、企業のコスト削減だけでなく、国が掲げる「エネルギーの安定供給」や「脱炭素社会の実現」という目標に貢献するものです。企業にとっても、持続可能な社会の実現に向けた社会的責任を果たすうえで、エネルギーマネジメントシステムの活用は重要な役割を担っています。
しかし、導入にはコスト面や技術面での課題もあります。初期投資や投資回収の計画をしっかりと立て、建物の規模や予算、使いやすさなどを考慮したうえで最適なシステムを選ぶことが大切です。とくに、投資回収の観点では、建物内で最も電力を消費する空調設備のエネルギーマネジメントを行うことが効率的といえるでしょう。
パナソニックでは、お客さまのニーズに柔軟に対応できるよう、高圧小口需要家向けに使いやすさとコスト面を見直した「Emanage(エマネージ)」や、あらゆる規模に対応可能な空調設備のエネルギーマネジメントシステム「Panasonic HVAC CLOUD」など、ニーズに合わせたソリューションをご用意しております。
エネルギーマネジメントシステムの導入をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。