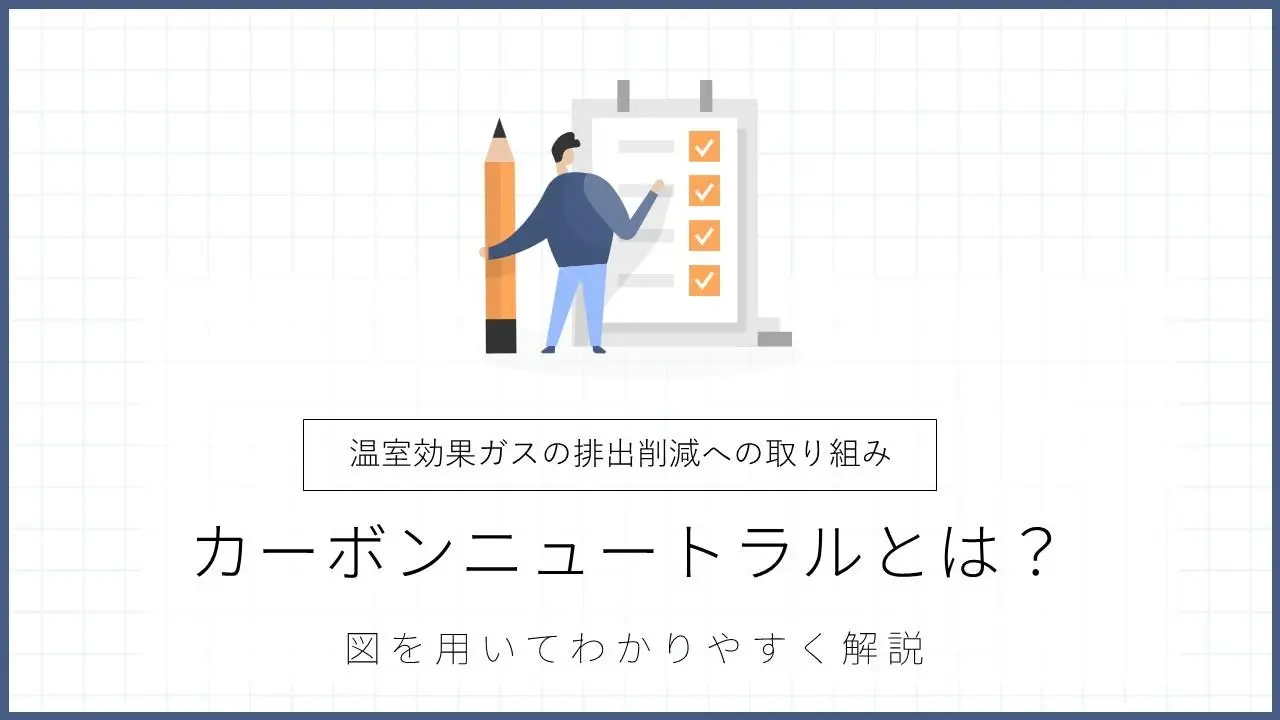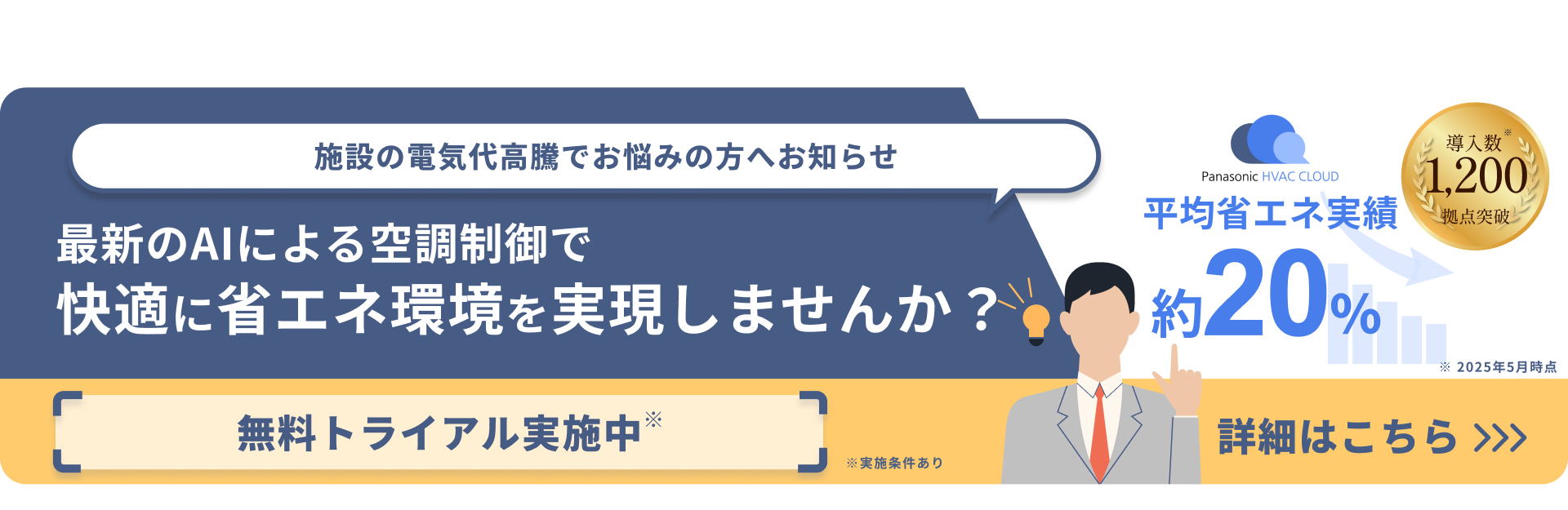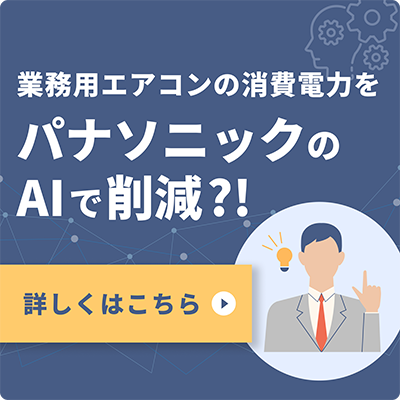「カーボンニュートラル」という言葉を、ニュースや企業の取り組みで目にする機会が増えています。しかし、言葉としては聞いたことはあっても、「実際にはどんな意味なのか、どんな仕組みなのか」はあまり知られていないかもしれません。
この記事では、カーボンニュートラルとは何か、なぜ必要とされているのか、そして企業はどう取り組めばよいのかを、図を交えながら分かりやすく解説していきます。
カーボンニュートラルとは
カーボンニュートラルという概念を理解するためには、まずその基本的な定義と仕組みを把握することが重要です。カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出を「全体としてゼロ」にするということを指します。
「全体としてゼロ」とはどういう意味?
カーボンニュートラルの中心となるのが、「全体としてゼロ」という考え方です。温室効果ガスの排出を完全にゼロにすることは現実的には困難であるため、できる限り排出量を減らすことが求められます。
そのうえで、どうしても減らしきれない分については、植林や森林保全による「吸収」や、CO2(二酸化炭素)を回収するような技術によって「除去」することで、差し引きゼロに近づけていくのです。
つまり、排出した分を別の方法で打ち消すような「排出量-(吸収量+除去量)=正味ゼロ」という計算で成り立っています。
そもそも温室効果ガスって何?
|
<温室効果ガスの種類>
|
温室効果ガスとは、太陽の熱を地表付近の大気中に閉じ込める性質を持つガスのことです。
この働きがあるおかげで、地球の平均気温は約14℃に保たれています。もし温室効果ガスが一切なければ、地表の温度は氷点下19℃にまで下がるとされており、私たちの暮らしは成り立ちません。
ただし、温室効果ガスの量が増えすぎると、大気中に閉じ込められる熱の量が増え、地球全体の気温が上昇します。この現象が「地球温暖化」であり、現在、深刻な環境問題のひとつとなっています。

脱炭素との違い
カーボンニュートラルと似た言葉に「脱炭素」があります。一般的には、脱炭素はCO2の排出量を削減する取り組みをいいます。一方で、カーボンニュートラルはCO2だけでなく、メタンやフロン類などの温室効果ガス全体を実質的にゼロにすることを指します。
つまり、脱炭素は「CO2の排出量」を「削減してゼロをめざす」のに対し、カーボンニュートラルは「温室効果ガス」を「削減・吸収・除去により正味ゼロをめざす」という違いがあります。
しかし、日本が排出する温室効果ガスの約9割がCO2であることから、「カーボンニュートラル=脱炭素」と同じ意味合いで使われることも多いのが現状です。
日本がカーボンニュートラルをめざす目的
|
地球の平均気温は、2020年時点で産業革命以前(1850~1900年)と比べてすでに約1.1℃上昇しており、放置すればさらなる気温上昇が避けられないとされています。このまま対策を講じなければ、さらに気温が上がっていくと予測されています。
気温の上昇は、集中豪雨や猛暑の頻発だけでなく、農林水産業・水資源・生態系・自然災害・健康・産業・経済活動など、私たちの生活すべてに影響を及ぼしかねません。こうした問題はもはや「気候変動」ではなく、「気候危機」と呼ばれるようになっています。だからこそ、持続可能な社会を築いていくために、温室効果ガスの排出を「正味ゼロ」にするカーボンニュートラルへの取り組みが不可欠です。
カーボンニュートラルの実現はいつまでに必要なのか
パリ協定では、今世紀後半のカーボンニュートラル実現を目標に掲げています。国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が発表した「1.5℃特別報告書」では、世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて1.5℃以内に抑えるためには、2050年ごろまでにカーボンニュートラルを達成する必要があると報告されました。
これらを踏まえて、2050年までにカーボンニュートラルを実現する動きが国際的に広まっています。また、各国は中間目標も自主的に設定しており、日本では2030年度までに温室効果ガスの排出量を2013年度比で46%削減することを掲げています。
カーボンニュートラル実現に向けた国の動き
日本で排出する温室効果ガスは年間で12億トンを超えています。2050年までにこれだけの量を実質ゼロにするには、国や自治体、事業者だけでなく、日本全体での取り組みが必要だとして、国はさまざまな取り組みを行っています。
その一部として以下3つを紹介します。
|
脱炭素事業への出資制度 |
カーボンニュートラル実現に取り組む民間事業者等を対象に投融資を実施 |
|
デコ活の推進 |
国民・消費者1人ひとりの意識と行動を後押しするための国民運動「デコ活」の実施 |
|
気候変動の国際交渉 |
気候変動に関する国際会議「COP(コップ:Conference of the Parties)」において地球温暖化対策および気候変動に係る国際交渉を実施 |
企業がカーボンニュートラルに取り組むメリット
企業経営において、カーボンニュートラルの実現はもはや避けて通れない課題となっています。投資家や消費者、そして社会全体が環境意識を高める中で、企業がこの問題にどう向き合うかが、企業の信頼性やブランド価値に直結する時代です。
一方で、カーボンニュートラルの実現には、業務の見直しや省エネルギー設備の導入などにかかる投資が必要となるため、コスト面を懸念する企業も少なくありません。しかし、それを上回る多くのメリットがあることも理解しておくべきです。
- 優位性の構築
いち早くカーボンニュートラルに取り組むことで、業界内での先進的な立場を確立し、良いイメージを獲得できる - エネルギーコストの削減
省エネ設備の導入により、長期的にエネルギーコストを削減できる - 知名度・認知度の向上
カーボンニュートラルの取り組みがメディアに取り上げられることで、自社を知ってもらうきっかけが増える。それによって売上の増加も期待できる - 社員のモチベーションや採用力の向上
サステナブルな企業に魅力を感じる求職者が増加しており、社員の誇りや働きがいにもつながる - 資金調達面での優遇
カーボンニュートラルへの取り組みは、企業の持続可能性や将来性を評価する重要な指標とされつつあり、資金調達が有利になる
カーボンニュートラル実現のステップ
企業がカーボンニュートラルをめざして取り組む際は、いきなり排出削減に取りかかるのではなく、「知る」「測る」「減らす」の段階的なステップに沿って進めていくことが重要です。さらに「発信」を加えることで、社内外への理解促進や評価向上にもつながります。
|
知る |
自社を取り巻くカーボンニュートラルの動きを知り、方針を検討する |
|
測る |
温室効果ガスの排出量を「活動量×係数」で算定し、削減のターゲットを特定する
|
|
減らす |
特定したターゲットでどのような削減対策が実施可能であるかをリストアップし、計画を策定する |
|
+α 発信 |
自社が行った取り組みを社内・社外に向けて発信する |
まずはカーボンニュートラルについて知ることから始めます。セミナーや講演会、他社の事例、地方自治体や商工会議所などの相談窓口などを活用して情報を集め、自社で取り組めることは何かを考えましょう。
次に行うのは、温室効果ガスの排出量の見える化です。事業所単位(事業所A・事業所B)や、事業活動単位(電気・軽油など)で温室効果ガスの排出量を算定し、優先して取り組むべき分野を特定します。
削減すべき対象が見えたら、具体的な対策をリストアップし、段階的に導入していきます。
例えば、「こまめに照明を消す」といった日常的な省エネ行動から始め、徐々に設備投資やシステム導入へと進めるのが現実的です。
例えば空調の分野では、パナソニックの「Panasonic HVAC CLOUD」が有効です。AIが空調の設定温度を自動制御することで快適性を保ちながら約20%の空調消費電力量削減効果(※)を実現します。また、自動で省エネ実績レポートを作成してくれるため、施策の効果検証や改善にも活用できます。
さらに、これらの取り組みを発信することで、社員一人ひとりの意識向上や行動変容が期待でき、組織全体としての推進力が高まります。社外に向けて発信すれば、「環境配慮型の企業」として認知され、ブランドイメージの向上や新たな取引先の開拓、自治体・関係企業との連携、新卒採用などの面でプラスに作用します。
検証と見直しを繰り返しながら、カーボンニュートラルの取り組みをレベルアップしていきましょう。
※1年間、関東地方の2つの異なる物販店舗(約1,000㎡)の施設で検証。「設定温度自動リターン」機能(一定時間で指定した温度設定に戻る機能)との比較。
まとめ
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出を「全体として実質ゼロ」にする取り組みです。単にCO2を出さないことではなく、排出をできるだけ減らし、吸収や除去の手段も組み合わせて、温室効果ガス全体のバランスをゼロに近づけるという考え方です。
日本では2050年までのカーボンニュートラル実現を目標に掲げており、企業にとっても法的義務を超えた経営上の重要な課題となっています。企業がカーボンニュートラルに取り組むことで、優位性の構築、エネルギーコスト削減、企業価値向上など多くのメリットを得られます。
実現に向けては、「知る」「測る」「減らす」「発信」というステップを踏んで段階的に取り組むことが効果的です。日々の省エネ行動に加え、AIやIoTを活用したシステム導入など、複数の手段を組み合わせることが求められます。
パナソニックの「Panasonic HVAC CLOUD」のようなAI制御システムは、快適性を保ちながら大幅な空調エネルギーの削減を実現できるソリューションです。ぜひ、カーボンニュートラル達成に向けた具体的な一歩として、導入を検討してみてください。