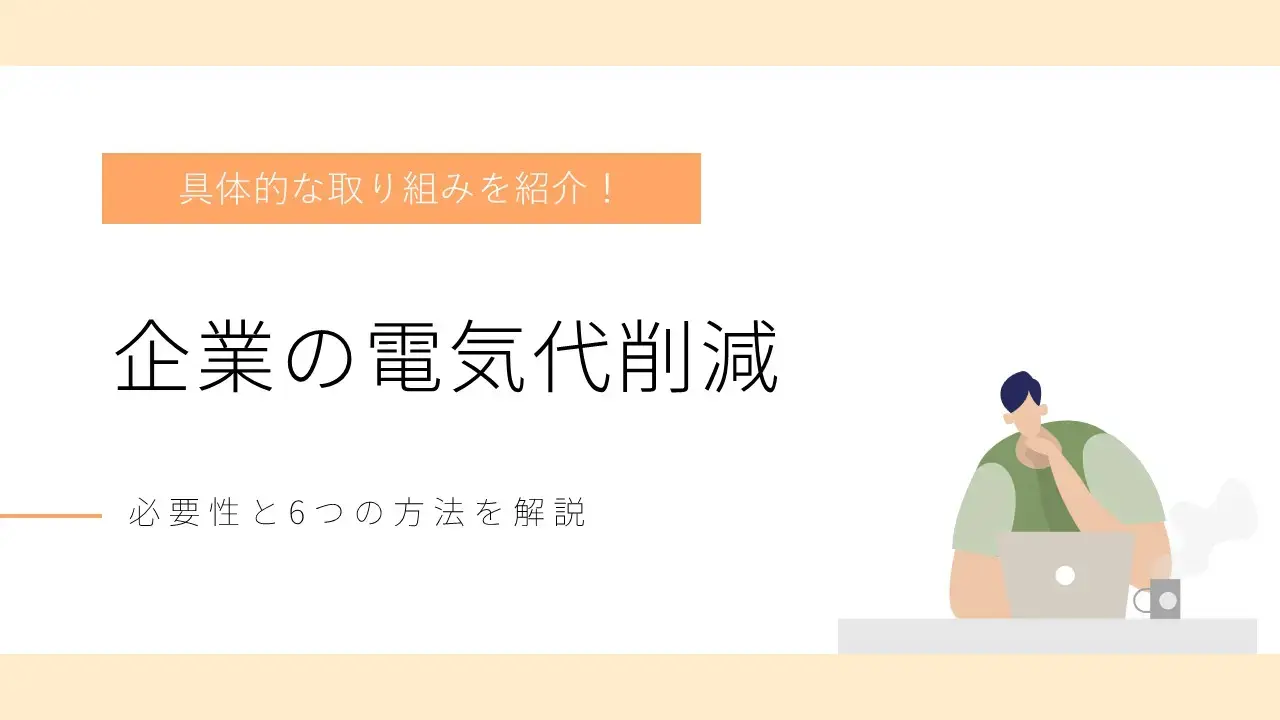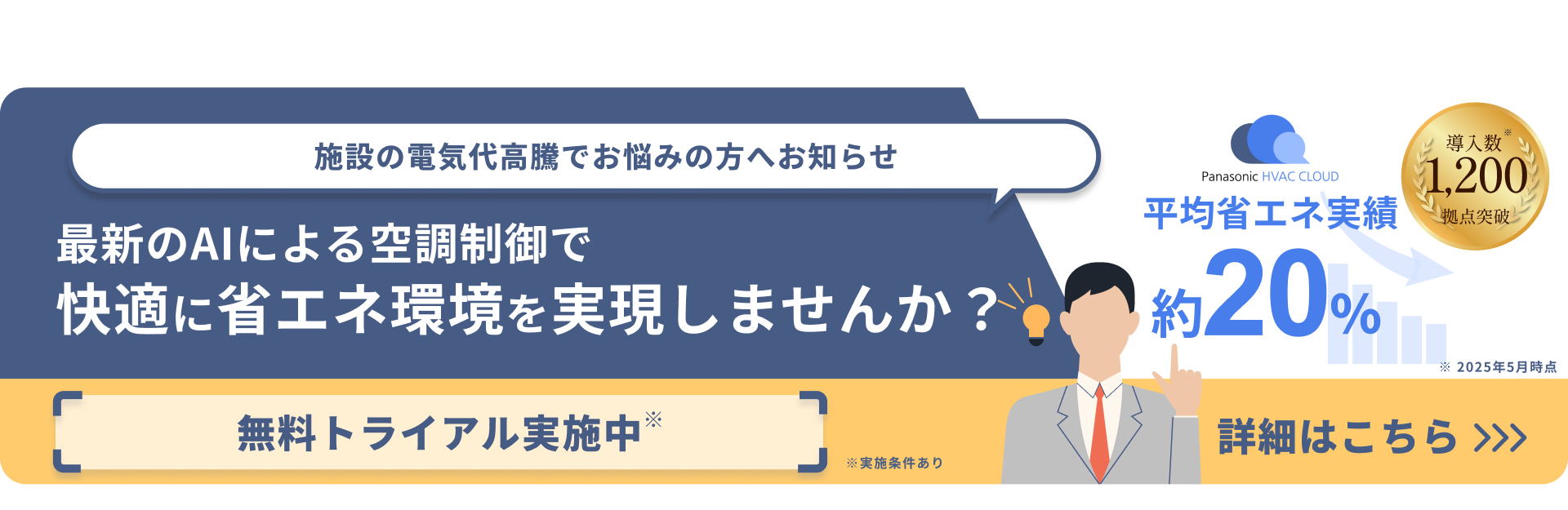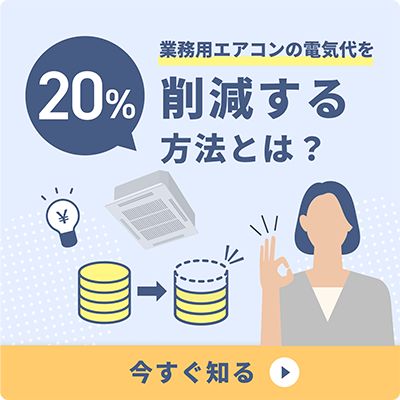昨今の電気代高騰により、企業の経営負担は増加しています。エネルギー価格の上昇や再生可能エネルギーの賦課金増加など、複数の要因が重なり、電気代削減は企業にとって避けて通れない重要な課題です。
本記事では、企業が電気代削減を行う必要性と、効果的な6つの削減方法について、詳しく解説します。
企業が負担する電気代が年々高騰!削減への取り組みが急務
昨今の電気代高騰は、企業にとっても小さくない経営負担となっています。この負担を軽減するためには、電気代の削減が重要です。
日本はエネルギー資源の多くを海外からの輸入に依存しているため、資源価格の影響を受けやすい状況にあります。
実際に、ウクライナ侵略をはじめとした社会情勢の緊張や、急激な気温変化による空調需要の増加、自然災害による供給不足など複数の要因が重なり、2021年後半以降、エネルギー価格は歴史的な高騰を記録しました。
引用:3.経済性|資源エネルギー庁
さらに、太陽光発電などの再生可能エネルギーの普及促進のために需要者から回収される賦課金の増加も電気代上昇の一因となっています。
こうした状況下で、企業が持続可能な経営を実現するためには、電気代の削減は避けて通れない課題といえるでしょう。
企業が電気代を削減する6つの方法
企業が電気代削減を効果的に進めるためには、複数のアプローチを組み合わせることが重要です。
ここでは、すぐに取り組める省エネ推進から、長期的な投資効果が期待できる設備導入まで、実践的な6つの方法をご紹介します。
【1】組織全体で省エネを推進する
電気代削減の第一歩は、組織全体で省エネ意識を高めることです。
従業員一人ひとりが日常業務のなかで省エネを意識し、無駄な電力使用を控えることが重要になります。システムの導入や設備更新のように時間とコストを伴わず、ルールを決めて周知するだけで実践できる取り組みです。
具体的な方法と、オフィスビルにおける取り組みの効果は以下の通りです。
|
取り組み |
建物全体の省エネ効果 |
|
使用していない照明を消灯する |
[冬季]2.9% [夏季]3.3% |
|
無理のない範囲で空調の温度を下げる |
[冬季]3.4% [夏季]4.1% ※冬季は設定温度を22℃から20℃に下げた場合、夏季は26℃から28℃に上げた場合 |
|
使用していない空調を停止する |
[冬季]1.7% [夏季]2.4% |
|
OA機器の電源を切るか、スタンバイモードにする |
[冬季]3.6% [夏季]2.8% |
【2】省エネ性能の高い機器に変更する
電力消費量の大きい設備や機器を、省エネ性能の高いものへ切り替えることで、電気代を大きく削減することが可能です。
例えば、従来の蛍光灯や白熱電球をLED照明に交換する、省エネ性能に優れた空調に入れ替える、従来の換気システムから全熱交換器に入れ替えるなどの方法があります。
実際に、パナソニックの旧モデル(2012年モデル:PA-P80UM1SX)から現行モデル(PA-P80U7SGB)に入れ替えたケースでは、年間の消費電力量が43%削減され、年間の電気代も57%、金額にして27,100円の節約となりました。(※)
※1台あたりの試算です。
※電気代は(社)日本冷凍空調工業会の統一条件のもとに運転した場合の計算値であり、地域やご使用状況により変わることがあります。(統一条件:規格 JRA4002:2013R/地区 東京/建物用途 事務所/使用期間 【冷房】4月19日〜11月11日【暖房】12月3日〜3月15日/使用時間 8:00〜20:00 6日/週 /電気料金単価 東京電力 低圧電力契約))
※電気代に基本料金は含まれていません。
※旧製品の電気料金は、機器の経年劣化を考慮して算出しています。
【3】空調の最適化を図る
空調は建物全体の電力使用量の大きな割合を占めるため、その運用を最適化することで電気代の削減効果は大きくなります。
効果的な空調最適化の方法として、以下のような取り組みが挙げられます。
1.24時間営業など、常に人がいる場合はつけっぱなしにする
2.営業時間などに応じて運転スケジュールを設定する
(人が少ない時間帯が決まっている場合は、その時間だけ温度が自動で上がるよう設定をしておくなど)
3.定期的にフィルター清掃などのメンテナンスを行い、運転効率の低下を防ぐ
4.夏は運転前に換気を行い、室内のこもった熱気を逃すことで冷房効率を向上させる
5.サーキュレーターや扇風機を併用し、空気を効率よく循環させる
6.省エネを意識した運転を行う(風量を自動に設定する、設定温度を見直すなど)
7.自動制御システムを導入する
[1]から[6]はすぐに始められる取り組みですが、より効率的で効果的な省エネをめざすなら[7]の自動制御システムの導入がおすすめです。特に、空調を1台ずつ管理・調整することが現実的ではない大規模な施設では自動制御システムの導入は一般的です。また最近では、小中規模の施設でも電気代削減や環境問題への対応、人材不足による管理工数の削減のために、導入が進んでいます。
例えば「Panasonic HVAC CLOUD」なら、AIが施設情報・利用者の空調設定・気象情報・時刻設定を学習し、外気温度や時刻に応じて自動で設定温度を調整します。これにより、人による過剰な快適運用を減らし、実施検証では1年間で約20%の消費電力量削減を確認しました。(※)
■過剰な快適運用の例
Panasonic HVAC CLOUDならではの特長として、利用者が日常的に行っている空調設定をAIが学習し、快適性を損なうことなく、無理のない省エネを実現できる点が挙げられます。さらに、「店舗A・店舗B・店舗C」のような複数拠点の空調も、ご自身のPCから遠隔での一括管理が可能です。
効率的かつ効果的、そして快適な空調管理をめざすなら、「Panasonic HVAC CLOUD」の導入をぜひご検討ください。
(※)1年間、関東地方の2つの異なる物販店舗(約1,000㎡)の施設で検証。「設定温度自動リターン」機能(一定時間で指定した温度設定に戻る機能)との比較。
【4】太陽光発電システムや蓄電池を導入する
さらに蓄電池を併用すれば、発電した電力を貯めておき、夜間や天候不良時にも活用できるようになるため、さらなる削減効果を見込めます。
導入には一定の初期投資が必要ですが、補助金制度を活用することで導入負担を軽減できる場合もあります。長期的な視点で見れば、電気代削減効果と環境負荷軽減の両面でメリットがある方法といえるでしょう。
【5】デマンドコントロールを行う
高圧受電を利用する事業者は「デマンド値」が電気料金に影響するため、デマンドコントロールを行い、ピーク時の電力消費を抑えることが電気代削減の鍵となります。
デマンド値とは30分間の平均電力のことで、1日のなかでは計48回計測されます。高圧小口電力契約(50~500kW未満)の場合、1ヶ月間で最も大きいデマンド値が電気料金の「基本料金」に反映され、以降1年間はたとえ節電を行っても下がりません。
また、高圧大口契約(500~2,000kW)と特別高圧契約(2,000kW)の場合も、契約超過金の支払いや、契約変更が必要になることがあります。
このため、ピーク時の電力使用量をコントロールする「デマンドコントロール」が重要となります。
【6】電力会社を見直す
電力自由化により、大手電力会社以外にも、多様な電力会社からプランを選択できるようになりました。電力使用量や設備の稼働状況などに応じて、事業に合ったプランを選ぶことで、コストの削減が期待できます。
例えば、夜間の稼働が多い工場であれば、夜間の電力単価が安いプランを選択することで、電気代を抑えられるでしょう。業種や事業規模に応じて最適なプランを選択することが重要です。
【事例1】Panasonic HVAC CLOUDで29%の空調消費電力量を削減

大手外食チェーンA社様では、世界情勢を背景とした電気代の増加が経営課題となっていました。電力使用量の大きな割合を占める空調の省エネに着目しましたが、お客様や従業員の快適性を犠牲にするわけにはいかず、個々の「暑い」「寒い」というクレームへの対応も手間となっていました。
そこで、AI学習により温度を自動で調整する「Panasonic HVAC CLOUD」を導入したことで、空調の消費電力量を平均で約29%削減しました。さらに、空調の管理は本部側で一括して行えるため、店舗スタッフの運用負担も軽減されています。
結果的に、各店舗では空調に関する業務を意識することなく、省エネと快適性の両立を実現できました。お客様からの「暑い」「寒い」といった声も減り、クレーム対応の負担軽減にもつながっています。
【事例2】Panasonic HVAC CLOUDで53%の一次エネルギー消費量削減を達成
パナソニックは、2050年のカーボンニュートラル実現をめざし、自社拠点でのCO2排出量削減に積極的に取り組んでいます。
パナソニックグループの新社屋「パナソニック関東設備株式会社」では、省エネ性能に優れた空調設備やLED照明の設置、約20%(※)の空調消費電力量の削減効果をもたらす「Panasonic HVAC CLOUD」の導入などを行いました。複数のソリューションを組み合わせることで、再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量を従来比で53%削減することに成功しました。CO2排出量の削減とともに、消費電力の削減も両立しています。
また、「Panasonic HVAC CLOUD」による空調の消費電力量の推移や設定状況をデジタルサイネージに表示することで、社員一人ひとりの省エネ意識の向上も図っています。
(※)1年間、関東地方の2つの異なる物販店舗(約1,000㎡)の施設で検証。「設定温度自動リターン」機能(一定時間で指定した温度設定に戻る機能)との比較。
まとめ
企業の電気代削減は、昨今のエネルギー価格高騰により、経営上の重要課題となっています。
効果的な削減を実現するためには、組織全体での省エネ推進から始まり、省エネ機器への更新、空調最適化、太陽光発電導入、デマンドコントロール、電力会社の見直しなど、複数のアプローチを組み合わせることが重要です。
なかでも、空調は建物全体の電力使用量の大きな割合を占めるため、その最適化による効果は大きく、AI制御システムの導入により快適性と省エネの両立が可能です。企業事例でも、適切な施策により大幅な電力削減効果を実現できることが証明されています。
パナソニックでは、空調設備の運用・管理の最適化に貢献するサービスを提供しており、特に「Panasonic HVAC CLOUD」は、AIによる省エネコントロールで快適性と省エネの両立を実現します。
多店舗、多拠点の空調を遠隔で一括管理することにより、運用/管理の効率化につながり、さらに消費電力量の見える化でムダを可視化することで、企業の電気代削減に大きく貢献します。
ぜひお気軽にお問い合わせください。