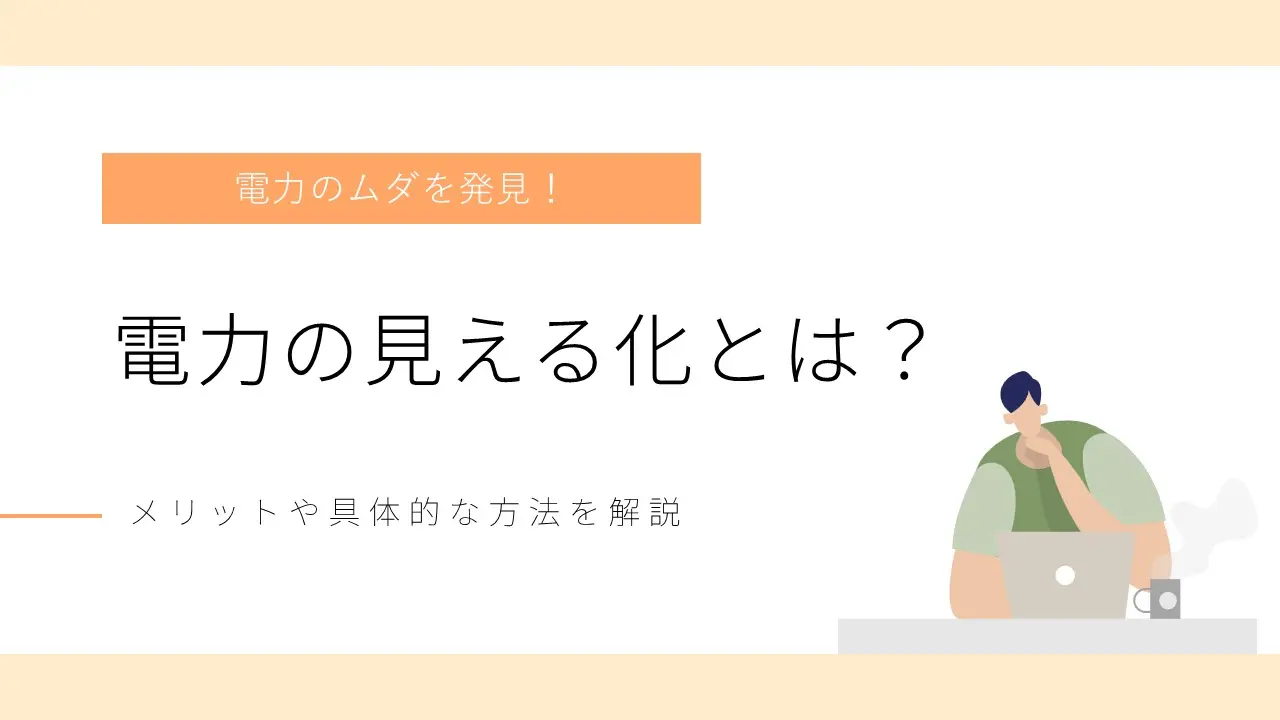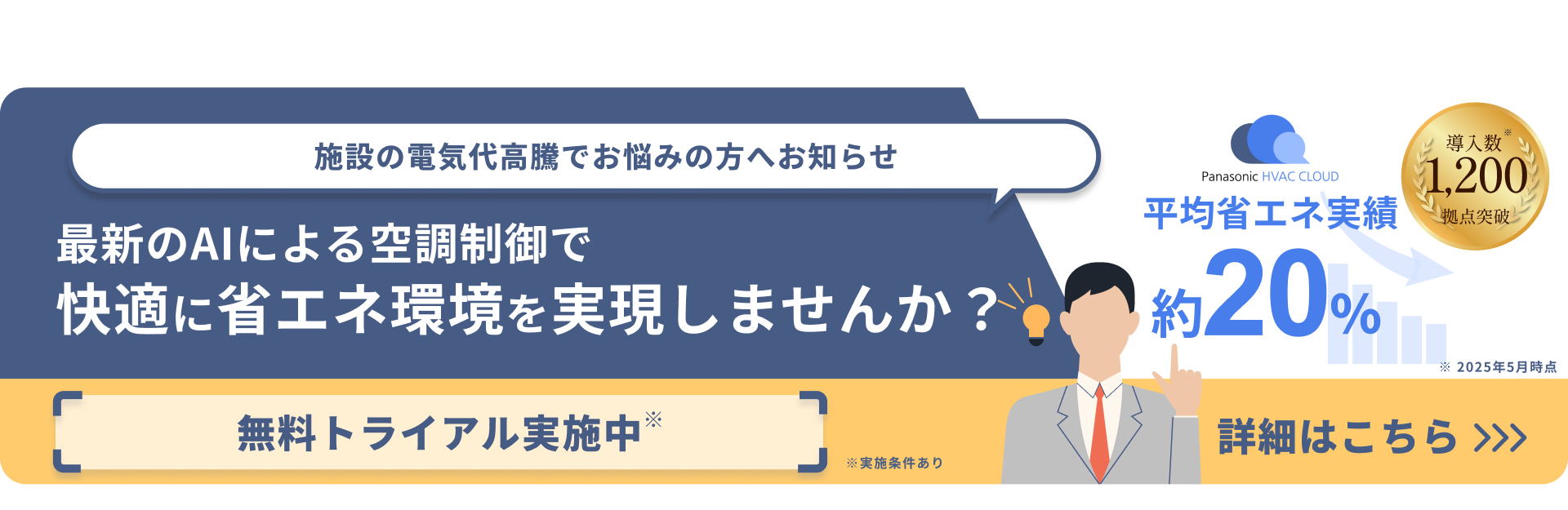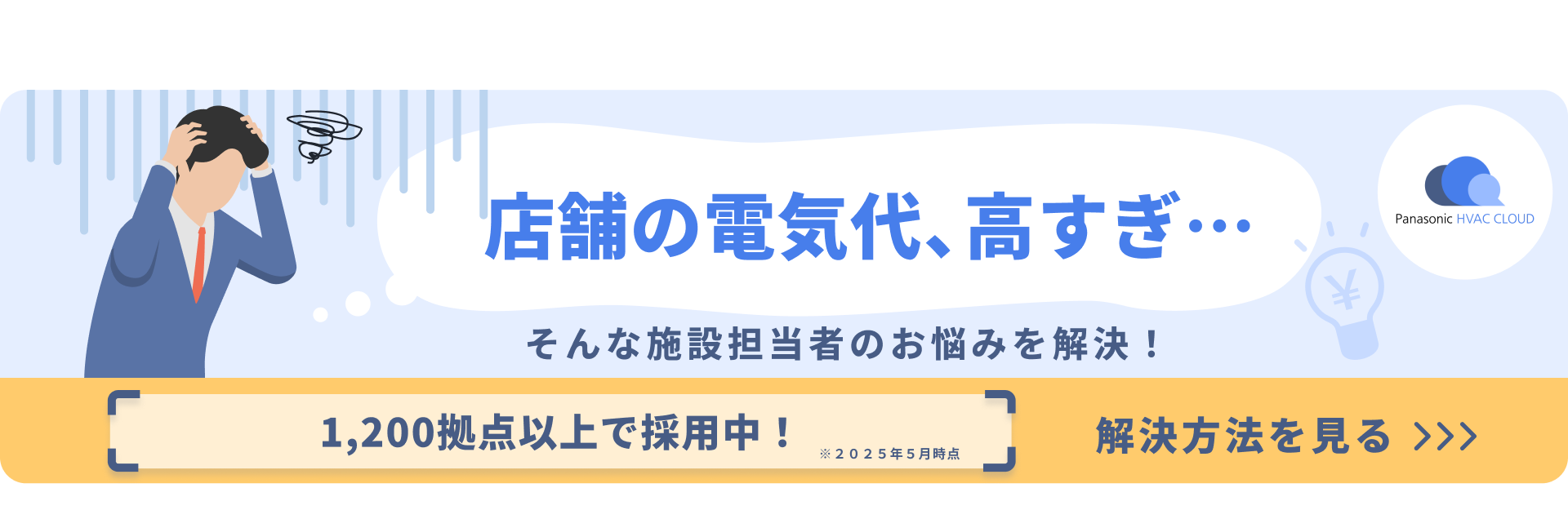企業の電気代削減や省エネ対策において、「電力の見える化」は重要な第一歩です。電力使用量や消費電力の状況を把握することで、効果的な省エネ対策を講じることが可能になります。
本記事では、電力の見える化の基本情報やメリット、方法、導入フローなどについて解説します。エネルギーコストの削減を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
電力の見える化とは?進んでいる背景
電力の見える化とは、複雑で見えにくい消費電力を数値やグラフなどで可視化することで、誰にでも理解できるようにする取り組みのことです。これにより、電力のムダを発見し、効果的な省エネ対策の立案や改善につながります。
見える化が進んだ背景には、「震災による電力供給の不安定化」と「環境への配慮」と「エネルギーコストの高騰」の3つの理由があります。
背景1.東日本大震災による電力バランスの崩れ
2011年に発生した東日本大震災では、原子力発電所や火力発電所などの設備が甚大な被害を受けました。また、安全確保の観点から、国内すべての原子力発電所が一時的に停止しました。こうした事態を受け、電力の供給力不足への対策が必要になり、計画停電や、電力使用量の制限が実施されました。
この一連の出来事は、個人の生活や企業活動に大きな支障をきたし、電力の安定供給がいかに重要であるかを再確認するきっかけになりました。以降、供給体制の強化だけでなく、需要側におけるエネルギー利用の見直しも求められています。
2013年には省エネ法が改正され、時間帯や季節による電力使用の偏りを抑える「電力需要の平準化」が推進されました。その実現に欠かせない取り組みとして、消費電力の状況を正確に把握する「電力の見える化」の導入が進められています。
背景2.地球温暖化防止に向けた取り組み
日本はエネルギー資源に乏しく、その多くを海外から輸入した化石燃料に依存しています。しかし、化石燃料は燃焼時に大量のCO2を排出するため、地球温暖化の要因とされています。
持続可能な社会の実現に向けて早急な温暖化対策が求められるなか、日本政府は2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の達成を目標に掲げました。
カーボンニュートラルの達成には、エネルギーの消費そのものを見直し、CO2の排出要因である電力使用量を削減していくことが必要です。その第一歩として、現状の消費電力を可視化し、課題を把握する「電力の見える化」が推進されています。
背景3:エネルギーコストの高騰
近年、日本ではエネルギーコストの上昇が企業の経営を直撃しています。背景には、ロシアのウクライナ侵略による化石燃料価格の高騰や再生可能エネルギー発電促進賦課金の値上げ、円安による影響などがあります。
実際に経済産業省の電気料金平均単価の推移を見てみると、2023年の産業用電力平均単価は2010年度と比べて約74%増加していることが分かります。
引用:3.経済性|資源エネルギー庁
そのため、自社の電力使用状況を正確に把握し、無駄を減らすことがエネルギーコスト対策として喫緊の課題となっています。
こうした背景から、「電力の見える化」の導入が企業にとって欠かせない取り組みとなっています。
電力を見える化するメリット
- データに基づいた省エネ対策が可能になる
- 快適性を損なうことなく消費エネルギーを削減できる
- 省エネへの関心を高められる
- 環境配慮の取り組みとしてアピールできる
各メリットについて詳しく解説します。
データに基づいた省エネ対策が可能になる
例えば、オフィスに誰もいない時間帯に空調が運転していることが見えれば、タイマー設定や温度設定の見直しといった対応を行うことでムダな電力の消費を防ぐことができます。特定の時間帯の電力使用量が多い場合には、使用機器のスケジューリングを見直すことでデマンド値の抑制が可能です。
こうした取り組みは、データによって「ムダ」を明確化できるからこそ実現できる対策です。
快適性を損なうことなく消費エネルギーを削減できる
電力を見える化することで、どこにムダなエネルギーが使われているかを正確に把握し、具体的な改善策を講じられるようになります。
空調の利用を厳しく制限するといったような我慢を強いる省エネではなく、見える化によって発見した「ムダ」に対してアプローチを行えるため、快適性を損なうことなくエネルギーを削減できます。
省エネへの関心を高められる
電力の見える化によって得られたデータを組織内で共有すれば、省エネに対する関心や意識を高めるきっかけとなります。
具体的な電力使用量やムダのある箇所を示すデータを提示することで、単に「省エネをしよう」と呼びかけるよりも、問題意識が強まるでしょう。
関係者への説明資料としても活用できるため、改善策の検討や実施がスムーズになり、組織全体での省エネ活動が効果的に進められます。
環境配慮の取り組みとしてアピールできる
電力の見える化は、社外に対する環境配慮の姿勢を示す取り組みとしても有効です。環境への意識の高さを取引先や顧客、地域社会に対して示すことができます。
持続可能な経営への取り組みをアピールすることで、企業価値の向上にもつながります。
電力を見える化する方法
電力の見える化には様々なアプローチがあります。なかでも主要な方法が以下の3つです。
- 請求書やWeb上の数値をデータ化する
- メーターの数値をデータ化する
- システムを導入する
予算や目的に応じて、適切な方法を選択しましょう。
請求書やWeb上の数値をデータ化する

電力料金の請求書や、電力会社がWeb上で提供している電力使用量などの数値を取得し、見える化する方法です。取得したデータをエクセルなどの表計算ソフトに取り込み、グラフ化することで、電力の使用状況を把握できます。設備やシステムの導入が不要なため手軽に始められます。
しかし、手動でのデータ処理が必要なため手間がかかり、入力ミスのリスクもあります。また、請求書に記載されているのは当月の全体の電力使用量であり、時間帯や設備ごとの詳細なデータは含まれていません。
この方法は、まず電力の見える化を体験してみたい場合や、簡易的な把握から始めたい場合に適しています。
メーターの数値をデータ化する
各階や設備ごとに設置されたメーター(電力計)の数値をデータ化する方法もあります。こちらも手入力が必要なため手間や入力ミスのリスクはありますが、始めやすい方法です。
また、メーターを確認する時間帯に応じたデータが取得できるため、請求書よりも詳細な電力の見える化が可能です。例えば、朝8時と翌朝8時の数値差から1日の電力使用量を把握でき、メーターを確認する間隔を短くすればさらに細かな消費状況の把握も可能になります。
引用:テナントビル等における 「エネルギー見える化設備」 を活用した
システムを導入する
電力の見える化を効率的かつ高度に行うには、専用のシステム導入が効果的です。導入コストは懸念されますが、データ収集や分析の手間を大幅に削減できるほか、時間帯や設備ごとの詳細なデータを取得できる点は大きなメリットです。より正確で迅速な省エネ対策が可能となります。
|
デマンド監視装置 |
電力使用量を監視し、あらかじめ設定した目標値を超えそうになると管理者へ警報を行うシステム (データの閲覧可否はシステムによる) |
|
デマンドコントロールシステム・デマンドコントローラー |
デマンド監視装置の機能に加え、目標値を超えそうになったときに設備を自動で制御するシステム (データの閲覧可否はシステムによる) |
|
エネルギーマネジメントシステム(EMS) |
過去やリアルタイムのエネルギーの使用状況を見える化し、手動または自動制御によって設備の運転を最適化するシステムのこと |
電力の見える化設備の導入フロー
電力の見える化には専用のシステム導入が効果的ですが、導入にあたっては段階的なフローを踏むことが重要です。
まずは、「電力の見える化を行う目的」と「電力の見える化を行う内容」を明確にしましょう。
■「目的」の例
[×]省エネを図りたい
[○]複数拠点のエネルギー管理を行い、省エネ対策を実施したい
■「内容」の例
- 見える化する場所や設備(ビル全体、階別、空調設備、照明設備など)
- 見える化する時間(年間、月間、毎日、毎時、瞬時値など)
これらを踏まえたうえで、必要な機能が備わったシステムを選定すれば、効果的な電力の見える化を実現できます。
空調の消費電力量を見える化するならPanasonic HVAC CLOUD
空調の消費電力量を見える化するシステムとして、パナソニックの「Panasonic HVAC CLOUD」をご紹介いたします。
空調の消費電力量は、建物全体の消費電力量の50%にも達する(※)ため、空調の消費電力量を見える化し、省エネ対策を講じることは、建物全体のエネルギー効率を高めるうえで極めて重要です。
(※参照)関東経済産業局「中小企業の支援担当者向け省エネ導入ガイドブック」
※用途により割合は異なります
※集会場の場合
「Panasonic HVAC CLOUD」は、物件の月ごと、日ごと、時間帯ごとでの空調消費電力量の推移をグラフで可視化できます。店舗A、店舗B、店舗Cといった複数拠点でも遠隔で確認できるため、全物件の空調消費電力を一括で可視化し管理業務の手間を減らします。
また、「Panasonic HVAC CLOUD」には、消費電力量の見える化だけでなく、以下のような機能もあります。
◾️設定温度の可視化
物件ごとに設定温度の推移をグラフで可視化できます。ムダを発見し、具体的な節電対策を講じることが可能です。
◾️空調運転の一括遠隔管理
どの空調機器がいつの時間帯に動いているか、どのくらいの温度設定で運転しているのかを複数拠点で一括して可視化できるため、スケジュール設定による切り忘れ防止や、適正温度の見直しを行えます。これにより、消費電力量の削減と管理工数の削減に貢献します。
◾️警報メール通知
空調機器に異常があった場合、エラーコードをメールで通知します。遠隔で異常を確認でき、夏季や冬季などに空調機を使おうとした際の「故障に気づかず使用できない」といった事態の予防が可能です。現地での確認の手間が省けるため工数の削減になるほか、修理や交換などの対応の手配がスムーズに行えます。
◾️AI省エネコントロール
AIによる運転制御で省エネと快適性を両立する業界初の機能(※1)を搭載しており、施設情報・利用者の空調設定・気象情報・時刻設定をAIが学習し、外気温度や時刻に応じて自動で設定温度を調整します。人による過剰な快適運用を減らすことで、実施検証では1年間で約20%の消費電力量削減効果を確認(※2)しており、快適性を損なわずに省エネを実現します。
(※1)2023年2月時点 空調業界当社調べ。
(※2)※1年間、関東地方の2つの異なる物販店舗(約1,000㎡)の施設で検証。「設定温度自動リターン」機能(一定時間で指定した温度設定に戻る機能)との比較。
まとめ
電力の見える化は、消費電力を可視化することで電力使用状況を把握し、効果的な省エネ対策を実現する重要な取り組みです。東日本大震災による電力供給不安や、地球温暖化対策の必要性から、その重要性はますます高まっています。中でも、建物全体の消費電力量の約50%を占める空調設備の見える化は特に効果的です。
電力を見える化する方法には、請求書の活用やシステム導入など、さまざまな選択肢があります。パナソニックの「Panasonic HVAC CLOUD」は、空調の消費電力量を見える化するだけでなく、AI機能による自動制御機能で快適性を保ちながら省エネを実現できます。
複数拠点の一括管理も可能で、管理工数の削減にも貢献します。空調の電力コスト削減と環境配慮を両立したい企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。