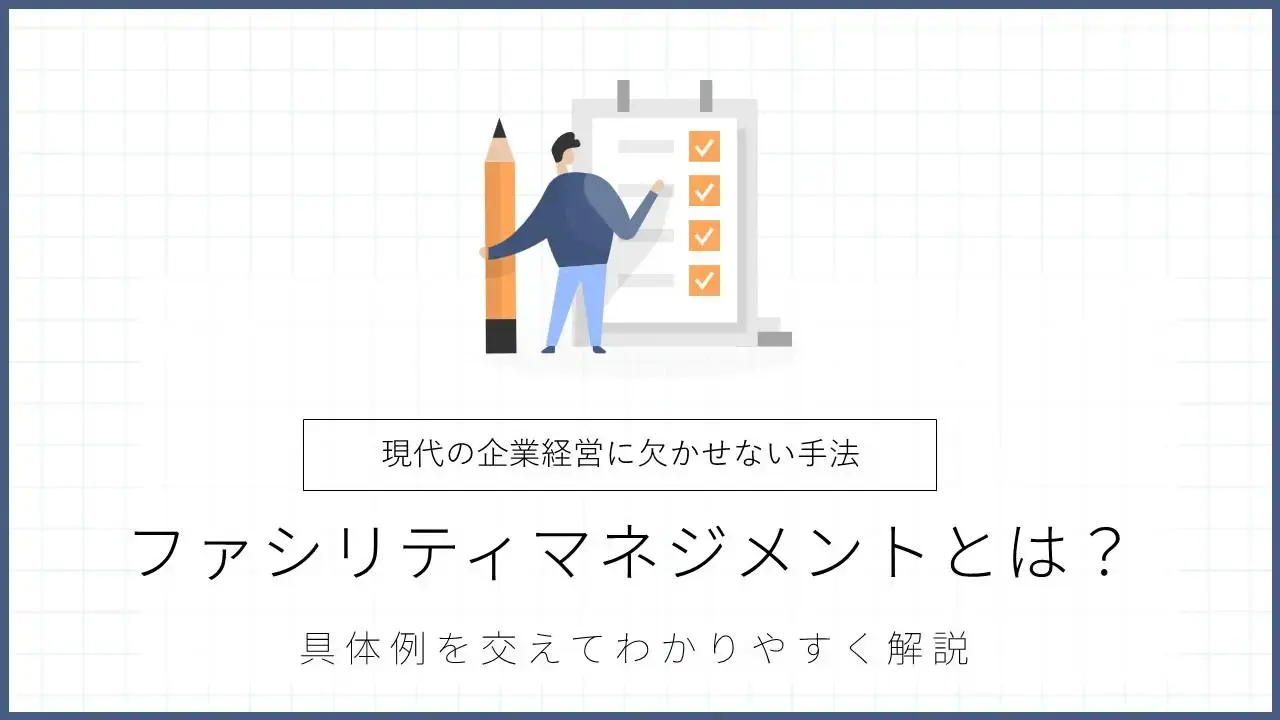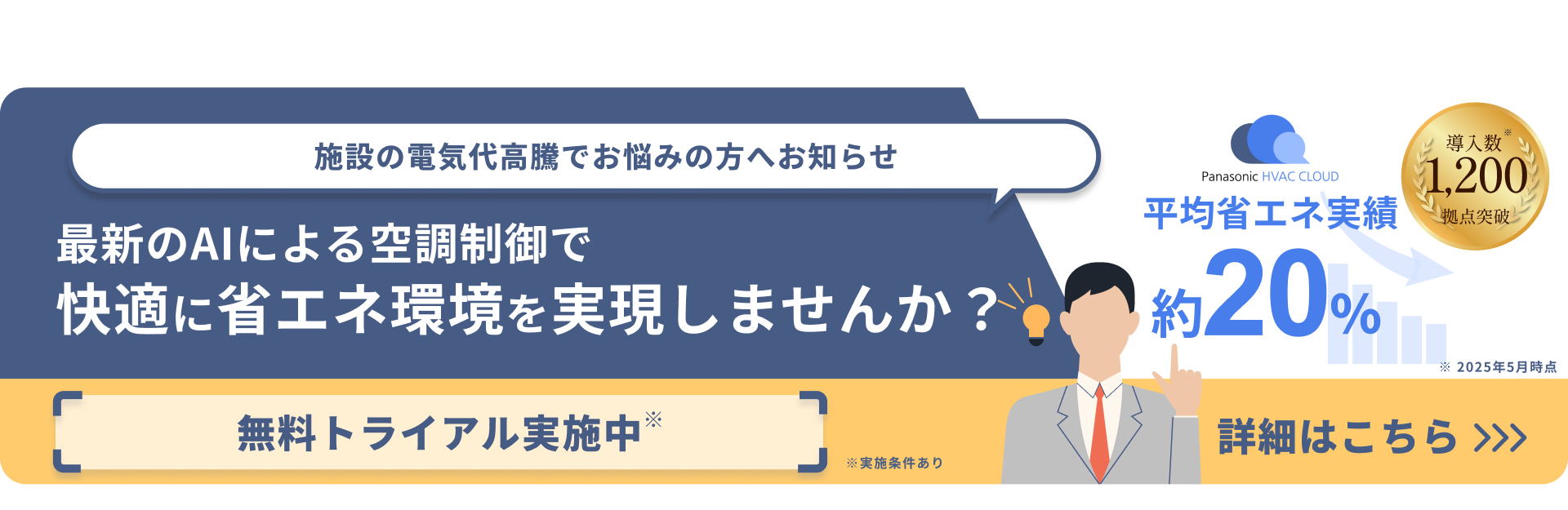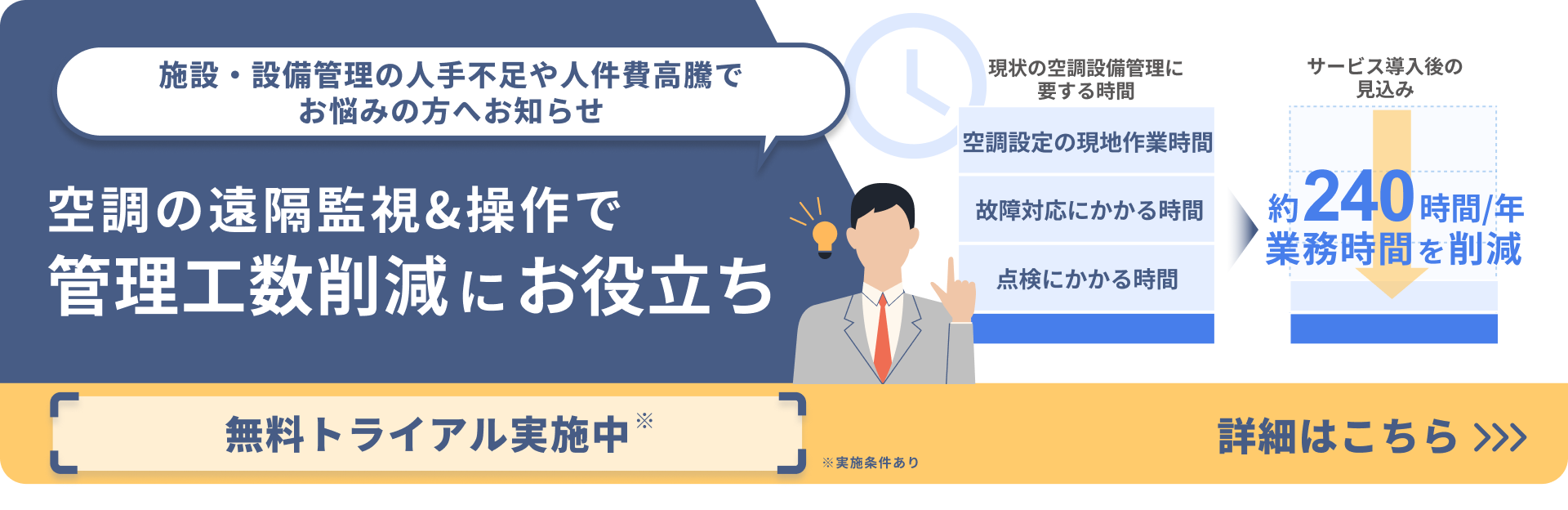ファシリティマネジメント(FM)は、企業の施設や環境を戦略的に活用し、コスト削減や生産性向上を実現する経営手法です。働き方の多様化や環境問題への対応が求められる現代において、その重要性は高まり続けています。
本記事では、ファシリティマネジメントの基本概念から具体的な実践例まで、わかりやすく解説します。
ファシリティマネジメント(FM)の意味
ファシリティマネジメントの本質を理解するためには、まずその定義と構成要素を明確にすることが重要です。ファシリティマネジメントについて、公益財団法人日本ファシリティマネジメント協会(JFMA)は以下のように定義しています。
企業・団体等が組織活動のために、施設とその環境を総合的に企画、管理、活用する経営活動
※引用:FMとはどのようなものか|JFMA 公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会
「ファシリティ」の意味や必要性について、より深く理解を深めていきましょう。
ファシリティマネジメントの「ファシリティ」とは?
ファシリティマネジメントにおける「ファシリティ」とは、土地や建物、その中にあるワークプレイス、設備、家具という物的資産に加え、それらによって形成される職場環境全体を指します。さらに、そこで働く人々などの施設利用者の快適性・生産性を支える物理的・心理的な環境も対象となるのです。
また、近年では建物や設備などのハード面だけではなく、インフラやリスク環境、ホスピタリティなどのソフト面もファシリティの一部とみなされるようになりました。
このように、ファシリティの概念は従来の「建物の管理」という枠組みを超えて、組織活動を支えるあらゆる環境要素を包含するものへと発展してきました。
つまり、ファシリティマネジメントとは、これらの「ファシリティ」を、コストを最小限に抑えつつ効果を最大限に引き出すよう「マネジメント」し、組織の様々な価値を生み出す経営活動です。
ファシリティマネジメントの必要性
企業経営においては、「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」という4つの経営資源をいかに効果的に活用するかが非常に重要とされています。しかし、「モノ」に該当するファシリティ、特に施設関係費は人件費に次ぐ固定費にも関わらず、ほかの経営資源と比べて十分に重視されてきませんでした。
この背景には、バブル期に定着していた「スクラップ&ビルド」という考え方が影響しています。バブル期は資金調達が容易だったため、建物を建てては取り壊すことが一般的であり、長期的な視点で施設を維持・活用する意識が根づきにくかったのです。
しかし、バブル崩壊後の経済低迷によって資金調達が困難になり、限られた資産をいかに有効に使うかという発想が求められるようになります。この流れの中で、ファシリティマネジメントの重要性も徐々に認識されるようになりました。
加えて、スクラップ&ビルドは大量の廃棄物を伴い、環境負荷の大きい手法であることから、地球温暖化といった社会課題への対応としても見直しが迫られています。
ファシリティマネジメントのレベル
公益財団法人日本ファシリティマネジメント協会では、ファシリティマネジメントを3つのレベル(経営・管理・日常業務)から、状況に応じて現実的に対応できる活動として定義しています。

※引用:FMとはどのようなものか|JFMA 公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会
施策を実行したあとは、評価を行い、その結果を次の改善に活かすというPDCAサイクルを回すことが重要です。
ファシリティマネジメントの具体例
ファシリティマネジメントを理解するには、実際の企業や組織でどのように活用されているのかを知ることが効果的です。
ここでは、代表的な取り組み事例を紹介しながら、ファシリティマネジメントがどのように組織の価値向上に貢献しているかを見ていきましょう。
ワークプレイスの見直し
社員が日々働くワークプレイスの環境を整えることは、ファシリティマネジメントの大きな役割の一つです。空間の使い方や家具の選定、レイアウトの工夫などを通じて、社員の集中力や生産性を高め、コミュニケーションの活性化にもつなげられます。
例えばデスク1つとっても、その配置や形状、大きさによって、周囲との関わり方や作業効率が大きく変わります。固定席制では個人の作業に集中しやすい一方で、部署間の交流は生まれにくくなります。一方、フリーアドレス制を導入すると、部署を超えたコミュニケーションが活発化し、新たなアイデアやイノベーションが生まれやすくなります。
実際の事例として、パナソニックグループのパナソニックコネクト株式会社では、フリーアドレス制を取り入れ、社長もオープンスペースで業務を行うスタイルに転換しました。この取り組みにより、組織全体がフラットな文化に変化し、意思決定のスピードや情報共有のしやすさが向上しています。
また、働き方が多様化している今、在宅勤務やハイブリッドワークによってスペースが余っているケースもあるかもしれません。そのような状況では、余剰スペースをリラックスできる休憩スペースに変えたり、集中作業ができる個室ブースを設けたりすることで、社員のモチベーション維持や生産性向上につなげることが可能です。
建物の有効活用
ファシリティマネジメントでは、稼働していない事業所や空室が目立つ社宅など、現在使われていない建物やスペースをいかに有効活用するかも重要な視点です。そのままにしておくと固定資産税や維持管理費だけがかかり、企業にとってはコストの負担となるばかりか、利益にはつながりません。
例えば、使用していない事業所やオフィスフロアに、グループ会社や関係会社を移転させることで、施設を有効に活かすとともにコスト削減にもつなげられます。また、空室となった社宅を地域企業に貸し出し、社員寮として活用してもらうことで、収益を得ながら地域とのつながりを深めることも可能です。
老朽化が進み維持費や修繕費がかさむ場合には、改修を行って再利用をめざすか、あるいは取り壊して土地を売却・有効活用する判断も求められます。この際、将来的な事業展開や地域の発展可能性、環境への影響なども考慮した総合的な判断が必要になります。
このように、使われていない建物や空間を見直し、資産としての価値を最大化することも、ファシリティマネジメントの大切な役割のひとつです。
建物の省エネ化
建物の省エネ化は、ファシリティマネジメントの「コストを最小限に抑えつつ効果を最大限に引き出す」という考え方において、非常に重要な取り組みのひとつです。
例えば、照明のLED化や、空調設備の高効率化、エネルギーの見える化、断熱性能の強化などにより、電力使用量を削減することでランニングコストを抑えられます。
また、省エネ施策は、温室効果ガスの排出抑制にもつながるため、環境への配慮という観点でも大きな意義があります。企業としては、社会的責任(CSR)を果たしていると評価されやすくなり、ブランドイメージや企業価値の向上にもつながるでしょう。
省エネ化は単なるコストカットではなく、経営の質を高めるための重要な活動といえます。
近年では、AIを活用してエネルギー消費を最適化する制御システムの導入が、新たな省エネ対策として広がりを見せています。建物の省エネ化を実現する方法の一例として、以下のようなシステムの導入が挙げられます。
◆建物の省エネ化に大きく貢献する「Panasonic HVAC CLOUD」
空調の消費電力量は、建物全体の消費電力量の50%にも達します(※1)。空調の消費電力量を見える化し、省エネ対策を行うことは、建物全体のエネルギー効率を高めるうえで非常に重要です。
「Panasonic HVAC CLOUD」は、物件の月ごと、日ごと、時間帯ごとでの空調消費電力量の推移をグラフで可視化できます。
また、AIによる運転制御で省エネと快適性を両立する業界初の機能(※2)を搭載。施設情報・利用者の空調設定・気象情報・時刻設定をAIが学習することで、外気温度や時刻に応じて自動で設定温度を調整します。
人による過剰な快適運用を減らすことで、実施検証では1年間で約20%の空調消費電力量削減効果を確認(※3)。快適性を損なわずに省エネを実現することが可能です。
(※1参照)関東経済産業局「中小企業の支援担当者向け省エネ導入ガイドブック」※用途により割合は異なります ※集会場の場合
(※2)2023年2月時点 空調業界当社調べ。
(※3)1年間、関東地方の2つの異なる物販店舗(約1,000㎡)の施設で検証。「設定温度自動リターン」機能(一定時間で指定した温度設定に戻る機能)との比較。
防災やセキュリティの強化
企業活動の継続性を確保し、施設利用者の安全を守るうえで、防災およびセキュリティ対策の強化は欠かせません。
災害発生時にも事業を継続できるよう、建物の耐震補強や非常用電源の整備、災害時の避難計画の策定などを通じて、リスクへの備えを万全にしておくことはBCP(事業継続計画)の一環として重要です。
また、盗難や不審者の侵入、サイバー攻撃による情報漏えいなどのリスクにも対応しなければなりません。情報漏えいは顧客や取引先の信頼を損なうだけでなく、訴訟リスクや多額の損害賠償につながる恐れもあるため、早期からの対策が重要です。
ホスピタリティの向上
ファシリティマネジメントの役割は設備管理だけにとどまりません。施設を利用する人々に快適で心地よい環境を提供する「ホスピタリティ」も重要な要素です。
従業員や来訪者がポジティブな体験を得られるような空間づくりは、組織の成長や競争力強化に直結する重要なファシリティマネジメントの一環です。
例えば、オフィス内に無料のドリンクコーナーを設けることで、従業員の満足度やモチベーション向上が期待できます。また、受付での丁寧な応対や快適な待合スペースの提供など、来訪者に対して行き届いたサービスを行うことで、企業全体の印象が向上し、信頼関係の構築が期待できます。
こうした取り組みはコストが懸念されるかもしれませんが、実際には従業員の生産性や定着率、顧客満足度の向上といった形で、長期的に見れば大きな価値を生み出す効果が期待できるのです。
ファシリティマネジメントを担うヒューマンリソースの課題解決
ファシリティマネジメントの持続可能な運用を実現するためには、その業務を担うヒューマンリソースの課題解決も不可欠です。
日本社会が直面する高齢化や人手不足の課題に対して、ファシリティマネジメントを担う人材育成制度の整備、DX化による効率化などの対応が必要になってきます。
DXについては例えば、前述の「Panasonic HVAC CLOUD」を導入すれば、店舗A・店舗B・店舗Cといった複数拠点の空調設備の稼働状況をクラウド経由で遠隔管理することが可能になります。
物件全体の月別、日別、時間帯別の空調消費電力や温度設定を一元的に把握できるため、具体的な節電対策の立案や切り忘れ防止、適正温度設定の見直しを迅速かつ効率的に行えます。
空調設備に異常があった場合はエラーコードをメールで通知するため、現地での確認の手間が省けて工数の削減になるのとあわせて、修理や交換対応などの初動手配がスムーズに行えます。夏季・冬季に空調機が必要になった際の「故障に気づけておらず使用できない」といった事態の予防も可能です。
限られた人員でも多拠点の空調設備を効率的に管理でき、人手不足の解消と快適な環境づくりを両立させることができるでしょう。
ファシリティマネジメントと混同されやすい言葉との違い
ファシリティマネジメントは、類似する用語と混同されることがあります。正確な理解のために、よく混同される「施設管理」や「プロパティマネジメント」との違いを明確にしておきましょう。
「施設管理」との違い
「施設管理」は、建物や設備の維持・保全を目的とした業務を指し、点検・修繕・清掃・警備などが中心となります。 これに対しファシリティマネジメントは、維持・保全だけを意味するのではなく、施設とその環境の「より良いあり方」を追求するものです。
例えば、定期的な点検によって故障を防ぎ、破損箇所を修理するというのが従来の施設管理です。一方、ファシリティマネジメントは維持・保全を含みつつも、そこから一歩踏み込んで施設やその環境の向上をめざします。
具体的には、点検作業を効率化してコスト削減を図る、業務効率を高めるためにオフィスのレイアウトを見直す、照明をLEDに切り替えてエネルギー消費を抑えるなど、事業の収益性や持続可能性まで視野に入れた取り組みが挙げられます。
「プロパティマネジメント」との違い
プロパティマネジメントとは、不動産オーナーに代わって物件の運営や管理を行う業務を指します。具体的には、テナントの募集や契約の締結、家賃の徴収、苦情対応、修繕対応などであり、不動産の管理や資産価値を維持・向上させることが目的です。
一方、ファシリティマネジメントは、企業や組織の立場から、自らが保有・使用する施設を最適な状態で維持・活用するという発想です。
両者は意味や目的に違いがありますが、使われていない建物やスペースの有効活用や、物件の効率的運用といった側面では、プロパティマネジメントもファシリティマネジメントの一部として捉えられるでしょう。
ファシリティマネジメントを導入する目的・メリット
ファシリティマネジメントの導入により、企業は多様なメリットを得ることができます。コスト削減から従業員満足度の向上、環境への貢献まで、その効果は多岐にわたります。
ここでは、主要な目的とメリットについて詳しく解説します。
コスト削減
ファシリティマネジメントを導入する目的・メリットのひとつが、施設に関するコストの削減です。使われていないスペースや、適切でない使われ方をしている施設が明らかになることで無駄な支出を抑えることが可能です。
例えば、使用されていない事業所がある場合、そのまま維持するのではなく、別用途への転用や売却を検討することで、維持管理にかかっていた人件費や光熱費、修繕費などの固定費を大幅に削減できます。
設備や建物の省エネ化を進めれば、長期的なエネルギーコストの削減も可能です。
施設利用者にとっての快適・魅力的な施設の提供
ファシリティマネジメントは、経営視点から施設やその環境を最適化する取り組みであり、施設利用者にとって快適で魅力的な空間づくりも重要な目的のひとつです。特に、そこで働く人々にとっての快適性・利便性・安全性を高めることは、企業全体の競争力にも直結します。
例えば、空調が適切に管理されているオフィスと、寒暖の差が激しいオフィスでは、社員の集中力や作業効率に差が生じます。無料のドリンクコーナーや、仕事の合間にひと息つけるリラックススペースの設置など、細やかな配慮が働きやすい環境を生み出すこともあるでしょう。
より良い環境が整っていれば従業員のモチベーションが高まり、業務効率や組織へのエンゲージメント(愛着や貢献意欲)の向上が期待できます。
その結果、人材の定着率向上や生産性向上による利益アップといった成果につながるでしょう。
環境問題への貢献
現代社会において、企業は単に利益を追求するだけでなく、組織活動が社会や環境へ与える影響を考慮する「企業の社会的責任(CSR)」が強く求められています。とくに世界的にカーボンニュートラル実現をめざす現代において、環境問題への取り組みは企業の責務として非常に重要なテーマとなっています。
ファシリティマネジメントは、こうした課題に対して有効なアプローチの一つです。
例えば、省エネ性能の高い機器へと更新することで電力使用量を抑えられます。日本が排出する温室効果ガスのうち約9割がエネルギー由来のCO2が占めている(※)ため、電力使用量を減らすことが直接的に環境負荷の軽減につながるのです。
ファシリティマネジメントを通じた環境問題への取り組みは、ESG投資の観点からも評価され、企業価値の向上にもつながります。
※出典元:日本が抱えているエネルギー問題|経済産業省 資源エネルギー庁
まとめ
ファシリティマネジメントは、単なる施設の維持管理ではなく、コスト削減、従業員の働きやすさ向上、環境問題への対応など、多面的な価値創造を実現する戦略的なアプローチです。
企業・団体等が組織活動のために施設とその環境を総合的に企画、管理、活用する経営活動として、現代の企業経営に欠かせない要素となっています。
ワークプレイスの見直しや建物の有効活用、省エネ化の推進、防災・セキュリティの強化、ホスピタリティの向上など、具体的な取り組みを通じて組織の競争力強化に貢献します。特に働き方の多様化や人手不足、環境問題への対応が求められる現代において、DXを活用した効率的なファシリティマネジメントの重要性はさらに高まっています。
空調設備のファシリティマネジメントにおいては、「Panasonic HVAC CLOUD」のような先進的なソリューションが大きな効果を発揮します。AIによる快適性と省エネを両立した空調の設定温度自動制御と、クラウドシステムならではの遠隔管理により、約20%の空調消費電力量削減(※)を実現。人手不足の解消と環境負荷の軽減を同時に達成できます。
これからのファシリティマネジメントには、このような技術を活用したスマートな管理が不可欠といえるでしょう。
(※)1年間、関東地方の2つの異なる物販店舗(約1,000㎡)の施設で検証。「設定温度自動リターン」機能(一定時間で指定した温度設定に戻る機能)との比較。