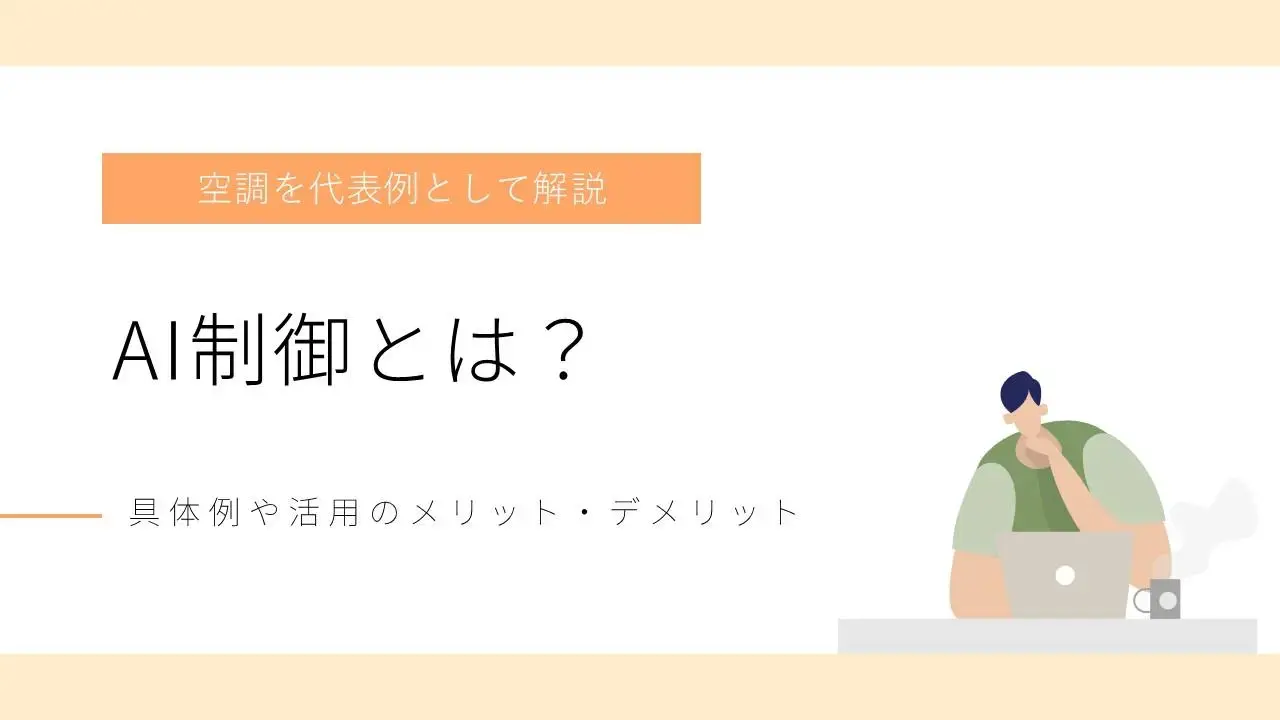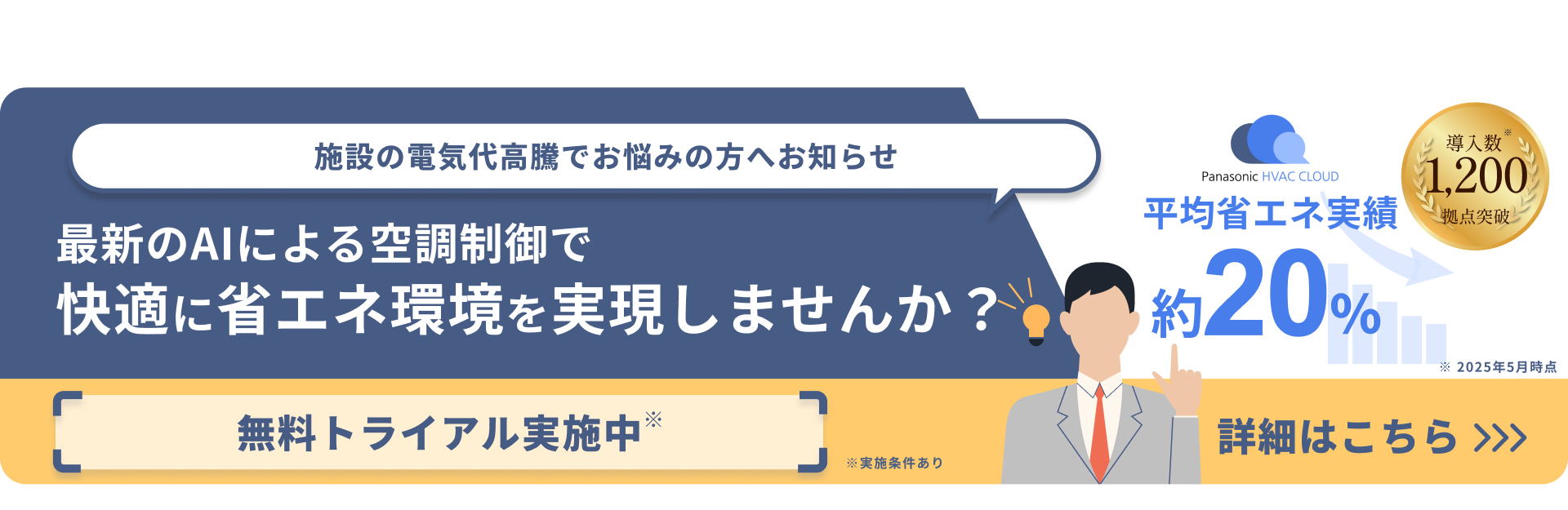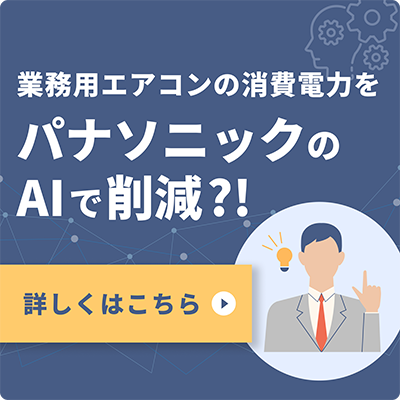近年、製造業から建設業、小売業に至るまで、あらゆる分野でAI技術の開発・導入が急速に進んでいます。特に設備管理の分野において、AI制御は従来の手動制御では実現できない高度な自動化と効率化を可能にしています。
本記事では、AI制御の基本的な仕組みから具体的な活用例、導入時のメリットまで、企業の管理者が知っておくべき情報を詳しく解説します。
AI制御とは
そもそもAIとは、「Artificial Intelligence(アーティフィシャル インテリジェンス)」の略称です。日本語では「人工知能」を意味し、コンピューターに人間のような知能を持たせる技術を指します。
AI制御は、このAIのなかでも、機械やシステム、設備の運転管理に特化したものです。
■AI制御の具体例
- 空調・温度管理:AIが気象情報や時刻などをもとに室内温度を自動調整
- 生産ライン:データをもとにAIが故障のリスクを予見し、機械を自動停止
- 自動運転車:AIが白線や障害物といった周囲環境を認識しながら、自動で運転
AI制御の仕組みと種類
AI制御は、与えられたデータのなかから規則性を見つけ出し、将来の状態を予測したり最適な操作を導き出したりする、「機械学習」という技術によって成り立っています。
この機械学習は、大きく4つの手法に分けられ、それぞれ異なる場面で活用されています。
|
教師あり学習 |
<詳細> あらかじめ「正常/異常」や「良品/不良品」といった正解付きデータを与え、そこからパターンやルールを導き出す手法 <具体例> 機械の「正常な動作」と「異常な動作」の情報を事前に与え、異常の兆候や発生を検知できるようにする |
|
教師なし学習 |
<詳細> 正解データが与えられていない状態で、大量のデータをもとにパターンやルールを見つけ出す手法 <具体例> 機械の「正常なパターン」を学習し、そのパターンから外れた挙動を見つけ出すことで、異常の兆候や発生を検知する |
|
強化学習 |
<詳細> 試行錯誤を繰り返し、最適な行動を学習する手法 <具体例> 人が普段行っている空調の温度調整を学習し、気象情報や時刻などの条件をもとに、AIが自動で最適な温度設定を実施する |
|
深層学習 |
<詳細> 大量のデータを与えただけで、人の手を介さずとも自動で特徴を学習する手法 <具体例> 自動運転においては、標識や走行速度、走行レーン、周囲環境といった情報をカメラやセンサーで認識し、自動車をどのように制御すべきか判断する |
「フィードバック制御」との違い
フィードバック制御は、制御対象の「目標値」と「実際の出力値」を比較し、その偏差を無くすよう自動制御することを指します。
例えば、室内温度を25℃に保つよう空調を制御した場合、目標値は25℃であり、実際の室内温度が30℃であれば出力値は30℃となります。この5℃の差を埋めるために、設定温度や風量を自動調整して目標値の25℃にするのがフィードバック制御です。
つまり、フィードバック制御は「偏差を前提に制御する方式」であり、AIのように学習や分析を行い、状況に応じて最適な判断を自律的に行う能力は持ちません。
一方、AI制御は過去のデータから学習し、環境条件を予測して事前に最適な制御を実現するため、より高度で効率的な運転が可能になります。
AI制御を活用するメリット
何を対象にAI制御するのかによってメリットは異なります。ここでは、空調設備にAI制御を取り入れた場合を例としてメリットをご紹介します。
- エネルギー効率の向上
- 快適性の向上
- 運用管理の効率化
- エネルギーの安定確保と地球環境への貢献
ひとつずつ見ていきましょう。
電気代の削減
AI制御では、過去の運転データや外気温などを学習し、必要最小限の冷暖房出力で運転を行います。これにより、必要以上にエネルギーを消費することなく、電気代を節約できます。
とくに空調は、建物全体のエネルギー消費に占める割合が最大で50%(※)と大きく、省エネによる節約効果は非常に大きいといえるでしょう。

※用途により割合は異なります
快適性の向上
従来の空調は人の手によって設定が行われていましたが、その判断は個々の主観に左右されるため、ほかの人にとっては暑すぎたり寒すぎたりすることが少なくありませんでした。
AIによる自動制御であれば、日々の運転を学習して制御を行うため、利用者全員が心地よく過ごせる空間を保ちやすくなるでしょう。
運用管理の効率化
従来の空調制御は、担当者が温度や湿度、人の動き、天候の変化などを総合的に判断しながら手動で調整を行う必要がありました。そのため、管理には時間も労力もかかり、担当者の経験や勘に依存する面も少なくありませんでした。
AI制御を導入すれば、センサーやデータから得られる情報を自動的に分析し、空調を最適な状態に保つことが可能です。結果として人件費や業務負担の軽減につながり、担当者はより重要な業務に集中できるようになります。
エネルギーの安定確保と地球環境への貢献
AI制御によって空調運転を最適化すれば、無駄なエネルギーを使うことがなくなります。
電気をつくるには石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料が必要ですが、世界中で電気を消費しているため、これらの資源はいずれ枯渇するといわれています。特に、日本はエネルギー自給率が低く、海外から輸入する化石燃料に頼っており、国際情勢などによって安定的な確保が難しくなるリスクもあります。
また、化石燃料の燃焼時に排出するCO2は温室効果ガスの一種であり、地球温暖化の原因のひとつです。
AI制御による省エネルギーは、こうした限りある資源を大切に使い、CO2排出量を抑えることで地球温暖化対策にも貢献します。社会問題への対応は、企業としての社会的責任を果たす手段にもなり、持続可能な経営に寄与するでしょう。
AIによる運転制御で空調の省エネと快適性を両立する「Panasonic HVAC CLOUD」
ここでは、AI制御を活用して空調の省エネと快適性を両立する「Panasonic HVAC CLOUD」をご紹介します。
本サービスは、AIによる運転制御で省エネと快適性を両立する業界初の機能(※1)を持つ空調のマネジメントサービスであり、AIが以下のような流れで学習し、外気温や時刻に合わせて温度を自動制御します。

このAI制御により人による過剰な快適運用を削減することが可能です。実地検証では、空調の消費電力を約20%削減することが確認されました(※2)。
設置もWLANアダプターとLTEルータだけの省施工なシステムなので、新築・後付けのどちらも対応可能で、安価かつ短時間で完了します。約400㎡の店舗に導入する場合のシミュレーションでは、導入2年目から導入費用対効果が黒字化される見込みです。

AI制御以外にも、以下のような機能が利用できます。
- 月次・年次のAI省エネ効果を自動レポート発行
- 設定温度を変更しても、一定時間後に決められた設定温度に戻す設定温度自動リターン(※)
- 1週間のスケジュール設定
- 消費電力や設定温度の可視化
- 空調機から発報された警報コード・名称をお客様メールへ通知、一覧表示
- お客様が管理している本サービス導入物件の一覧表示
※AI省エネコントロール機能ご利用時には、設定温度自動リターンをご利用いただけません
複数棟・多店舗の空調を一括管理することも可能で、店舗A・店舗B・店舗Cといった複数拠点にある建物の空調を遠隔で管理できます。わざわざ現地に出向く必要がないので、管理工数を大幅に削減できるでしょう。
パナソニックでは、お客様が抱える不安に対し、導入検討の段階から徹底したサポートを行っています。まずはお気軽にご相談ください。お客様の既存の設備状況を確認し、導入の費用対効果の試算も承っています。
(※1)2023年2月時点 空調業界当社調べ
(※2)1年間、関東地方の2つの異なる物販店舗(約1,000㎡)の施設で検証。「設定温度自動リターン」機能(一定時間で指定した温度設定に戻る機能)との比較。
まとめ
AI制御は、人工知能を活用して機械やシステムの運転管理を自動化する革新的な技術です。
従来のフィードバック制御とは異なり、過去のデータから学習して最適な判断を自律的に行う能力を持ち、特に空調設備への導入ではエネルギー効率の向上、快適性の向上、運用管理の効率化、環境への貢献といった多面的なメリットが期待できます。
導入時にはコストがかかるものの、長期的な削減効果を考慮すれば十分な費用対効果が見込めるでしょう。
「Panasonic HVAC CLOUD」は、AI制御により省エネと快適性の両立を実現し、複数拠点の一括管理も可能な先進的なソリューションとして、企業のコスト削減や設備管理効率化に大きく貢献します。