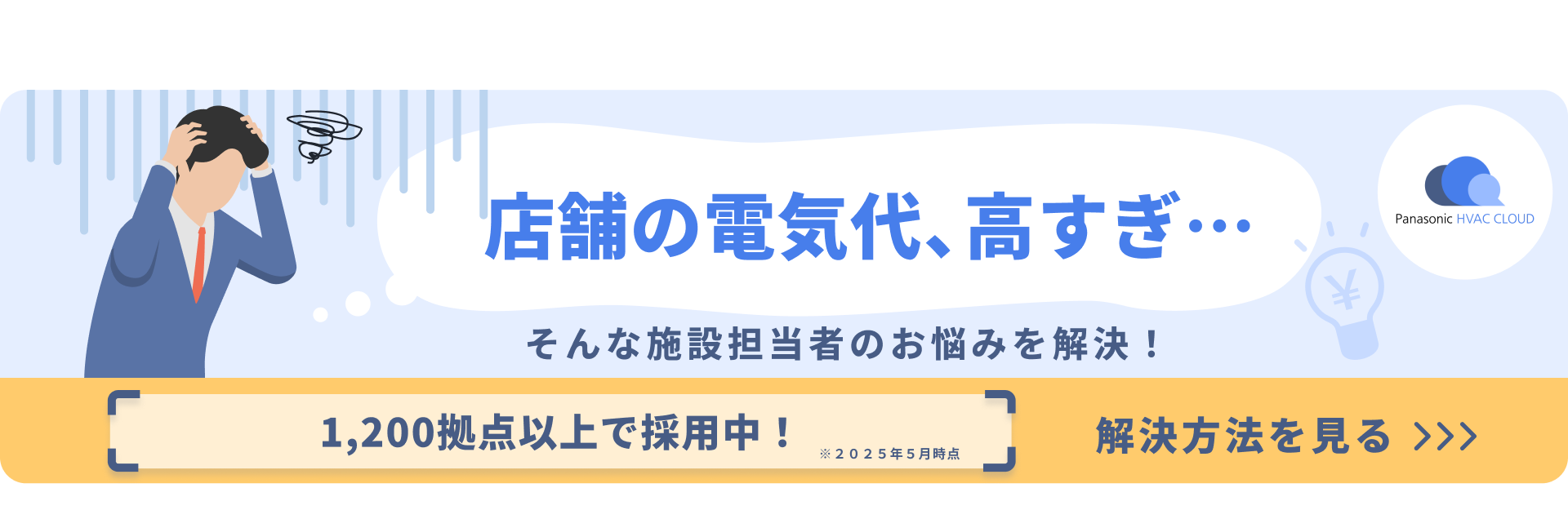電気代の高騰や物価上昇を受け、店舗の運営コスト削減は経営者にとって急務です。コスト削減を検討するうえでは、省エネによる電気代の削減も重要な要素といえるでしょう。
本記事では、店舗種別の電力消費実態や、具体的な対策、成功のコツまで、詳しく解説します。
実態から見る効果的な店舗の省エネ
省エネ対策を効率的に進めるためには、まず店舗の電力消費実態を正確に把握することが重要です。
業種や店舗規模によって電力の使用パターンは大きく異なります。消費電力の多い設備や時間帯を特定することで、より効果的な対策を立案できるでしょう。
以下は、資源エネルギー庁の資料(※)をもとにした、店舗の種類ごとの消費電力の傾向です。
※出典元:
夏季の省エネメニュー 事業者の皆様(本州・四国・九州版)
冬季の省エネメニュー 事業者の皆様(本州・四国・九州版)
卸・小売店
.webp?width=920&height=518&name=No.114_%E5%BA%97%E8%88%97%20%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D1_re20251009%20(2).webp)
卸・小売店は、一般的な営業時間前後にあたる9時から21時頃に高い消費電力が続く傾向にあります。
消費電力の内訳を見ると、夏季・冬季ともに空調と照明が全体の約半分を占めていますが、季節によってその割合は変動します。
夏季は冷房の使用で冬季よりも空調の消費電力の割合が大きく、冬季は日照時間が短くなる影響で照明の比率が高まるのです。
続くショーケースと冷凍・冷蔵はそれぞれ約7%と、照明や空調と比べれば割合は低いものの、全体としては中間に位置する消費電力であり、省エネ対策を講じたい分野にあたります。
■卸・小売店の省エネの方向性まとめ
- 夏季・冬季ともに消費電力の割合が高い「空調」と「照明」の省エネ対策を行うことで、効果を感じやすい
- 季節に応じて消費電力の割合は変わるので、「夏季は冷房」を、「冬季は照明」の省エネ対策により一層着目してみる
- 空調と照明に続いて消費電力の割合の多い「ショーケース」と「冷凍・冷蔵」の省エネ対策も組み合わせることで、効果をさらに高められる
食品スーパー
.webp?width=920&height=518&name=No.114_%E5%BA%97%E8%88%97%20%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D2_re20251009%20(2).webp)
食品スーパーでは、夏季は9時~17時、冬季は8時~20時頃にかけて、多くの電力を消費する傾向にあります。
夏季と冬季で多少の差はあるものの、いずれも開店・閉店準備や、営業時間内の稼働が大きな割合を占めます。
内訳としては、食品を扱う特性上、ショーケースの消費電力が最も多く、次いで空調、照明、冷凍・冷蔵が続きます。
また、夏季には食品の品質を保つために冷房の稼働が増え、空調の消費電力は冬季の2倍以上になることも特徴です。
■食品スーパーの省エネの方向性まとめ
- 最も消費電力が大きい「ショーケース」、続いて消費電力の大きい「空調」「冷蔵・冷凍」は省エネ対策の効果を実感しやすいが、食品を扱う関係上、無理のない範囲で取り組むことが大切
- 設置数が多く消費電力が大きくなりがちな照明についても、省エネ対策を検討する
飲食店
.webp?width=1200&height=676&name=No.114_%E5%BA%97%E8%88%97%20%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D3%20(1).webp)
飲食店は、夏季は10~20時頃に、冬季は16時~21時頃に高い消費電力が続く傾向があります。とくに、お昼時と夕食時の客足が集中する時間帯に消費が増加しやすいのが特徴です。
内訳を見ると、店内での快適性を重視するため夏季・冬季とも空調の割合が最も大きく、次いで照明の比率が高くなります。
また、夏季は調理による発熱も加わる影響で冷房負荷が増大するため、空調が全体の消費電力の約半分を占めます。食材管理や調理を伴うため、冷凍・冷蔵設備と調理機器の消費も多い傾向にあります。
■飲食店の省エネの方向性まとめ
- 夏季・冬季ともに最も消費電力の多い「空調」の省エネ対策が効果的だが、顧客の快適性に直結する点を考慮する必要がある
- 次いで消費電力の多い「照明」の省エネ対策による効果も期待しやすいが、集客や料理の見え方に影響しない工夫が求められる
- 「冷凍・冷蔵」は食品の品質を最優先に、「調理機器」においても味や提供スピードなどに影響のない範囲で省エネ対策を考える
具体的な店舗の省エネ対策
店舗ごとに消費電力の実態は異なりますが、「卸・小売店」「食品スーパー」「飲食店」いずれも共通して大きな消費電力を占めるのは、以下の4つです。
- 空調
- 照明
- 冷凍・冷蔵
- ショーケース
これらの設備は店舗運営に欠かせないものですが、省エネ対策を重点的に行うことで、電力使用量の大幅な削減が期待できます。
空調

空調の主な省エネ対策は次のとおりです。
- 定期的にフィルターを掃除する
- 使い方を見直す
- 省エネモデルに買い替える
- 自動制御を導入する
定期的にフィルターを掃除する
空調のフィルターが目詰まりすると、運転効率が低下して余分な電力を消費してしまいます。取扱説明書を参考にして定期的な掃除を行いましょう。
使い方を見直す
空調の使い方を見直すことで、電力消費を抑えることができます。
例えば、事務室など長時間不在になる部屋がある場合には、つけっぱなしにするのではなく使うときだけ空調をつけるようにしましょう。
反対に、人が頻繁に出入りする店舗や部屋では、こまめにオンオフするよりもつけっぱなしのほうが節電になる可能性があります。これは、室内温度が設定温度に達するまでが最も多くの電力を消費するためです。
そのほか、温度設定の見直しや、風量の自動運転、サーキュレーターや扇風機の併用など、空調の使い方だけでもさまざまな省エネ対策があります。
省エネモデルに買い替える
現在お使いのモデルが古い場合は、省エネ性能に優れた最新モデルに買い替えるのもおすすめです。
パナソニックの旧製品「PA-P80UM1SX(2012年モデル)」と、現行品「PA-P80U7SGB」を比較すると、年間消費電力量を43%も削減可能です。
年間で1台あたり27,100円もの電気代が削減でき、その節約効果は57%にもなります(※)。

※1台あたりの試算です。
※電気代は(社)日本冷凍空調工業会の統一条件に基づいて運転した場合の計算値です。地域やご使用状況によっては変動することがあります。(統一条件:規格 JRA4002:2013R/地区 東京/建物用途 事務所/使用期間 【冷房】4月19日〜11月11日【暖房】12月3日〜3月15日/使用時間 8:00〜20:00 6日/週 /電気料金単価 東京電力 低圧電力契約))
※電気代に基本料金は含まれていません。
※旧製品の電気料金は、機器の経年劣化により性能が低下することを考慮して算出しています。
ただし、空調の節電効果は省エネ性能だけではありません。無駄な電力消費を防ぐために、部屋の広さや用途などに応じた能力(馬力)を選ぶことも大切です。
自動制御を導入する
エアコンの運転や設定を適切な状態に保つことは非常に効果的な節電対策ですが、これらを手動で管理するとなると手間がかかります。とくに、店舗を複数展開している場合や、規模の大きい店舗では、すべてを手動で管理するのは現実的ではありません。そこでおすすめなのが、空調の自動制御です。
例えば「Panasonic HVAC CLOUD」なら、AIが施設情報や利用者の空調設定、気象データ、時刻設定を学習し、外気温や時間帯に合わせて温度設定を自動で調整します。これにより、人による過剰な快適運用を抑制し、実地検証において1年間で約20%もの空調消費電力量の削減効果があることを確認しました。(※)
また、AIが利用者の日々の空調設定を学習するため、快適さを保ちながら無理なく省エネを実現できます。
さらに、複数拠点(例:店舗A・店舗B・店舗C)の空調も、お手持ちのPCから遠隔で一括管理することが可能です。空調を効率的かつ効果的、そして快適な管理を実現したいなら、「Panasonic HVAC CLOUD」の導入をぜひご検討ください。
※関東地方にある約1,000㎡の2つの異なる物販店舗で1年間検証。一定時間で設定温度を元に戻す「設定温度自動リターン機能」との比較。
照明

照明の主な省エネ対策は次の通りです。
- 必要のない照明の消灯・照度が求められない場所の照度の引き下げや間引き
- 省エネ性に優れた照明への入れ替え
必要のない照明の消灯・照度が求められない場所の照度の引き下げや間引き
営業時間外や、使用していないエリアの照明はこまめに消灯しましょう。また、倉庫・バックヤード・スタッフ通路など、明るさをそれほど必要としない場所は、照度を引き下げたり、照明器具を減らしたりすることで、省エネが可能です。 従業員に対しても、照明のオン・オフの基準を明確に示しましょう。
また、天候にもよりますが、昼間は自然光を積極的に採用すると、照明の稼働時間をさらに減らせます。
省エネ性に優れた照明への入れ替え
照明そのものを、以下のような省エネ型に更新することも有効な対策です。
|
照明器具 |
特徴 |
|
LED照明 |
LED照明は従来の蛍光灯と比べて消費電力が少なく、寿命も長い |
|
人感センサー付き照明 |
人の出入りが少ない場所で自動的に消灯でき、無駄な点灯を防げる |
|
無線調光制御システム |
時間帯や外光の状況に応じて照度を細かく調整できる |
これらの導入は初期投資が必要ですが、ランニングコスト削減と環境負荷低減を考慮すると、長期的には節約が見込めます。
冷凍・冷蔵

冷凍・冷蔵設備の主な省エネ対策は次のとおりです。
- 食品は冷ましてから庫内にいれる
- 冷蔵庫は食品を詰めすぎない
- 庫内の設定温度を見直す
- 定期的にフィルターの掃除を行う
- 冷気を逃さない工夫を行う
食品は冷ましてから庫内へ入れる
調理直後の熱い食品をそのまま庫内に入れると、庫内温度が上昇し、再び冷やすには多くの電力を消費してしまいます。これを避けるために、事前に冷ましてから庫内に入れましょう。
調理した食品をすぐに冷ましたい場合には、ブラストチラーなど急速冷却加工機器の使用を検討しましょう。
冷蔵庫は食品を詰めすぎない
冷蔵庫内に食品を詰め込むと冷気の循環が妨げられ、冷やそうと余分な電力を消費します。また、詰め込んでいる状態では食品の出し入れに時間がかかり、ドアの開閉時間が長くなることにより、外に冷気が逃げてしまうのです。
そのため、適度なスペースを空けて入れるようにしましょう。なお、冷凍庫はすき間なく詰め込んでも問題ありません。
庫内の設定温度を見直す
必要以上に低い温度設定は、電力消費を無駄に増やす原因になります。食品の品質に問題のない範囲で庫内の温度設定を見直すことも有効な対策です。
定期的にフィルターの掃除を行う
業務用の冷蔵庫や冷凍庫にはフィルターがついており、汚れが溜まると冷却効率が落ちてしまいます。取扱説明書を参考に、定期的な掃除を行いましょう。
冷気を逃がさない工夫を行う
冷気が逃げると、庫内を冷やそうとするため電力を消費してしまいます。食品の並べ方を工夫し、取り出しやすい位置に置くことで開閉時間を短縮できます。また、ビニールカーテンの設置も有効です。
ショーケース

ショーケースの主な省エネ対策は、次の2つです。
- 吸込口と吹出口を塞がない
- 冷気を逃がさない工夫を行う
吸込口と吹出口を塞がない
ショーケースの吸込口と吹出口を塞ぐと冷却効率が低下してしまいます。物を置かないことと、定期的に掃除することが重要です。
冷気を逃がさない工夫を行う
オープン型のショーケースは冷気が逃げやすいです。ビニールカーテンやナイトカバーを設置し、冷気が逃げるのを防ぎましょう。これらは汚れ防止の効果もあるため、食品を取り扱ううえでの安心材料にもなります。
店舗の省エネを成功させるコツ
省エネ対策を確実に成果につなげるためには、計画的なアプローチと継続的な取り組みが欠かせません。ここでは、具体的なポイントを5つ紹介します。
現状の「電力使用量」と「電気代」を把握する
省エネ対策の第一歩は、現状を正確に把握することです。季節や時間帯、設備ごとに電力消費・電気代の傾向が見えれば、データに基づいた具体的な省エネ対策の立案が可能になります。
電力の見える化を行う方法については以下で解説しています。
把握した現状の分析を行う
例えば、開店前の準備で冷暖房や照明を早くつけすぎていないか、閉店後も不要な機器が稼働していないかなどを確認することで、改善すべき点が明確になるでしょう。
従業員からの理解を得る
店舗の省エネには、経営者や管理者だけでなく、現場で働く従業員の協力が欠かせません。無理な節電は従業員の負担や業務効率の低下につながるため、「なぜ省エネが必要なのか」「どんな効果があるのか」を明確に伝えることが重要です。
例えば、「電気代削減が利益改善につながる」「環境負荷を減らす社会的意義がある」といった、具体的なメリットを共有すると良いでしょう。
また、従業員から省エネのアイデアを募ったり、省エネ推進役となる店舗リーダーを選任したりするなど、現場主体の取り組みにすることで、協力意識と継続性が期待できます。
できることから始める
省エネの取り組みは、「いつかやろう」と後回しにするより、今すぐにできることから始めるのが大切です。
大きな投資や大掛かりな設備変更をしなくても、身近な工夫から取り組むことができます。
例えば、使用していないエリアの照明をこまめに消す、空調の設定温度を適正に保つなどは、今日からでも始められる行動でしょう。
快適性を犠牲にしない
省エネを意識することは重要ですが、そのあまり店舗の快適性を損なってしまっては本末転倒です。
例えば、空調の設定温度を極端に変更すると、来店客が暑さや寒さを感じて滞在時間が短くなったり、購買意欲が低下したりする可能性があります。また、必要以上に照明を暗くすると、商品の見え方や店内の雰囲気が悪化し、売上にも影響が及びかねません。従業員の作業環境が悪化すれば、業務効率やサービス品質の低下にもつながるでしょう。
省エネの目的は、あくまで「ムダ」な電力消費を削減することであり、快適さや利便性まで削ることではありません。
「Panasonic HVAC CLOUD」であれば、AIが日々の利用者の空調設定を学習し、外気温度や時刻に応じて自動で設定温度を調整するため、快適性を損なわずに無理のない省エネを手間なく実現できます。
店舗の省エネ化で懸念されるコスト面への対策
省エネ化を進める際、多くの店舗が直面するのがコストの問題ではないでしょうか。すぐに取り掛かれる省エネ対策も大切ですが、「より大きな効果」や「効率的な管理」「快適性」を考えるなら設備投資が必要になってきます。
そこで活用したいのが、省エネ診断や補助金制度です。例えば、神奈川県(※)では無料で中小企業を対象に省エネ診断を実施しており、現状の調査から具体的な省エネ対策の提案まで行ってくれます。これにより、店舗側はコストだけでなく、計画立案や検討にかかる時間も節約できるでしょう。
また、国や自治体の補助金制度を活用すれば、負担を抑えて設備投資が可能です。
※出典元:中小企業省エネルギー診断(無料)|神奈川県ホームページ
まとめ
店舗の省エネ対策は、まず電力消費の実態を把握したうえで、空調・照明・冷凍冷蔵・ショーケースといった主要設備への重点的な取り組みを実施するのが効果的です。
卸小売店では空調と照明、食品スーパーではショーケースと空調、飲食店では空調と照明が特に重要な対策ポイントとなります。
成功のコツは、現状分析に基づく計画立案、従業員の理解と協力、身近な工夫からの段階的な実施、そして顧客の快適性を損なわない配慮です。省エネ診断や補助金制度の活用により、初期コストの負担を軽減しながら効果的な設備投資も可能になるでしょう。
とくに空調管理においては、「Panasonic HVAC CLOUD」のようなAI機能を活用したクラウドサービスにより、快適性と省エネの両立を実現できます。