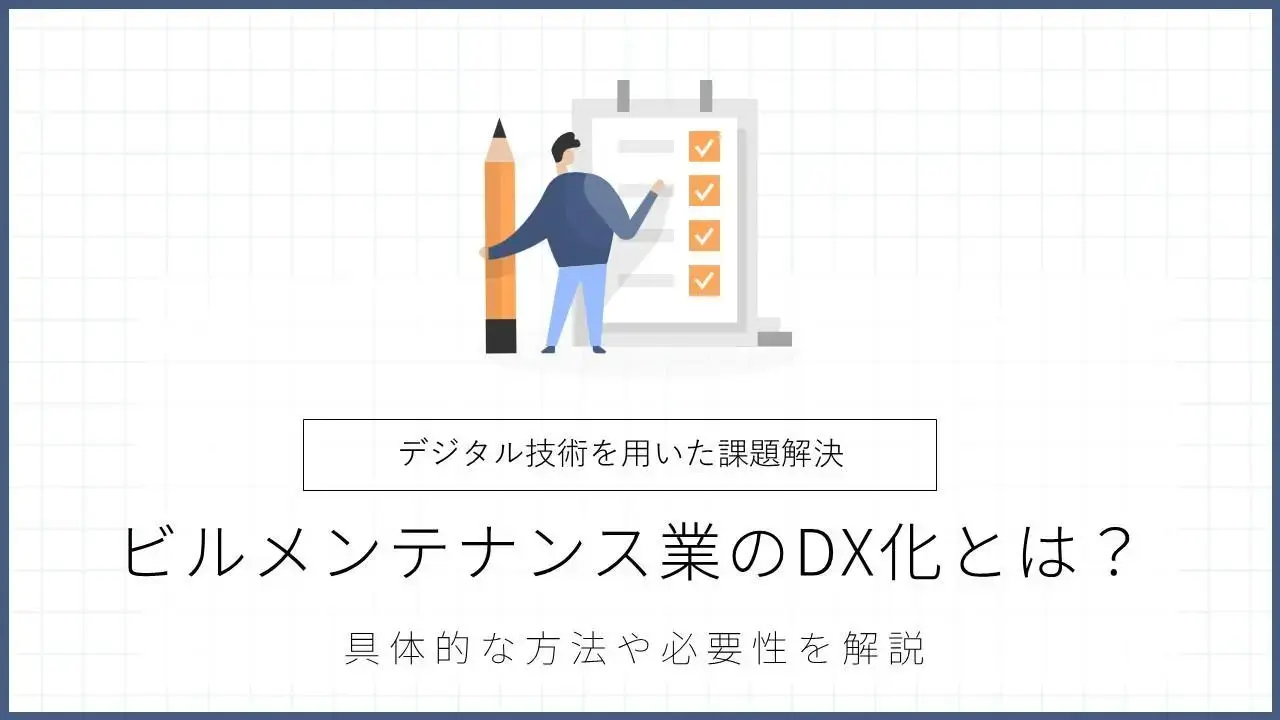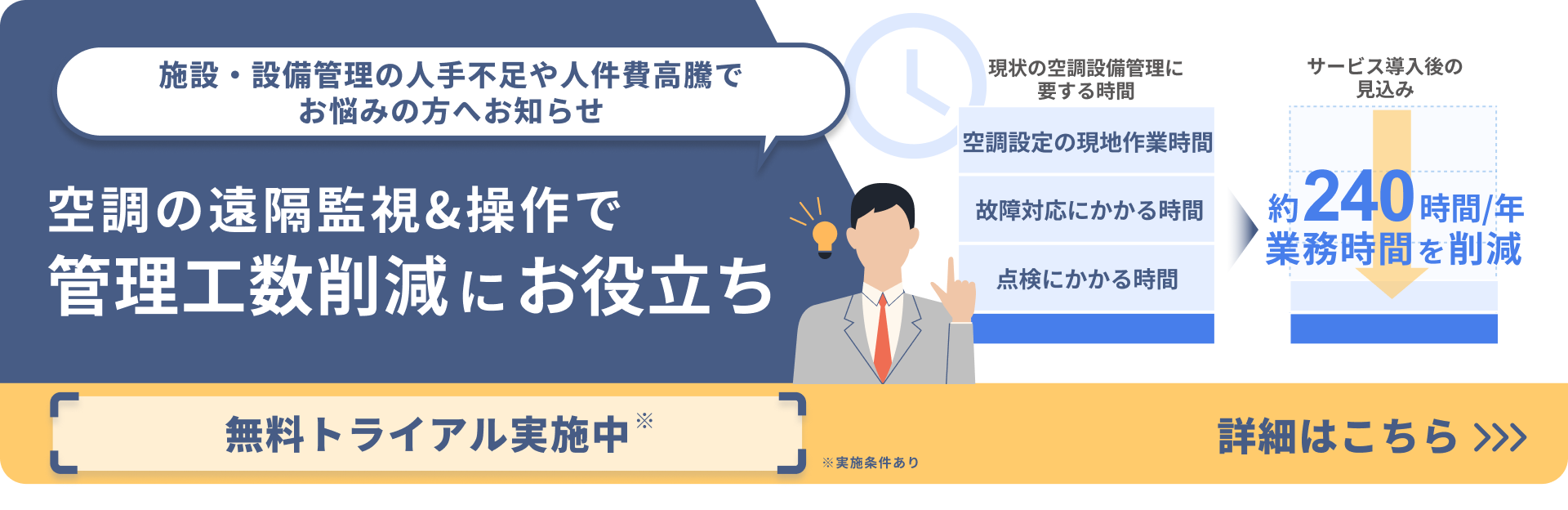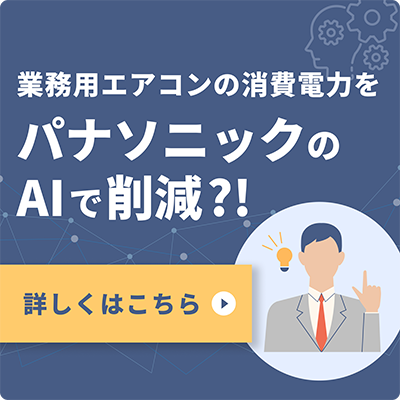ビルメンテナンス業界では、慢性的な人手不足や従業員の高齢化、価格競争の激化など様々な課題が深刻化しています。これらの課題を解決するカギとして注目されているのが、DX(デジタルトランスフォーメーション)の活用です。
従来のアナログな業務プロセスをデジタル技術で変革することで、業務効率の向上や人材不足の解消、競争力の強化が期待できます。
本記事では、ビルメンテナンス業のDX化について、その具体的な方法や必要性、成功させるためのポイントまで詳しく解説します。
ビルメンテナンスのDX化とは?
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用し、その過程で得られるデータや効率化などの成果により、サービスや業務プロセス、組織の在り方そのものを変革して競争力を高める取り組みです。
混同されやすい「デジタル化」は、紙や手作業をデジタルに置き換える工程にすぎず、その先にあるのがDX化といえるでしょう。
ビルメンテナンスにおける具体例としては、紙で行っていた点検業務をスマートフォンやタブレットに置き換えるのは「デジタル化」にあたります。一方、業務効率化によって人員の負担を軽減し、人材定着率の向上やコスト削減を通じて経営戦略まで改善する視点がDX化の特徴です。
ビルメンテナンスにおけるDX化の例
ここでは、ビルメンテナンスにおけるDX化に活用できる具体的なデジタル技術として「点検アプリ・システム」「ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)」「清掃ロボット」「トイレセンサー」「クラウド型空調制御サービス」の5つをご紹介します。
点検アプリ・システム
点検アプリ・システムは、ビルメンテナンス業務の効率化と情報の一元管理を実現するための代表的なツールです。
従来のビルメンテナンスは紙ベースで行われ、作業員が点検表を手書きし、必要に応じて写真を撮影、そのあとに事務所に戻って写真のデータを取り込み、点検表の情報をもとにPCで報告書を作成するという手間のかかるプロセスが一般的でした。
この方法では、多くの時間と人手を要するだけでなく、記入漏れや入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすく、書類の管理も煩雑になりがちでした。トラブル発生時も、共有ノートへの手書き、付箋の貼り付け、ホワイトボードに書いて知らせるなどアナログ的な手法が多かったため、対応の遅れや情報の抜け漏れが発生しやすく、情報の蓄積も困難だったのです。
点検アプリ・システムを導入することで、スマートフォンやタブレット上であらかじめ設定した点検項目に沿って、写真や点検内容を入力するだけで報告書が自動生成されます。これにより、現場での作業効率や正確性が大幅に向上するでしょう。
また、進捗状況の一覧化や、アラート機能により対応漏れも防げます。蓄積されたデータを分析すれば、設備の劣化傾向や点検頻度の最適化など、予防保全や業務改善にも活用できるようになります。
ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)
ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS:ベムス)とは、建物の電力や空調などのエネルギー使用を見える形で管理し、最適な運用を促進するシステムです。
BEMSを導入することで、受変電設備、空調・衛生設備、照明設備などの運転状況をリアルタイムで把握し、そのデータをもとに各設備の運転を最適化できます。従来の省エネ対策では、空調を弱めたり照明を間引いたりするなど、快適性を犠牲にする方法が中心でしたが、これでは業務効率の低下や利用者満足度の低下を招く恐れがありました。
一方で、BEMSを活用すると余分なエネルギーだけを削減しつつ、快適な室内環境を提供できるのです。
さらに、BEMSはエネルギー消費データを継続的に蓄積するため、設備の劣化や故障の兆候を早期に把握でき、予防保全や計画的な設備更新の立案にも役立ちます。
清掃ロボット
清掃ロボットは、人に代わってロボットが床掃除を行う機械です。ビルメンテナンス業務の中でも、最も多く受注されている業務のひとつが「一般清掃」であり、全体の94.6%を占めています(※)。
床掃除をロボットに任せることで、作業員はほかの業務に専念できるようになります。これにより、限られた人手をより効率的に活用できるほか、掃除ロボットは決められたルートで均一した清掃を行うため、清掃品質を向上させることも可能です。
清掃ロボットを導入して床掃除を自動化することで、作業効率を大幅に向上させ、人手不足が課題となっている業界においても解決の糸口となるでしょう。
※出典元:ビルメンテナンス情報年鑑2025|公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
トイレセンサー
商業施設や公共施設のトイレでは、常にキレイを保ち、トイレットペーパーやハンドソープなどの備品も補充する必要があります。
しかし、一律のスケジュールで清掃や補充を行うのは、効率的とはいえません。清掃関連のコストを削減しつつ、快適な環境を維持するためには、清掃頻度やタイミングを最適化することが重要です。
トイレセンサーを設置することで、各トイレの使用状況をリアルタイムで把握できるため、実際の利用頻度に応じた清掃スケジュールの最適化が可能になります。
また、蓄積されたデータをもとに、消耗品の補充タイミングを予測することもできます。これにより、人的リソースを効率的に活用できるほか、清潔で快適なトイレ環境を常に維持することができるでしょう。
クラウド型空調制御サービス
空調制御を行うサービスを活用することも、ビルメンテナンスをDX化する方法の1つです。
例えば、パナソニックが提供する「Panasonic HVAC CLOUD」は、空調設備の運用・管理をクラウドベースで一元化できる空調制御サービスです。AIによる空調設備の設定温度制御、消費電力量の推移の可視化、異常発生の通知などができます。
また、クラウドシステムだからこそ実現できる、ビルA、ビルB、ビルCといった複数拠点の空調設備を遠隔で一括管理できる機能も備えており、管理業務の手間を減らします。
具体的に「Panasonic HVAC CLOUD」は以下のようなことが可能です。
- 空調運転の一括遠隔管理
複数拠点の空調機器がそれぞれ何度に設定されているかを、遠隔で一括管理できます。スケジュール設定による切り忘れ防止や、設定温度・空調消費電力量の可視化によるムダの発見・見直しが行え、空調消費電力量と空調設備管理工数の削減に貢献します。
- 警報メール通知
空調機器に異常が発生した際、エラーコードをメールで通知します。
遠隔で異常を確認できるため、「故障に気づかず空調機を使用できない」といった事態を未然に防ぎやすくなるでしょう。
初動対応で現地に赴く手間が省けて工数の削減になるほか、修理・交換の対応の手配もスムーズに行えます。
- AI省エネコントロール
AIによる運転制御で省エネと快適性を両立する業界初の機能(※1)です。
施設情報・利用者の空調設定・気象情報・時刻設定といった内容をAIが学習し、外気温度や時刻に応じた設定温度を自動調整します。人による過剰な快適運用を防ぐことができ、実証実験では1年間で約20%の空調消費電力量削減効果が確認されています(※2)。
- 設定温度の可視化
物件ごとに設置されている空調設備の設定温度の推移をグラフで可視化できます。
これにより、ムダな運用を行っている店舗を発見し具体的な節電対策を実施可能です。
(※1)2023年2月時点 空調業界当社調べ。
(※2)1年間、関東地方の2つの異なる物販店舗(約1,000㎡)の施設で検証。「設定温度自動リターン」機能(一定時間で指定した温度設定に戻る機能)との比較。
ビルメンテナンス業のDX化が必要な理由
ビルメンテナンス業界が抱える課題は複雑で多岐にわたりますが、その多くがDX化によって解決できる可能性を秘めています。業界全体の構造的な問題として浮き彫りになっているのが、労働力の確保と品質維持の両立の困難さです。
ビルメンテナンス業のDX化が必要な主な理由は、以下の4つです。
● 慢性的な人手不足
● 従業員の高齢化
● 賃金上昇や価格競争による経営の圧迫
● 業務の属人化
これらの課題は、「公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会(※)」が2015年度から2024年度までの10年間に実施した調査で、ビルメンテナンス業の「お悩みごと」としても上位に挙げられています。
※出典元:ビルメンテナンス情報年鑑2025|公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
慢性的な人手不足
公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会が実施した調査によれば、2015年度から2024年度の10年間で常にトップだったのが「現場従業員が集まりにくい」であり、慢性的な人手不足が続いていることがわかります。
そのような状況の中、ビルメンテナンス業はコロナ禍による衛生意識の高まりや、地球温暖化対策としての省エネ・脱炭素化の拡大などで社会的ニーズが高まっています。人の手による作業が中心となるこの業界では、人材の不足がそのまま機会損失やサービスの質低下につながりかねません。
こうした課題に対応するため、DXによる業務効率化や生産性向上が不可欠となっているのです。
従業員の高齢化
「全国ビルメンテナンス協会」の同調査によれば、ビルメンテナンス業が抱える課題として2番目に多かったのが「現場従業員の若返りが図りにくい」でした。
日本全体で進行する少子高齢化と人口減少により若手人材が確保できなければ、ベテランからの技能継承や長期的な人材育成が困難となり、将来的なサービス品質の維持にも影響するでしょう。
こうした背景から、DXによる業務効率化や省人化、さらには職場環境の改善によって、若い世代にも魅力的に映る職場づくりが急務となっています。
賃金上昇や価格競争による経営の圧迫
同調査では3番目の課題として挙げられているのが「賃金上昇による経営の圧迫」です。
さらに2018年度からは、新たな課題として「オーナーに対する料金交渉の難しさ」も浮上しました。
とくにビルメンテナンス業では、オーナーにとってより良い条件を提示した会社と契約を締結する競争入札が行われることがあり、価格競争が激化しやすい傾向にあります。このため、賃金が上昇しても契約料金に反映しにくく、経営を圧迫する要因となっているのです。
DXの推進によって、業務効率化による人件費の削減、電気代などのエネルギーコストの削減、ペーパーレス化による紙代・インク代の削減など、多方面からのコスト削減が可能になります。その結果、生産性向上による利益率の改善も図れるでしょう。
業務の属人化
同調査において業界課題の第4位として挙げられてきたのが「現場管理者の育成」です。ビルメンテナンス業界では、長らく紙やホワイトボードでの管理・情報共有が主流だったため、現場で得られた知識や情報が体系的に蓄積されにくく、共有の仕組みも不十分でした。
その結果、トラブル発生時には経験豊富な特定の担当者しか対応できない、過去の事例を参考にした迅速な解決が困難といった非効率かつ業務の偏りが生まれていました。DX化により、点検記録や作業履歴、トラブル対応の事例を一元管理すれば、誰でも必要な情報にアクセスでき、属人化を防止できます。
これにより、人材育成や引き継ぎもしやすくなるでしょう。
ほかにもあるビルメンテナンス業のDX化を行うメリット
ビルメンテナンス業が抱える課題に対するメリット以外にも、「環境負荷への貢献」「顧客満足度の向上」といったメリットがあります。
社会全体が持続可能性や顧客体験の向上を重視する現代において、DX化は企業の競争優位性を高める重要な要素となるでしょう。
環境負荷への貢献
近年、地球温暖化や資源枯渇といった課題を背景に、企業活動における環境配慮が強く求められており、DX化はその対応策として有効です。
例えば、業務のデジタル化によるペーパーレス化は、紙の使用量を削減でき、CO2を吸収する役割を担う森林伐採の抑制、さらには紙の焼却時に発生するCO2の削減につながります。
また、デジタル技術を活用して点検や清掃のタイミングを最適化すれば、現場への不要な移動を減らせるため、自動車の使用回数低下による排気ガス削減も可能です。
顧客満足度の向上
DX化により、蓄積された点検記録や過去のトラブル事例を容易に参照できるようになります。
これにより、同様のトラブルを未然に防ぐ対策が立てやすくなり、発生した場合でも迅速かつ的確な対応が可能になります。さらに、データを活用して清掃のタイミングを最適化することで、常に清潔で快適な環境を維持できるでしょう。
このように、DX化は品質の高いサービスの提供を可能にし、顧客満足度の向上が期待できます。競争が激化するビルメンテナンス業界においては、単なる価格競争に頼るのではなく、こうした安心・安全・快適性という付加価値を打ち出すことが、他社との差別化や長期的な契約維持にもつながるのです。
ビルメンテナンス業のDX化を成功させるポイント
DX化の取り組みを成功させるためには、技術導入だけでなく、組織全体の変革マネジメントが重要です。多くの企業がDXに失敗する背景には、技術的な視点だけに偏り、現場や人への配慮が不足していることが挙げられます。
以下では、DX化を成功に導くための重要なポイントを解説します。
まずは経営層がDXについて理解を深める
経営層がDXの本質を理解していなければ、単なるデジタル化に留まったり、現場任せになり現場の負担が増えたり、現場の理解が得られない可能性があります。まずは、経営層が会社の存在意義や将来的な理想像を明確にし、現状と理想のギャップを分析したうえで、達成すべき具体的な目標を設定することが重要です。
その目標を踏まえ、DXによってどのような価値を生み出せるのかを考えると、具体的な方針が定まります。
また、DX導入の目的や効果を現場にもわかりやすく伝えられるようになり、現場の納得感を得ながら計画を進められるでしょう。「公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会」などが実施するセミナーを活用して理解を深めることも一つの手です。
DX推進のチームを構築する
DX化を効果的に進めるには、専門チームの構築が欠かせません。誰が主体となってDXを推進するのかを決めないと、責任や役割があいまいになり、計画が停滞する可能性があります。
チームには、デジタル技術に詳しい担当者だけでなく、現場の業務知識を持つスタッフも参加させることで、実務に即した導入計画や運用ルールを策定できるでしょう。
自社だけで進めるのが困難な場合は、外部パートナーの専門的な知見を取り入れることで、DX化を効果的かつ円滑に進めることが可能です。
まとめ
ビルメンテナンス業界では、慢性的な人手不足、従業員の高齢化、賃金上昇による経営圧迫、業務の属人化といった課題が長期間にわたって深刻化しています。こうした構造的課題に対し、有効な打ち手として注目が集まっているのがDX化です。
点検アプリ・システムやBEMS、清掃ロボット、トイレセンサーなど、様々なデジタル技術の導入により、業務効率の向上と人的リソースの最適な活用が実現できます。さらに、環境負荷の軽減や顧客満足度の向上といった付加価値も創出でき、単なる価格競争から脱却した差別化戦略の構築も可能です。
DX化を成功させるためには、経営層のDXに対する深い理解と、現場と連携した専門チームの構築が重要となります。特に空調管理においては、「Panasonic HVAC CLOUD」のようなクラウド型制御サービスを活用することで、複数拠点の一括管理や省エネ効果の最大化を図ることができるでしょう。