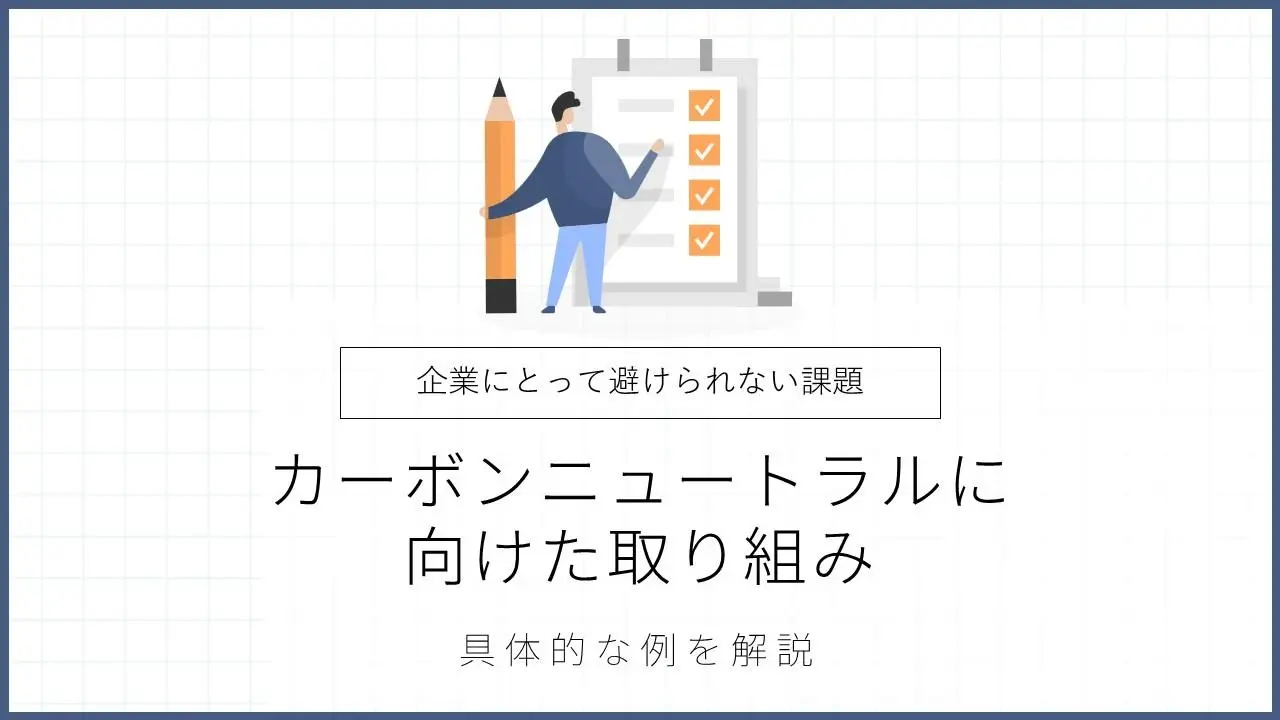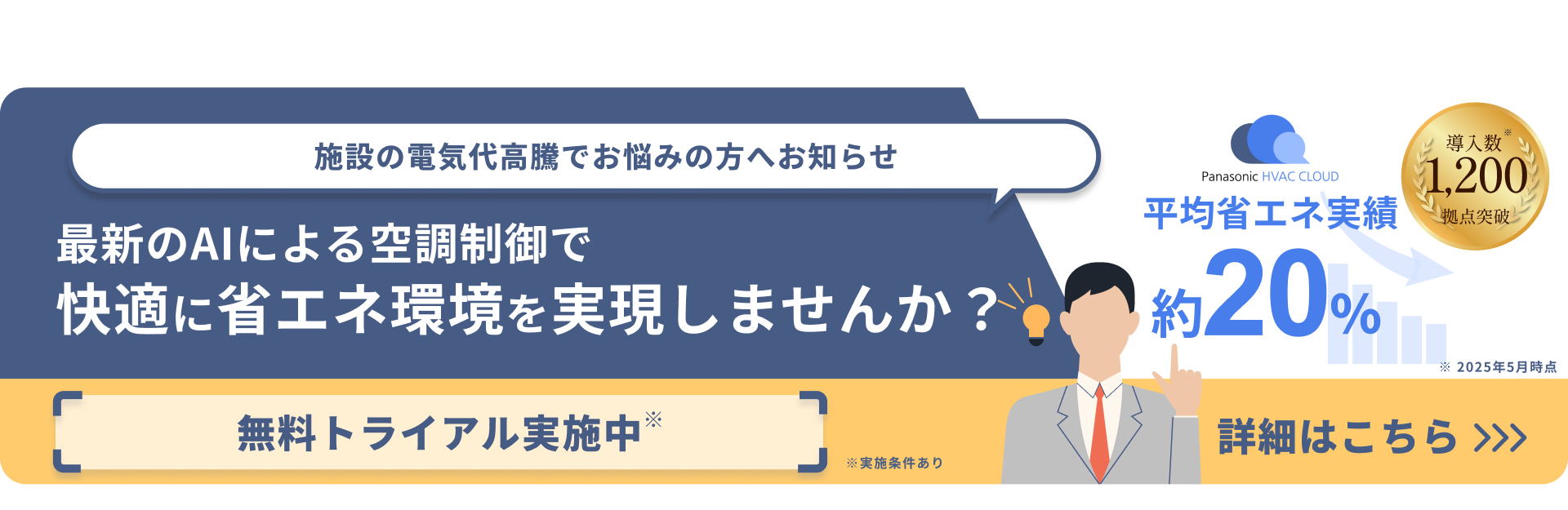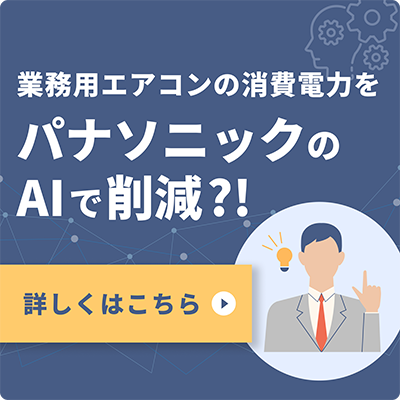気候変動問題の深刻化に伴い、企業にとってカーボンニュートラルへの取り組みは避けて通れない課題となっています。
そもそもカーボンニュートラルとは、事業活動や日常生活で排出される温室効果ガスを可能な限り削減し、どうしても排出を避けられない分については植林などによる吸収・除去で埋め合わせ、実質的に排出量をゼロにする取り組みを指します。
2020年時点でも産業革命以前(1850~1900年頃)と比べて地球の平均気温はすでに約1.1℃上昇しており、このまま温室効果ガスの排出が増え続ければ、私たちの暮らしや経済活動に深刻なリスクがさらに拡大すると懸念されています。
本記事では、カーボンニュートラル実現に向けて具体的な取り組みについて解説します。
カーボンニュートラル実現に向けた具体的な取り組み
カーボンニュートラルに取り組むにあたって、まず知っておきたいのが温室効果ガスの種類とその排出実態です。温室効果ガスとは、地球を覆って熱を閉じ込める働きを持つ「CO2(二酸化炭素)」「メタン」「一酸化二窒素」「フロン類」の総称ですが、その中でも約9割を占めるのがCO2です。
そして、CO2の排出量を分野別に見ると、最も多いのはエネルギー転換部門で、全体の約38.3%を占めます。その多くは、火力発電によって電気をつくる際に排出されたものです。
引用:4-04 日本の部門別二酸化炭素排出量(2023年度)
また、産業部門や運輸部門、その他部門などの分野においても電力使用に伴うCO2排出が含まれています。つまり、カーボンニュートラルを進めるうえでは、電力の使用量を減らすことが非常に効果的だということです。
もちろん、温室効果ガス全体の約1割を占めるメタンや一酸化二窒素、フロン類の削減もカーボンニュートラルの実現には欠かせません。実際、フロン類は地球温暖化への深刻な影響があるとされ、フロン類が大気中へ排出することを抑制する法律「フロン排出抑制法」も整備されています。対象となる機器を使用している企業は、法令に沿った対応が求められます。
とはいえ、温室効果ガス全体の大部分をCO2が占めていることから、カーボンニュートラルを効率よく進めるには、CO2の排出削減に重点的に取り組むことが効果的なアプローチといえるでしょう。
※出典:4-04 日本の部門別二酸化炭素排出量(2023年度)
既設機器のエネルギーの使い方を見直す
エネルギーの使い方を見直すことは、コストや時間をかけずにすぐ取り組めるカーボンニュートラルへの第一歩です。
- 使っていない部屋の照明や空調を消す
- 無理のない範囲で空調の設定を調整する
- 空調のフィルターを定期的に清掃する
- 長時間席を離れる際にはパソコンやプリンターなどのOA機器の電源を切るか、スタンバイモードに切り替える
- ディスプレイの明るさを抑える
- 使用頻度の低い機器のコンセントを抜く
- クールビズやウォームビズを導入して空調の必要性を下げる
省エネ設備の導入・更新
建物の電力使用量の中で、空調が占める割合は特に高いです。例えば、夏季のオフィスビルにおける17時頃の電力消費のうち、空調は約49%を占めています。
そのため、空調設備を見直すことは省エネ対策として非常に効果的です。省エネ設備の導入や更新は、初期投資こそかかるものの、効果的にカーボンニュートラルに取り組む方法のひとつです。
- 蛍光灯からLED照明に替える
- 省エネ性能に優れた空調に替える
- エネルギー運用の最適化を図るシステムを導入する
例えば、エネルギー運用の最適化を図るシステムには、デマンド監視装置・デマンドコントロールシステム・エネルギーマネジメントシステムがあります。照明や空調を手動でこまめに調整することも大切ですが、建物が大規模になるほど管理は煩雑になりがちです。
システムを導入することで、ムダな消費電力量を的確に把握し、データに基づいた効率的な管理や自動制御が可能になります。
|
デマンド監視装置 |
設定した目標値を超えそうになると警報を出すシステム |
|
デマンドコントロールシステム |
警報に加え、設備の稼働を自動的に制御する機能を備えたシステム |
|
エネルギーマネジメントシステム |
情報通信技術(ICT)を活用してエネルギーの使用状況を可視化・最適化するシステム |
再エネ設備の導入・再エネ電力の購入
太陽光発電や風力発電、バイオマス発電などの再生可能エネルギー(再エネ)設備は、CO2(二酸化炭素)を排出しません。敷地内に太陽光発電設備を設置することで、CO2排出量の削減に加え、自家消費による電力コストの削減も同時に図れます。
敷地や予算の制約により再エネ設備の導入が難しい場合には、再エネを調達できる電力プランに切り替えるだけでも、火力発電に依存する消費電力量を減らすことが可能です。こうした間接的な方法でも、十分にカーボンニュートラルに貢献できます。
環境負荷を考慮した移動手段の選択
1人が1km移動するのに排出するCO2は、車145g、バス66g、鉄道20g、自転車や徒歩は0gとなっています。短距離であれば自転車や徒歩を選び、遠距離ではできるだけ公共交通機関を利用することで、CO2排出量を大幅に削減できます。
また、事業用車をガソリン車から、電気自動車(EV)に置き換えるのも効果的な方法です。電気自動車は製造や充電に電力を使うためCO2をまったく排出しないわけではありませんが、走行時の排出はゼロです。製造から廃棄までのライフサイクル全体でみると、ガソリン車と比較してCO2排出量を抑えられるとされています。
※出典:気候変動キャンペーン Fun to Share | 「移動」を「エコ」に。 smart move
カーボン・オフセットの活用
カーボン・オフセットとは、まず自らできる限り温室効果ガスの削減に努めたうえで、どうしても排出を避けられない分を、排出量に見合った削減活動に投資することで埋め合わせようとする取り組みです。
具体的には、森林保全や植林事業、再エネの導入支援などのプロジェクトに資金を拠出し、その活動で創出された排出削減量を自社の排出量と相殺します。
こうした取り組みを行うことで、実質的にカーボンニュートラルをめざすことが可能です。また、この取り組みの信頼性を担保するため、国が整備している「J-クレジット制度」などを活用することが推奨されます。
■J-クレジット制度とは?
|
J-クレジット制度とは、環境省、経済産業省、農林水産省が運営するベースライン&クレジット制度であり、省エネ・再エネ設備の導入や森林管理等による温室効果ガスの排出削減・吸収量をJ-クレジットとして認証しています。
|
カーボンニュートラルに取り組むにあたって考えられる課題
世界各地でカーボンニュートラルへの動きが急速に広がる中、企業にとっても環境への取り組みは避けて通れない課題となっています。一方で、コストや手間がかかることを理由に、取り組みを後回しにしている企業も少なくありません。
コストや手間などの負担を抑えるためには、まずCO2の削減効果が大きい部分から優先的に取り組むのが効果的です。例えば、事務所やビル、商業施設などでは、業務用エアコンが最大のエネルギー消費源となっているケースが多く見られます。
そのため、省エネ性能に優れた空調設備への入れ替えや、デマンド監視装置・デマンドコントロール・エネルギーマネジメントシステムなどを導入することで、エネルギー使用量の可視化・最適化が可能になります。
例えばパナソニックの「Panasonic HVAC CLOUD」は、AIが空調の設定温度を自動制御することで、従来の人による設定温度調整に比べて約20%の消費電力量削減効果(※)を確認しています。空調機器本体を除けば導入に必要なのはアダプターとルーターのみのため、低コストで導入が可能。また、クラウドを経由した複数拠点(店舗A・店舗B・店舗Cなど)の一括管理にも対応しているため、管理工数も抑えられます。
※1年間、関東地方の2つの異なる物販店舗(約1,000㎡)の施設で検証。「設定温度自動リターン」機能(一定時間で指定した温度設定に戻る機能)との比較。
また、設備更新の際には補助金や税制優遇を活用し、コスト削減を図ることも可能です。
■例
|
補助金 |
脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)
|
|
税制優遇 |
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 (最大14%または特別償却50%の税制措置) |
カーボンニュートラルに向けた取り組みをするメリット
カーボンニュートラルに取り組むには、設備投資や運用の見直しなど一定のコストや手間がかかります。しかし、それ以上に得られる企業価値の向上や経営上のメリットは大きいものです。
エネルギーコストを削減できる
設備の省エネ化や業務プロセスの改善により、エネルギー使用量を削減できます。CO2排出量を抑制できるだけでなく、電気代などのエネルギーコストの削減にもつながります。
初期投資がかかるものの、エネルギーコストの削減分で回収でき、長期的には大きな経済的メリットが期待できるでしょう。
取引先との関係性構築や新たな取引先の獲得につながる
環境意識の高まりにより、多くの企業が取引先に対してサステナビリティの取り組みを求めるようになっています。そのため、積極的に環境対策を進めている企業は、社会的評価が高まり、取引の継続や拡大に有利に働きます。
こうした姿勢は、信頼関係の構築や新たな取引先の開拓にもつながるでしょう。
自社の知名度や認知度向上が期待できる
カーボンニュートラルへの積極的な取り組みは、先進事例としてメディアや行政に取り上げられることがあります。こうした露出を通じて、自社の知名度や認知度を高めることが可能です。
加えて、環境問題への姿勢が評価されれば、企業ブランドの価値向上にもつながります。
資金の調達がしやすくなる
近年、環境・社会・ガバナンス(ESG)を評価する金融機関が増えており、サステナブルな経営を実践している企業に対して融資条件の優遇を行うケースがあります。これまでは利益率などの経済指標をもとに投資判断が行われてきましたが、気候変動が国際的な課題として注目される中、「気候変動リスクに適切に対応できていない企業」は将来的な経営リスクとみなされるようになりました。
そのため、投資先の選定においては、ESGといった非財務情報も重視される傾向にあるのです。
優秀な人材の獲得につながる
環境問題への関心が高まる中で、働き手は社会的責任を果たす企業を選ぶ傾向が強まっています。企業が積極的にカーボンニュートラルに取り組む姿勢を示すことで、信頼や共感を呼び、職場環境への満足度が向上します。これにより、既存社員の離職率低下や生産性向上が期待できます。
また、環境問題に関心をもつ新たな人材の獲得にもつながります。
カーボンニュートラルに向けた取り組みをしないリスク
カーボンニュートラルへの取り組みを怠ることで生じるリスクも存在します。環境規制の強化や社会的要請の高まりを考慮すると、早期対応は企業の競争力を維持するうえでも重要です。
カーボンプライシングによるエネルギーコストの増加
カーボンニュートラルに取り組まない企業は、今後の環境規制強化によりエネルギーコストの増加リスクを負う可能性があります。実際に、カーボンプライシング(炭素への値付け)として、「排出量取引制度」と「化石燃料賦課金(炭素税)」の2つの導入が決まっています。
排出量取引制度は企業ごとにCO2排出量に上限を設け、超過分を他社と取引できる仕組みです。すでに一部地域で実施されており、2026年度から本格稼働が決定しています。
化石燃料賦課金(炭素税)は企業が排出するCO2に対して課税する制度で、2028年度からの導入が決定しています。
|
排出量取引制度 |
企業ごとにCO2排出量に上限を設け、それを超過した企業と下回る企業とで排出量を取引する制度。すでに一部地域で実施中で、2026年度から本格稼働が決定している。 |
|
化石燃料賦課金(炭素税) |
企業が排出するCO2に対して課税する制度。2028年度からの導入が決定している。 |
電気代高騰による経営圧迫
カーボンニュートラルへの取り組みを怠ると、電気代高騰の影響を受けて企業の経営を圧迫するリスクが高くなります。
近年、石油や天然ガスなどの化石燃料価格の上昇や円安といった国際情勢によってエネルギーコストが値上がりしています。これに加えて、国内では再生可能エネルギーの導入を促進するための賦課金が電気料金に上乗せされています。
これらの複合的な要因により電気代は値上がりしており、結果として企業の経営を圧迫することにつながります。

取引先との契約解消
近年、サプライチェーン全体での温室効果ガス削減を進める動きが広がっており、多くの企業が取引先に対してカーボンニュートラルへの取り組みを要請しています。
とくにSBT(Science Based Targets)を認定している企業では、温室効果ガスの排出量を「スコープ1(自社の直接排出)」「スコープ2(購入した電力等の使用に伴う間接排出)」「スコープ3(取引先を含むサプライチェーン全体の間接排出)」の3つの分類で管理することが求められています。
引用:SBT(Science Based Targets)について
このため、取引先が温室効果ガスの削減に消極的である場合、自社のスコープ3の目標達成が難しくなることから、契約の解消や縮小を招く可能性が高まります。
競争力低下
環境意識の高まりとともに、消費者や取引先は環境配慮型の企業や製品を積極的に選ぶようになっています。環境対策を積極的に進める企業は、ブランドイメージの向上や新規顧客の獲得につながりやすく、市場での優位性を築けます。
一方で、対応が遅れる企業は市場からの評価が低下し、シェアを失うリスクが高まるでしょう。環境問題への関心が高い人材の応募が集まりにくくなるなど、人材確保の面でも競争力を損ないやすくなります。
カーボンニュートラルの取り組みを進める手順
カーボンニュートラルの実現には体系的なアプローチが重要です。計画的に取り組みを進めることで、効果的な成果を得られるだけでなく、企業にとってのメリットも最大化できます。
【1】理解を深めて方針を検討する
最初のステップは、カーボンニュートラルの目的や背景を正しく理解することです。気候変動が企業活動や社会全体に及ぼす影響、今後の規制や取引先からの要請など、多角的な視点で情報を整理しましょう。
情報収集の方法としては、先行事例を持つ取引先や顧客に話を聞く、地方自治体や商工会議所、金融機関に相談する、関連するイベントやセミナーに参加する、政府機関や自治体が公開している資料を確認するなどが挙げられます。
こうした情報をもとに、自社にとって実現可能な取り組みの方針や、進めることで得られる付加価値を考えましょう。
【2】CO2排出量の算定と削減対象を特定する
次に行うべきは、自社のCO2排出量を正確に把握することです。現状を「見える化」することで、改善すべきポイントや優先順位が明確になります。
算定対象となる主なエネルギー種別は「電力」「灯油」「都市ガス」「ガソリン」「A重油」「軽油」「液化石油ガス」「液化天然ガス」の8つであり、それぞれ使用量に排出係数を掛けることで算定が可能です。
引用:やってみよう! 中小企業のカーボンニュートラル
こうした算定作業は複雑に感じるかもしれませんが、入力項目に沿って使用量を記録するだけで排出量を算出できる無料のツールも多数提供されています。日本商工会議所や省エネルギーセンターなどの支援も活用すれば、専門知識がなくても低コストで取り組めます。
このように、排出量を見える化することで、CO2の排出量の多い事業所や活動が特定でき、優先的に改善すべき対象を整理しやすくなるでしょう。
引用:https://www.env.go.jp/content/000114653.pdf
【3】CO2排出量の削減計画を立てる
排出量の算定と削減対象の特定ができたら、次は具体的な削減計画を立てていきます。空調の温度設定や不要な照明の消灯といった小さな取り組みでも問題ないので、まずは実施できそうなアイデアを幅広くリストアップしましょう。
そのうえで、自社の事業環境をふまえた取り組みの実施可否を判断していきます。
引用:https://www.env.go.jp/content/000114653.pdf
あわせて、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、定量的な中間目標も設定します。例えば、国が掲げる「2030年に2013年度比で温室効果ガス46%削減」という目標を自社の中間目標に据える方法もあるでしょう。
パナソニックでは、2030年度に「全事業会社のCO2排出量の実質ゼロ化」と「約1億トンの削減貢献量の創出」をめざすことを中間目標として設定し、取り組みを進めています。こうした目標をもとに、実施する取り組みの優先順位や期間を整理しましょう。
補助金を活用する場合は、申請期間や条件なども考慮に入れ、計画に盛り込むことが重要です。
引用:https://www.env.go.jp/content/000114653.pdf
【4】計画の実行と見直しを行う
策定した計画に基づき、実際の取り組みを進めていきます。設備投資が必要な対策の実施にあたっては、リース会社や金融機関へのファイナンス相談、メーカーや設備業者による助言を受けることも効果的です。実行後は、CO2の排出量を定期的に算定し、設定した目標に対してどの程度達成できているか進捗状況を把握しましょう。
必要に応じて計画や対策内容を見直し、改善を重ねることでカーボンニュートラルへの取り組みの効果を高めていけます。
引用:https://www.env.go.jp/content/000114653.pdf
【5】取り組みを発信する
カーボンニュートラルに向けた取り組みは、社内外への発信も大切な要素です。社内で積極的に共有することで、社員一人ひとりの意識が高まり、組織全体としての行動につながります。
また、社外に向けた発信は、自社の環境意識を伝える絶好の機会になります。環境に配慮した企業としての評価が高まることで、新たな取引先の獲得や自治体・関係企業からの協力、さらには人材の採用にも好影響をもたらすでしょう。
引用:https://www.env.go.jp/content/000114653.pdf
まとめ
日本の温室効果ガス排出量の約9割を占めるのがCO2であり、その中でも電力消費が最大の排出要因となっています。
カーボンニュートラル実現にあたっては、電力の使い方を見直すことが重要です。なかでも空調は事務所やビル、商業施設などの建物で最も電力を消費する設備であり、取り組みによるCO2削減効果は大きいといえるでしょう。
無理のない範囲で空調の設定温度を見直す、使用していない部屋の空調を止めるといった日々の運用改善でもCO2削減は可能です。しかし、こうした調整を手間なく効果的に継続して行うためには、管理を自動化できるシステムを導入するのが有効な方法です。
Panasonic HVAC CLOUDは、AIが空調の設定温度を自動制御し、従来の運用と比べて約20%の消費電力量削減(※)を実現します。クラウド経由で複数拠点の空調を一括管理できるため、管理工数も大幅に削減できます。ぜひ、コスト削減しながらカーボンニュートラルに取り組みたい企業の方は、導入を検討してみてください。
※1年間、関東地方の2つの異なる物販店舗(約1,000㎡)の施設で検証。「設定温度自動リターン」機能(一定時間で指定した温度設定に戻る機能)との比較。