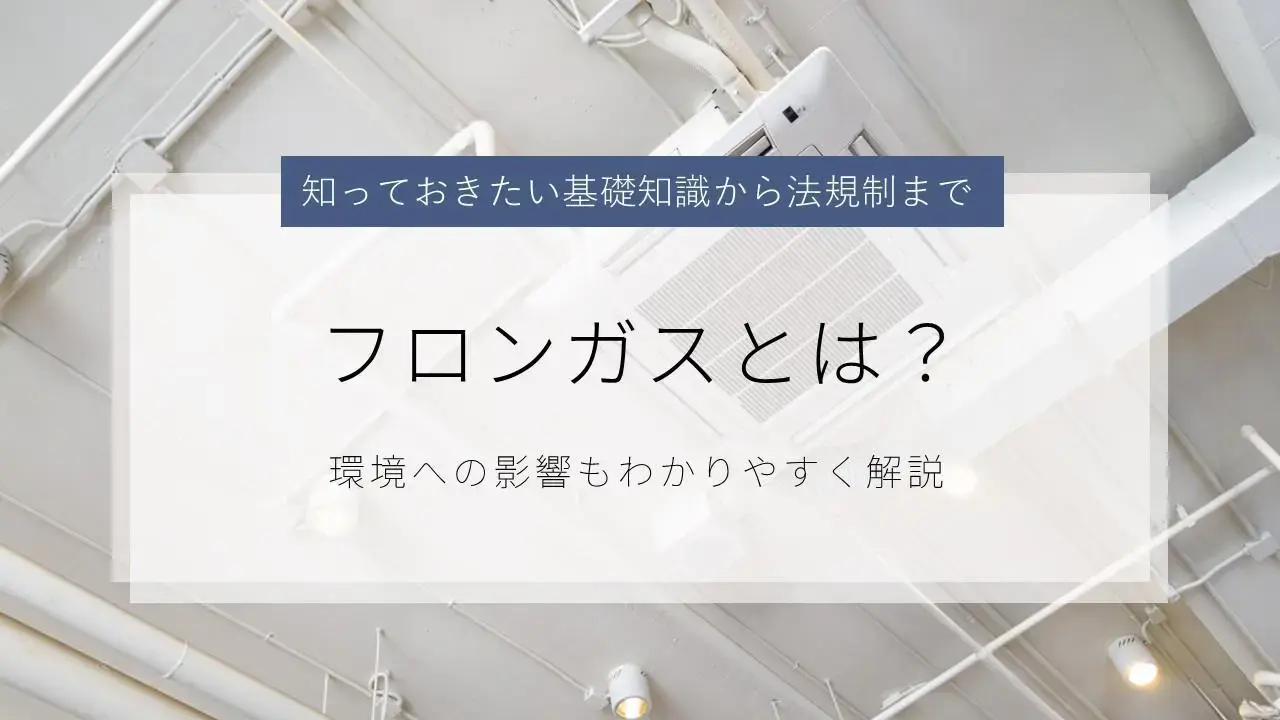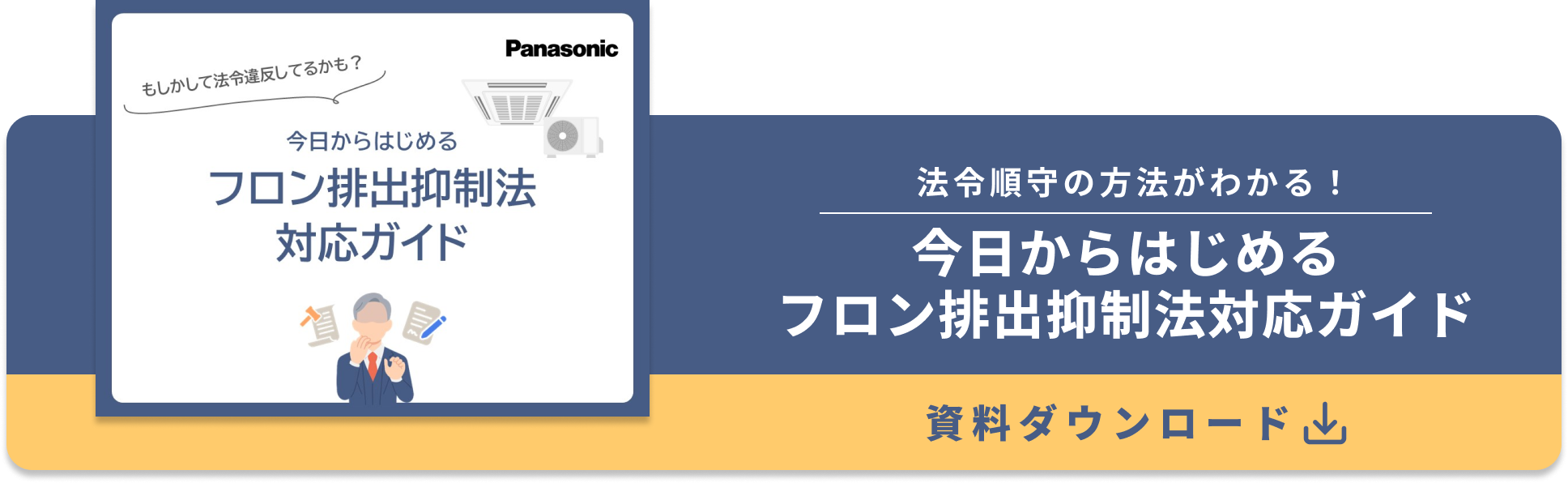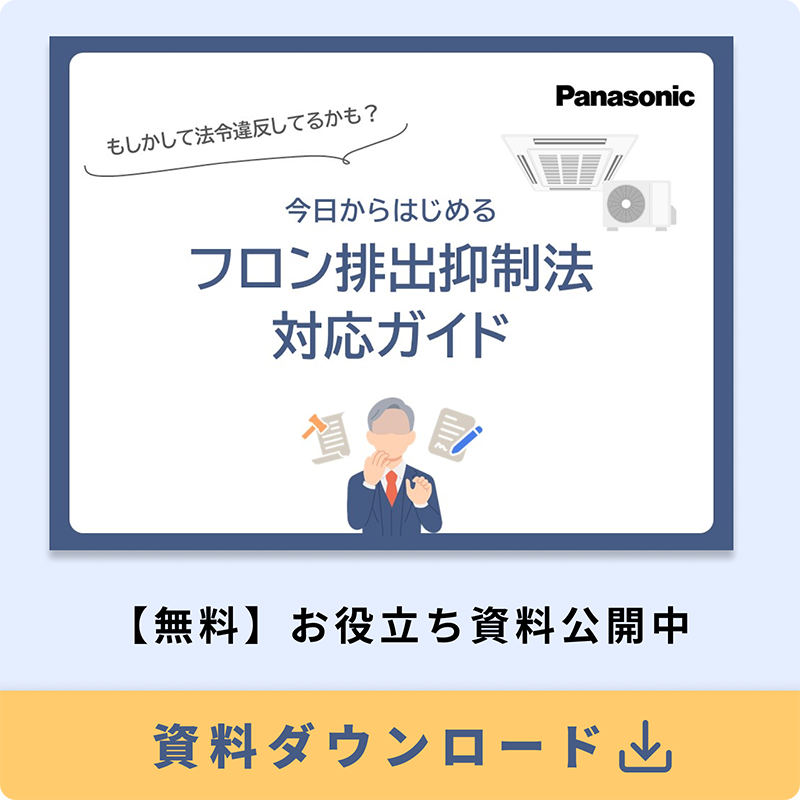フロンガスは現代社会の生活に欠かせない冷却技術に使われている一方で、オゾン層破壊や地球温暖化の原因として問題視されています。企業が適切な対策を講じるためには、フロンガスの基本的な性質と環境への影響について正しく理解することが重要です。
本記事では、フロンガスの基礎知識から法規制への対応まで、簡単にわかりやすく解説します。
フロンガスとは?
フロンガスとは、フッ素や炭素などからつくられた人工の化学物質で、正式には「フルオロカーボン」と呼ばれます。日本では「フロン」と略されて呼ばれています。
その特性と主な種類を見ていきましょう。
フロンガスの特性と用途
- エアコンや冷蔵庫、冷凍庫の温度を下げる冷媒
- 洗濯乾燥機(ヒートポンプ式)で空気を加熱・冷却する冷媒
- 電子部品の洗浄
- 発泡スチロールの発泡剤
- 断熱材の発泡剤
- ほこり飛ばしなどのスプレー
一方で、フロンガスはオゾン層の破壊や地球温暖化といった地球環境に対して悪影響を及ぼす性質もあるため、段階的に生産・消費の規制が進められています。
フロンガスの主な種類
代表的なフロンガスは以下の3つに分類されます。
|
代表的なフロンガス |
詳細 |
|
[CFC] クロロフルオロカーボン Chloro Fluoro Carbon |
<物質の詳細> 炭素・フッ素・塩素 <代表的な物質> R12、R11、R502等 <特徴> オゾン層の破壊効果・温室効果ともに高いため、先進国では1996年、発展途上国では2010年までに生産全廃 |
|
[HCFC] ハイドロクロロフルオロカーボン Hydro Chloro Fluoro Carbon |
<物質の詳細> 炭素・フッ素・塩素・水素 <代表的な物質> R22、R123等 <特徴> CFCよりは少ないものの、やはりオゾン層の破壊効果があり、温室効果も大きいため、先進国では2020年、発展途上国では2030年までの実質全廃が進められている |
|
[HFC] ハイドロフルオロカーボン Hydro Fluoro Carbon |
<物質の詳細> 炭素・フッ素・水素 <代表的な物質> R410A、R407C、R134a、R32等 <特徴> オゾン層への破壊効果が無いため代替フロンとして使われているものの、温室効果は大きいため排出削減の対象となっている |
最初に使われたCFCは、オゾン層の破壊効果・温室効果ともに大きいことから、1996年に生産が全廃されました。次に使われるようになったHCFCは、CFCと比べるとオゾン層の破壊効果・温室効果が少ないものの、地球環境への影響は依然として大きいため2020年には実質全廃となりました。
(※モントリオール議定書では、2020年時点で現存する冷凍空調機器への補充用途のHCFCに限り2029年末まで生産を認める特例が存在します。)
その次に使われるようになったHFCは代替フロンと呼ばれ、オゾン層の破壊効果は無いものの温室効果は大きいため、現在は「削減対象ガス」として、使用量の制限が進められています。
フロンガスが地球環境へ与える影響
フロンガスは、その便利さゆえに冷媒やスプレーなど幅広い用途で使用されてきましたが、地球環境に対して大きな負荷を与える物質でもあります。ここでは、特に深刻な影響を及ぼすとされる「オゾン層の破壊」と「地球温暖化」について詳しく見ていきましょう。
オゾン層の役割と破壊による地球環境への影響

引用:地球環境とフロン|環境省
フロンガスが大気中に放出されると、紫外線による化学反応によってオゾン層が破壊されます。
オゾン層は成層圏にあり、太陽からの有害な紫外線を吸収する働きがあるため、破壊されると紫外線が地上に大量に降り注ぎ、人体や生態系、植物、気候に影響を及ぼしかねません。
例えば、人体への影響としては皮膚がんや白内障、免疫機能の低下といった健康への影響を与えるとされています(※)。
※出典元:オゾン層が破壊されると…? 身近なところにも オゾン層破壊の原因が?|環境省
フロンガスが及ぼす地球温暖化・地球環境への影響
フロンガスは、地球温暖化の要因とされる温室効果ガスの一種です。
温室効果ガスとは、太陽の熱を地表付近の大気中に閉じ込める性質をもつガスの総称で、本来は地球の適温を保つうえで欠かせない存在です。仮に温室効果ガスがまったく存在しなければ、地球の平均気温は氷点下19℃にまで下がるとされており、私たちの暮らしに欠かせません。
しかし、温室効果ガスの量が増えると、大気中に閉じ込められる熱の量が増え、地球全体の気温が上昇します。この現象が「地球温暖化」であり、今や深刻な環境問題のひとつとして世界中で問題視されています。
日本における温室効果ガス排出量の割合(※)を見てみると、フロンガスは約4%と一見すると影響は少ないように思えるでしょう。
しかしながら、フロンガスは二酸化炭素(CO2)の数百倍から1万倍以上の温室効果があるとされており、わずかな排出でも地球温暖化に与える影響は極めて大きいのです。
引用:地球環境とフロン|環境省
地球温暖化は次のような深刻な問題を引き起こします。
- 気温が上昇する
- 南極などの氷が溶けて海面水位が増え、陸地が減る
- 南極などの寒い場所で生息する動植物が減る
- 農作物の生育に影響し、食べ物が少なくなる
- 暑い地域で発生する伝染病が増える
※出典元:日本の温室効果ガス排出量(2022年度)|資源エネルギー庁
このように、フロンガスの排出は単なる気温の問題にとどまらず、生態系・人類の健康・経済活動など、あらゆる分野に波及する課題として、今も国際的な対策が急がれています。
世界規模で取り組むフロンガスへの対策
ここまでご紹介したように、フロンガスが地球に与える影響は大きく、世界規模でその対策が進められています。まず、1970年代にフロンガスが地球環境に悪影響を及ぼすことが米国にて指摘され、地球規模の問題であることから、国際的な議論が始まりました。
その結果、オゾン層の保護を目的とした「オゾン層の保護のためのウィーン条約」が1985年に設立され、この条約の下で「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」が1987年に発行されました。そして、各国が「モントリオール議定書」に合意し、フロンガスの生産・消費を段階的に廃止する取り組みがスタートしたのです。
すでに「モントリオール議定書」に基づいて全廃されたCFC、2030年に向けて全世界での全廃を進めているHCFCに続き、HFCも削減対象として2016年10月に「モントリオール議定書」の対象に追加されています。
続いて、1997年には地球温暖化対策を目的とした「京都議定書」が採択されました。ここでも、HFCなどの代替フロンは温室効果ガスとして削減対象に位置づけられています。
この流れを受けて、アンモニアや二酸化炭素などによる温室効果の低い冷媒、フロンを使わない自然冷媒技術など、フロンに代わる新たな冷媒技術・製品の開発が世界規模で進められているのです。
日本におけるフロンガス対策
世界規模でフロン対策が進められていますが、日本においても独自のフロン対策を講じています。
|
日本のフロン対策 |
詳細 |
|
オゾン層保護法の制定 |
オゾン層を破壊する物質の生産自体を規制した法律 |
|
フロン排出抑制法・家電リサイクル法・自動車リサイクル法の制定 |
フロンを冷媒として使用した製品の、製造から廃棄までのライフサイクルを通じた管理について定めた法律 |
「フロン排出抑制法」「家電リサイクル法」「自動車リサイクル法」は、フロンガスが大気中へ排出されることを抑制する法律で、フロンガスを使用した製品の製造から廃棄までのライフサイクル全体を管理するため、制定されました。
次のように、対象機器ごとに別の法律が適用されています。
- 業務用の冷凍・冷蔵・空調機器:
「フロン排出抑制法」により、機器使用者に定期点検・漏えい報告・回収義務などが課される - 家庭用の冷蔵庫・冷凍庫・エアコン・ヒートポンプ式洗濯乾燥機:
「家電リサイクル法」により、家電メーカーや消費者が廃棄時にフロン回収・リサイクルを実施する - 自動車のエアコン(カーエアコン):
「自動車リサイクル法」により、廃車時に自動車リサイクル業者によってフロンの適正回収が義務づけられている
フロンガス使用機器を扱う企業が押さえておくべき対応と効率的な管理手法
日本でも「オゾン層保護法」などの法律に基づき、フロンの製造・使用・廃棄までの段階でさまざまな対策が講じられていますが、なかでも企業に密接に関わるのが「フロン排出抑制法」です。
この法律は、冷媒としてフロン類が使われている業務用の冷凍・冷蔵・空調機器の製造・販売・廃棄する者だけでなく、所有者に対しても機器の管理義務を課しているのが大きな特徴です。具体的には、機器の簡易点検や定期点検の実施、記録・保管の義務、機器廃棄時の冷媒回収と引取証明書の取得・保管などが求められます。
また、2020年の改正により「直接罰」が導入されました。違反が認められた場合には「最大1年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」が科される可能性があり、法令遵守の重要性は一段と高まっています。
一方で、法対応には人的・時間的な負担も伴うのが現実です。なかでも簡易点検は、3か月に1回以上の頻度で実施する義務があります。資格は不要ですが、社内で対応することが難しいケースもあり、アウトソーシングを検討する企業も少なくありません。
しかし、外部委託にはランニングコストがかかり、負担が大きくなってしまいます。
こういった課題を解決する方法の1つが、常時監視システムの導入です。
2022年8月の法改正により、一定の性能基準を満たす常時監視システムを用いれば、従来の目視による簡易点検を代替できることが明文化されました。