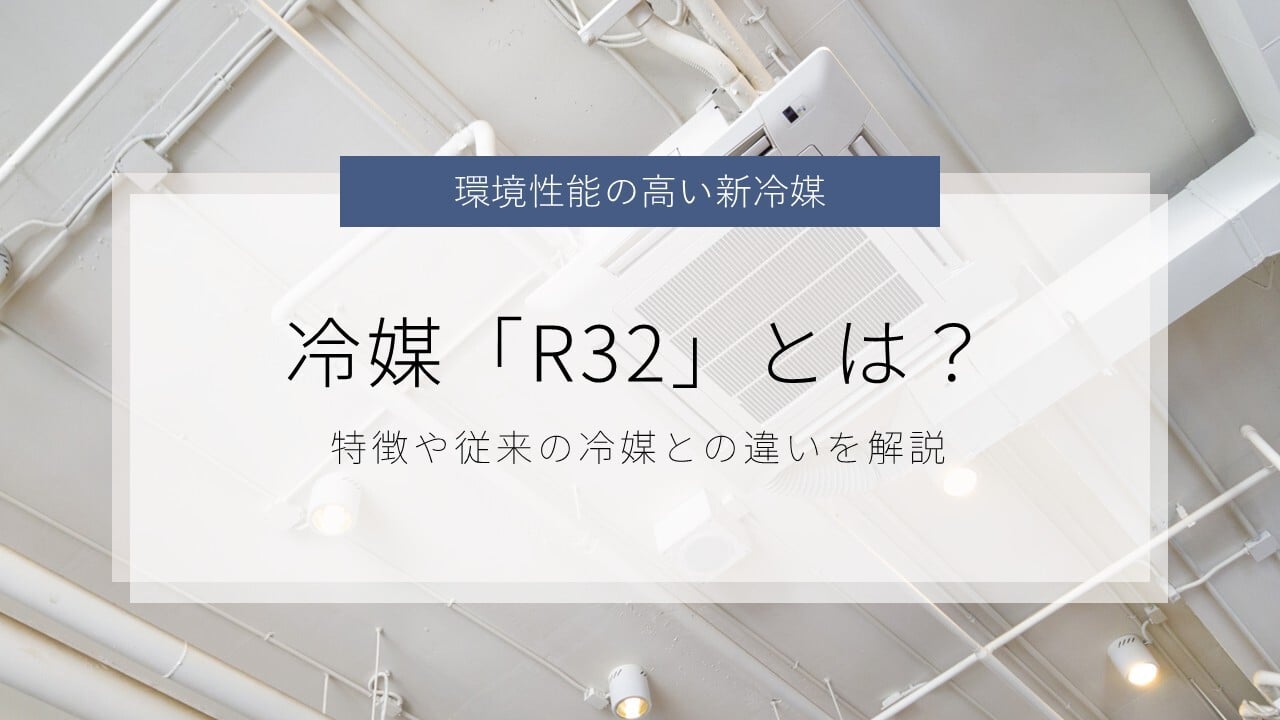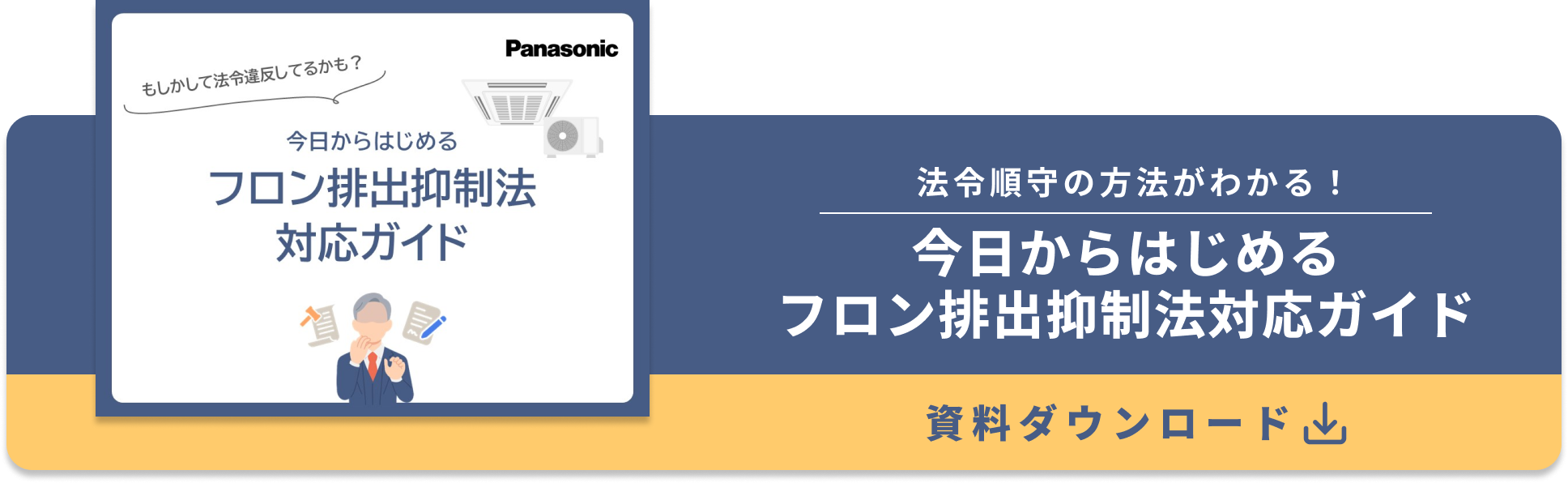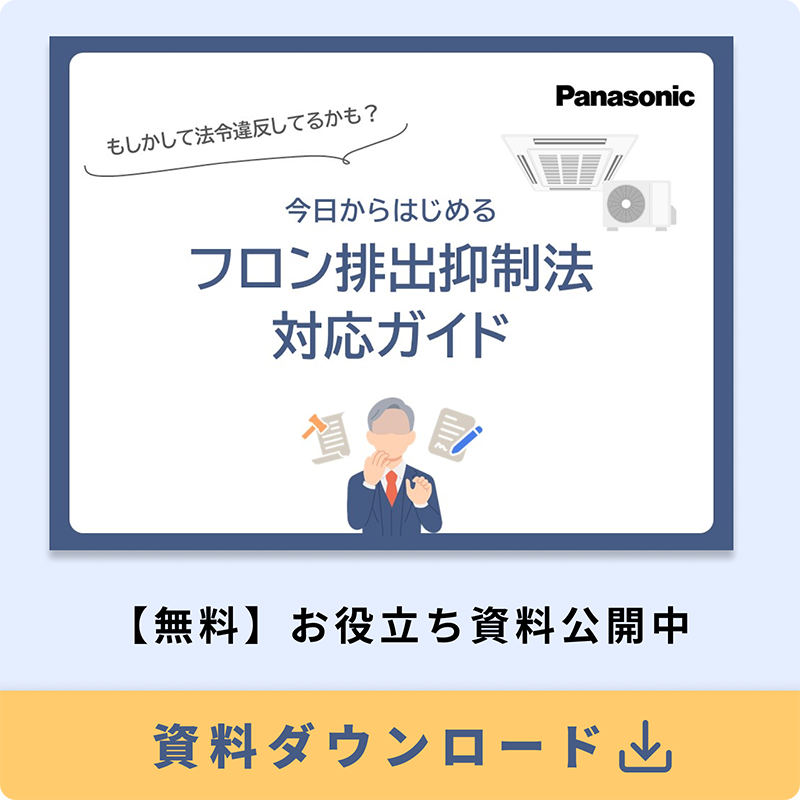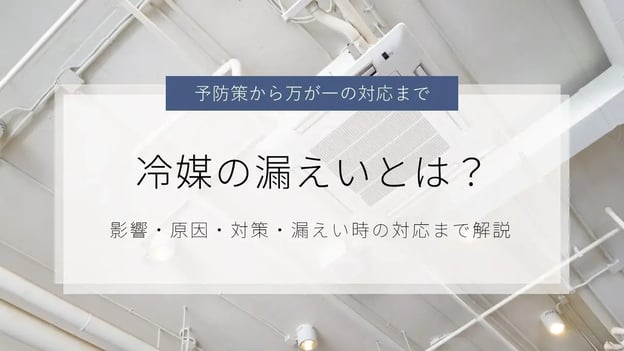地球温暖化が進行し、温室効果ガスの排出を抑える取り組みが世界的に進められています。エアコンの冷媒もその流れを受け、より環境性の高いものへとシフトしていっています。
現在、家庭用エアコンで主流の冷媒となっているのが「R32」と呼ばれるものです。
本記事では、そのR32冷媒の特徴や、従来の冷媒との違い、普及状況などについて解説します。
この記事で
わかること
- 新冷媒「R32」の特徴
- 従来の冷媒と「R32」の違い
- 「R32」の普及状況
新冷媒として登場したR32とは?
環境への負荷が少ない新しい冷媒として注目されているのがR32です。
従来の冷媒に比べてオゾン層破壊係数がゼロで、地球温暖化係数も低く、現在普及している冷媒の中では最もバランスの取れた選択肢と言えます。
すでに家庭用エアコンではR32への切り替えが進んで主流となっており、現在は業務用エアコンにもその流れが広がっている状況です。業務用エアコンにおいても、従来の冷媒からR32への置き換えは、環境への負荷やエネルギー効率の観点からも重要性が高まっています。
冷媒を取り巻く背景
冷媒は、エアコンが部屋を冷やしたり暖めたりするために欠かせない物質です。
現代のエアコンの多くは、空気中の熱を集めて冷却・加熱を行う「ヒートポンプ方式」が採用されています。冷媒はこの集めた熱を乗せて運ぶ役割(作動流体)を担うものです。
(例)ヒートポンプにおける冷媒の働き
冷媒にはさまざまな種類がありますが、その選定にあたっては、単に熱移動の性能面だけでなく、以下のような観点が重要視されるようになってきました。
- 環境性(※環境に与える影響。ODP(オゾン破壊係数)やGWP(地球温暖化係数)によって測られる)
- エネルギー効率
- 安全性
- 経済性
なかでも環境性への配慮は世界的な潮流となっており、冷媒の主流も環境負荷の少ないものへとシフトしてきた歴史があります。
地球環境を守るための国際的な枠組みづくりが進むなかで、今後もこの傾向は続くことが予想されます。
主要冷媒の変化とR32の誕生
冷媒の種類については以下の記事でより詳しく解説してい冷媒の主流は、環境性を重視する機運の高まりを背景に移り変わってきました。
以下の表は、代表的な冷媒の変遷をまとめたものです。
|
R12 (CFC:クロロフルオロカーボン) |
1928年に登場し、空調機器や冷蔵機器を中心に使用されてきた冷媒。 空気中に放出されることで、オゾン層を破壊することが判明。オゾン層破壊を防ぐことを目的に、1987年に「モントリオール議定書(※1)」によって段階的廃止が義務付けられた。 |
|
R22 (HCFC:ハイドロクロロフルオロカーボン) |
上記を受け、CFCから移行して主流の冷媒となった。 CFCよりは環境負荷が少ない冷媒ではあるが、オゾン層への影響が少なからずあることから、同様にモントリオール議定書によって2020年までの廃止が決定した。 |
|
R410 (HFC:ハイドロフルオロカーボン) |
オゾン層にダメージを与えない冷媒として、CFCから移行が進んでいった。 しかし、地球温暖化への注目が集まるなかで、その原因となる温室効果ガスとして削減すべきガスに位置づけられる。1997年に「京都議定書(※2)」において規制が進むことになった。 |
(※1)モントリオール議定書 | 地球環境・国際環境協力 | 環境省
(※2)京都議定書とは:林野庁
こうした背景から登場したのがR32で、オゾン層破壊係数が0、かつ地球温暖化係数もR410Aの3分の1程度に抑えられているのが特徴です。
現在、R32は、家庭用エアコンの分野では主流となるまでに普及が進んでいます。
なお、冷媒の種類については以下の記事でより詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
R32の特徴
R32は、オゾン層破壊係数がゼロで、地球温暖化係数も低いことに加えて、エネルギー効率の高さも大きな魅力です。
ここでは、R32冷媒の特徴を、従来の代表的な冷媒であるR410Aなどと比較しながら、より詳しく見ていきましょう。
R32とR410Aの違い
以下の表は、従来の代表的な冷媒とR32を比較したものです。R32は、オゾン層破壊係数(ODP)が0で、なおかつ地球温暖化係数(GWP)も大幅に低いことがわかります。
|
項目 |
R32 |
R410A |
R22 |
R12 |
|
構成 |
単一 |
混合 |
単一 |
単一 |
|
オゾン層破壊係数(ODP) |
0 |
0 |
0.055 |
1 |
|
地球温暖化係数(GWP) |
675 |
2,090 |
1,810 |
10,900 |
|
燃焼性 |
A2L |
A1 |
A1 |
A1 |
参照:業務用エアコンの冷媒転換について|業務用エアコン|関連製品|一般社団法人 日本冷凍空調工業会
※オゾン層破壊係数(ODP):CFC12=1としたオゾン層への影響をあらわす指標
※地球温暖化係数(GWP):CO2=1とした地球温暖化への影響をあらわす指標
※燃焼性:ISO 817 : 2014による冷媒の安全性を規定する分類
R32のメリット
R32の主なメリットは、大きく以下の2点です。
- 地球環境への負荷の少なさ
- エネルギー効率の高さ
それぞれ見ていきましょう。
地球環境への負荷の少なさ
R32は、オゾン層破壊係数(ODP)が0で、オゾン層破壊という深刻な環境リスクを引き起こしません。この点は従来の主流だったR410Aも同様です。
また、地球温暖化係数(GWP)を比較すると、R32はR410Aの3分の1以下であり、大幅に低くなっています。
さらに、R32はエネルギー効率の高さから、従来の冷媒よりも充填量を減らすことができます。
このように、R32はトータルで大きな環境負荷軽減を期待できる冷媒です。
エネルギー効率の高さ
R32は、従来のR410AやR22と比較して、1.5倍の冷凍能力を持っています。沸点が低く熱交換の効率がよいうえ、熱伝導性も高いためです。
高いエネルギー効率は、消費電力の削減にもつながります。省エネと環境保護の両方の効果が期待できる冷媒だといえるでしょう。
安全性に関する注意点
R32については、燃焼性の観点から、従来の冷媒と比べて、取り扱いに注意が必要です。
冷媒の燃焼性については、国際規格「ISO 817 : 2014」において、不燃性、微燃性、可燃性、強燃性の4段階で区分されており、R32は「微燃性」に分類されます。一方で従来主流のR410AやR22は「不燃性」でした。
引用:微燃性(A2L)冷媒を使用したビル用マルチエアコンを安全にご使用いただくためのガイドブック2023|日本冷凍空調工業会
とはいえ、R32の燃焼速度は10cm/秒以下、水平方向への炎の広がりもなく、爆発燃焼も起こしにくいことから、適切なリスクアセスメントを実施し、必要な対策を取ることで、安全に使用が可能です。
安全利用については、日本冷凍空調工業会がガイドライン(GL-20,16)を定めており、それに従って、機器の選定や冷媒漏洩時の安全対策を行う必要があります。
例えば、冷媒漏洩時の燃焼防止のため、計算結果に基づいた検知器・警報器、遮断装置、換気装置の設置が義務付けられています。
引用:微燃性(A2L)冷媒を使用したビル用マルチエアコンを安全にご使用いただくためのガイドブック2023|日本冷凍空調工業会
このように、R32は安全対策の必要性はあるものの、ガイドラインに沿って適切に行えば、安心して使用できます。
冷媒R32普及状況について
2020年に改正・施行された「フロン排出抑制法」により、R32をはじめとする新冷媒への移行が、いっそう後押しされています。
同法に基づく「指定製品制度」は、エアコンをはじめとしたフロン類使用製品の低GWP化・ノンフロン化を進めるための制度で、フロン類使用製品(指定製品)の製造・輸入業者に対し、出荷製品区分ごとに、環境影響度低減の目標値、目標年度を定め、事業者ごとに出荷台数に応じた加重平均で目標の達成を求めます。
こうした取り組みを背景に、家庭用エアコンではすでにR32が主流となり、現在では業務用エアコンでも導入が加速しています。家庭用エアコンと比べて稼働時間の長い業務用エアコンでのR32の普及は、温暖化対策やコスト削減の観点から極めて重要だといえるでしょう。
引用:R32冷媒 | 空調・換気・給湯設備(ビジネス) | Panasonic
まとめ
エアコンの冷媒は、オゾン層保護や地球温暖化の抑制といった課題を受け、より環境性能の高いものへと移行しつつあります。なかでも現在、新世代の冷媒として普及が進んでいるのがR32です。
R32は、オゾン層を破壊せず、地球温暖化係数を従来比3分の1以下に抑えるとともに、エネルギー効率を高めることで、総合的に地球環境負荷を大幅に減らすことができます。
ただし、R32は微燃性冷媒であるため、厳格な安全対策が必要です。日本冷凍空調工業会のガイドラインに基づいて、適切なリスクアセスメントと機器の選定を行う必要があります。
適切な安全対策の実施を念頭に設計を進めましょう。