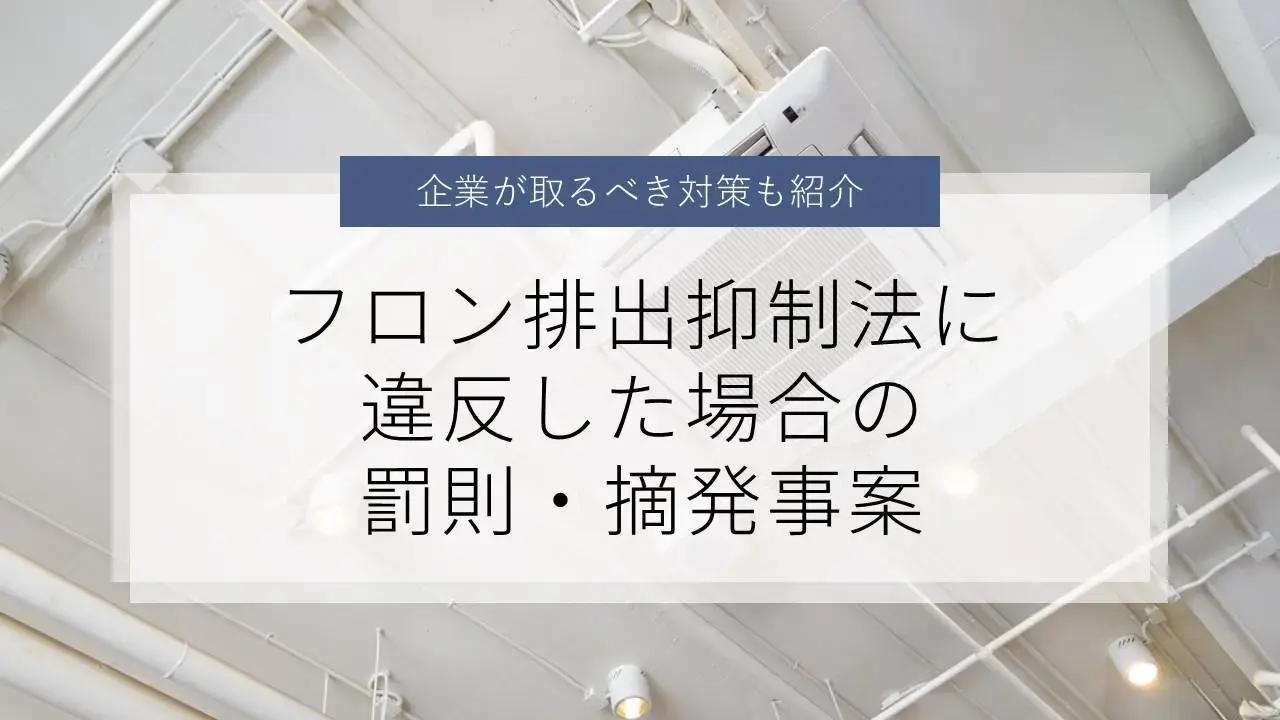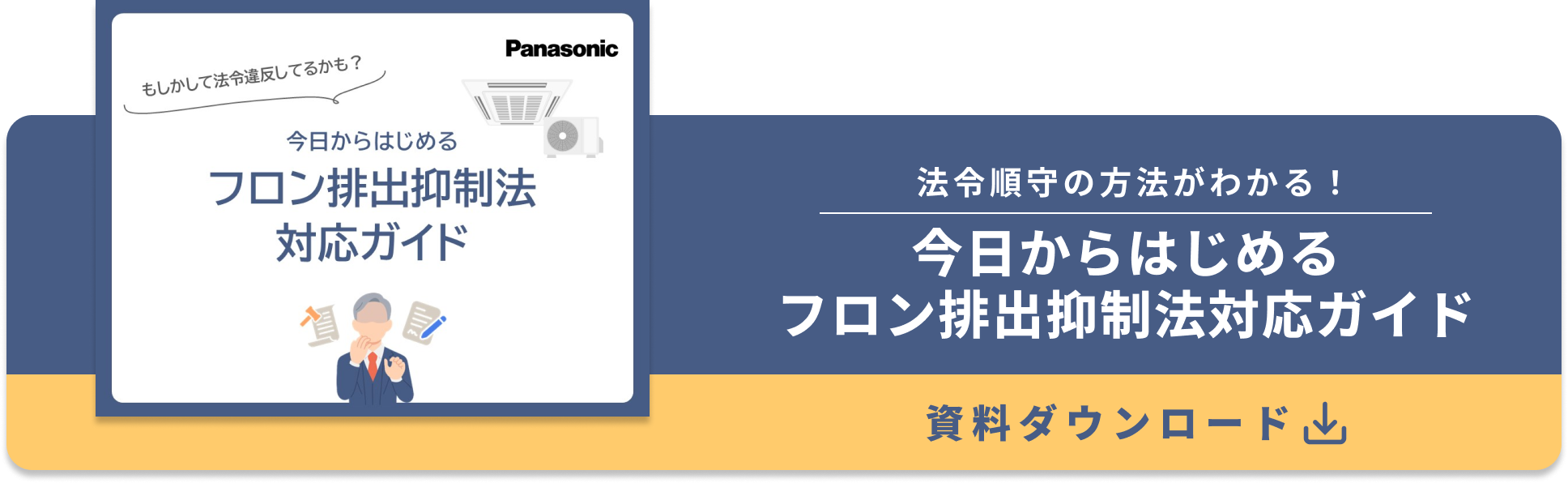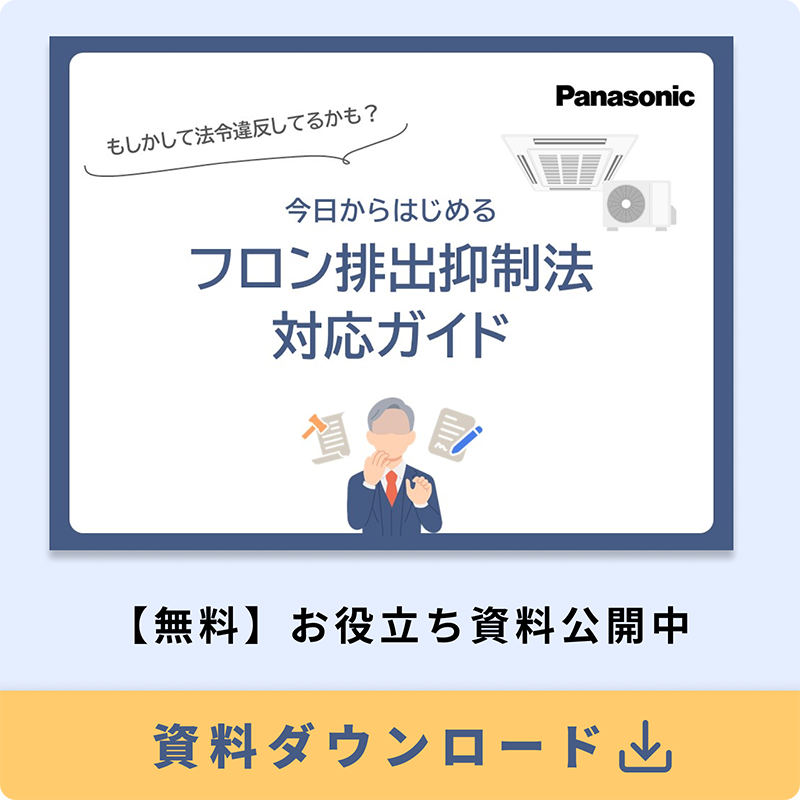フロン排出抑制法は、地球温暖化防止を目的とした重要な法律であり、違反した場合には厳しい罰則が科されます。2020年の改正により罰則が強化され、企業はより厳格なコンプライアンス遵守が求められるようになりました。
本記事では、フロン排出抑制法に違反した場合の具体的な罰則や実際の摘発事案について詳しく解説し、企業が取るべき対策についても紹介します。
フロン排出抑制法の概要については以下の記事を参照してください。
改正フロン排出抑制法の罰則が強化
2001年に制定された「フロン回収・破壊法」では、当初は勧告・命令を経たあとに従わなかった場合に罰則が適用される「間接罰」の仕組みが採用されていました。
しかし、フロン類の排出による環境負荷への懸念が高まる中、廃棄時のフロン回収率が4割弱で低迷していた実態を受け、2020年4月1日の改正により「直接罰」が導入されました。これにより、法令に違反した場合には勧告や命令を待たずに、即座に罰則が科される可能性があります。
企業は、より厳格な法令遵守が求められるようになり、違反行為に対する責任も重くなっています。
フロン排出抑制法に違反した場合の罰則
ここでは、「管理者」が対象となる主な違反行為と、それに対する罰則について詳しく紹介します。
なお、フロン排出抑制法における管理者とは、原則として第一種特定製品を所有する者とされています。法人が機器を所有している場合、その法人自体が管理者となり、代表者個人が罰則の対象となるわけではありません。
また、リース契約やレンタル利用、テナント入居などで他社が所有する機器を使用している場合、管理者が誰になるかは契約内容により判断されます。共同所有の場合には、管理者を明確にしておくために話し合いなどでの取り決めが必要です。
■第一種特定製品とは
|
以下2つに該当する「エアコンディショナー」および「冷蔵・冷凍機器(冷蔵または冷凍機能を有する自動販売機を含む)」 ・業務用として販売されている・冷媒としてフロン類が充填されている |
【罰則1】みだり放出違反(法第103条第13号)
特定製品からみだりにフロン類を放出すると、みだり放出違反(法第103条第13号)に該当します。
■罰則
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
【罰則2】命令違反、引渡義務違反(法第104 条第1号・第2号)
フロン排出抑制法について、都道府県知事または主務大臣からの指導→助言→勧告→命令を経ても従わなかった場合に罰則が科されます。
■罰則
50万円以下の罰金
なお、「指導・助言・勧告・命令」の対象となる義務には以下のようなものがあります。
- 機器を適切でない場所へ設置する
- 定められた点検を実施しない(簡易点検・定期点検)
- フロン類の漏えいに対して適切な措置を行わない
- 点検等の履歴を機器廃棄後から3年間保存しない
- フロン類が充てんされている機器を、フロン類の回収を依頼しないまま廃棄する
【罰則3】行程管理制度違反(法第105条第2号~第5号)
■罰則
30万円以下の罰金
<行程管理制度における書面の例>
|
回収依頼書 |
フロン類が充てんされている第一種特定製品を廃棄する際に、フロン類の回収を第一種フロン類充塡回収業者へ依頼するにあたって必要となる書面 |
|
委託確認書 |
フロン類が充てんされている第一種特定製品を廃棄する際に、フロン類の回収を第一種フロン類引渡受託者(建物解体業者等)へ委託するにあたって必要となる書面 |
|
引取証明書 |
フロン類が充てんされている第一種特定製品を廃棄する際に、フロン類の回収を第一種フロン類充塡回収業者・第一種フロン類引渡受託者へ依頼すると交付または送付される書面または写し |
【罰則4】虚偽報告、検査拒否(法第107条第2号・第3号)
フロン排出抑制法では、事業所や管理者に対して、適切に法令を遵守しているかどうかを確認するために、行政機関が報告徴収や立入検査を実施することがあります。この際、報告を怠ったり、虚偽の内容を報告した場合、または立入検査を拒み、妨害、忌避した場合には、法第107条第2号および第3号に基づき罰則が科されることになります。
■罰則
20万円以下の罰金
【罰則5】算定漏えい量の虚偽報告(法第109条第1号)
第一種特定製品を所有する管理者は、定期点検などでフロン類の漏えい量を算定した際、1,000t‐CO2以上の漏えいを確認した場合には、毎年度7月末日までに事業所管大臣に報告しなければなりません。
報告を怠った場合や、虚偽の報告をした場合には罰則が科されます。
■罰則
10万円以下の罰金
フロン排出抑制法の罰則・摘発事案
フロン排出抑制法に基づく摘発事案の一例として、ある自動車販売会社と解体業者が関与したケースをご紹介します。
この事案では、自動車販売会社が建物の解体工事を発注する際、本来はフロン類の回収に必要な「委託確認書」を交付しなかったことで、30万円以下の罰金が科されました。一方、解体を請け負った業者は、機器に残っていたフロンガスを回収せず、そのまま作業を実施しました。結果的にフロンを大気中に放出したとして、50万円以下の罰金を受けています。
いずれも、発注者と解体業者の双方がフロン排出抑制法の内容や義務を正しく理解していなかったことが原因です。
※出典:https://www.env.go.jp/earth/furon/files/r04_kanrisya_rev.pdf
フロン排出抑制法の罰則を受けないために
フロン排出抑制法の罰則を回避するためには、法令を正しく理解し、確実な遵守が不可欠です。また、複雑な点検業務を効率的に管理するためのシステム活用も重要な対策の一つとなります。
ここでは、企業が取るべき具体的な対策について詳しく解説します。
フロン排出抑制法を理解し遵守する
フロン排出抑制法を確実に遵守するためには、まずその内容を正しく理解することが欠かせません。摘発事例からもわかるように、管理者や関係者の認識不足が原因で違反が発生するケースがあります。
また、フロン排出抑制法はこれまでに複数回の改正が行われており、今後もカーボンニュートラルの流れにあわせて制度の見直しが進む可能性があります。常に最新情報をチェックし、柔軟に対応していくことが重要です。
もし自社での対応に不安がある場合は、設備業者などへの管理の委託や保守メンテナンスの依頼も検討しましょう。
パナソニックでは、空調機器の保守メンテナンスおよびスポット対応サービスを提供しており、簡易点検・定期点検の両方に対応しています。フロン排出抑制法や空調に関する専門知識・技術を持つ技術者が対応するため、安心してお任せいただけます。
万が一、フロン漏えいなどの不具合が発生した際も、迅速かつ適切な修理対応が可能です。
点検忘れを防ぐ仕組みを活用する
フロン排出抑制法では、管理者に対して定期的な点検とその記録保存が義務付けられており、怠ると法令違反となる可能性があります。
しかし、複数の拠点や多数の機器を抱える現場では、点検スケジュールの管理や記録の整理に手間がかかり、点検を忘れてしまうといったリスクも考えられます。フロン排出抑制法で定められている一定の基準を満たした「常時監視システム」の活用で、簡易点検を自動化することが有効です。
まとめ
本記事では、フロン排出抑制法に違反した場合の管理者に対する罰則について詳しく解説しました。
2020年の改正により「直接罰」が導入され、違反が認められた場合には最大1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。企業にとって、法令を確実に遵守することはこれまで以上に重要となっています。
しかし、点検業務には手間がかかるのも現実です。中でも簡易点検は、3か月に1回以上の頻度で実施する必要があり、資格は不要とはいえ、社内対応が難しいケースも多く、外部委託を検討する企業も少なくありません。
ただし、外部委託には継続的なコストがかかるため負担が大きくなってしまいます。こういった課題を解決するために検討したいのが、常時監視システムの導入です。
2022年8月22日の法改正によって、一定の基準を満たした常時監視システムを導入することで、従来の目視による簡易点検に代えることが可能となりました。
フロン排出抑制法の罰則規定を理解し、適切な対策を講じることで、企業は法令違反のリスクを回避しながら、効率的な機器管理を実現できるでしょう。