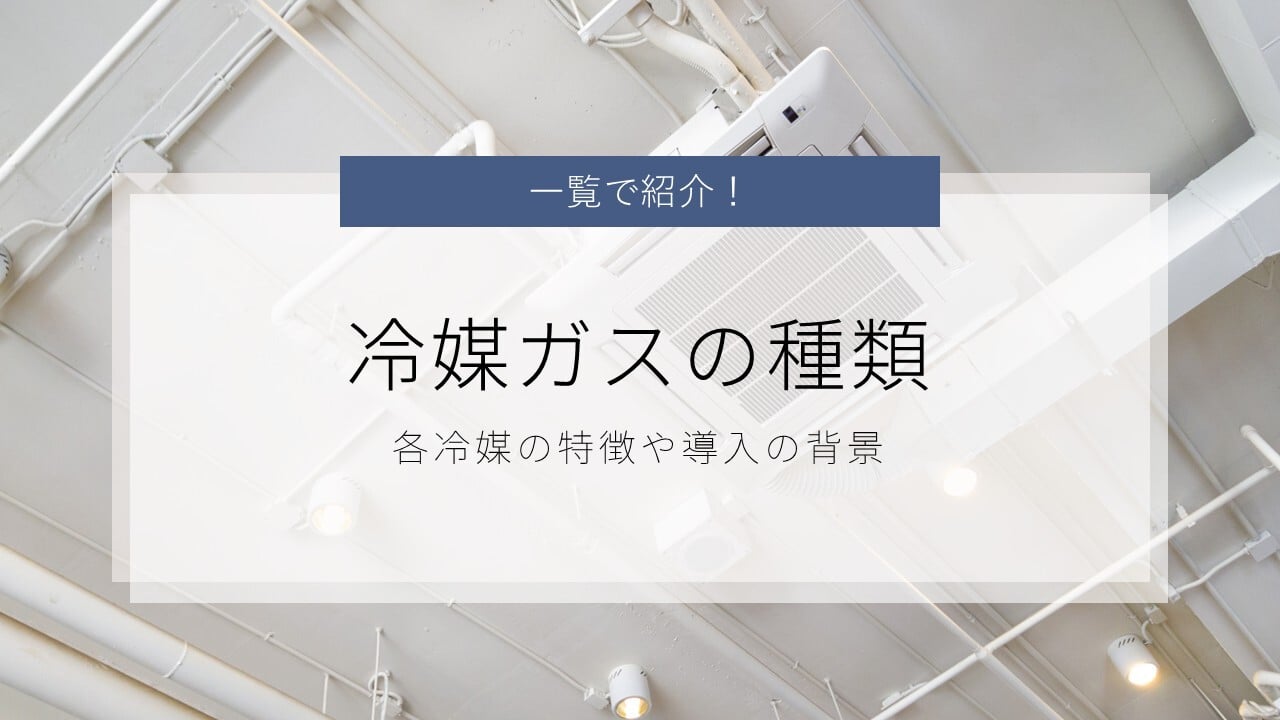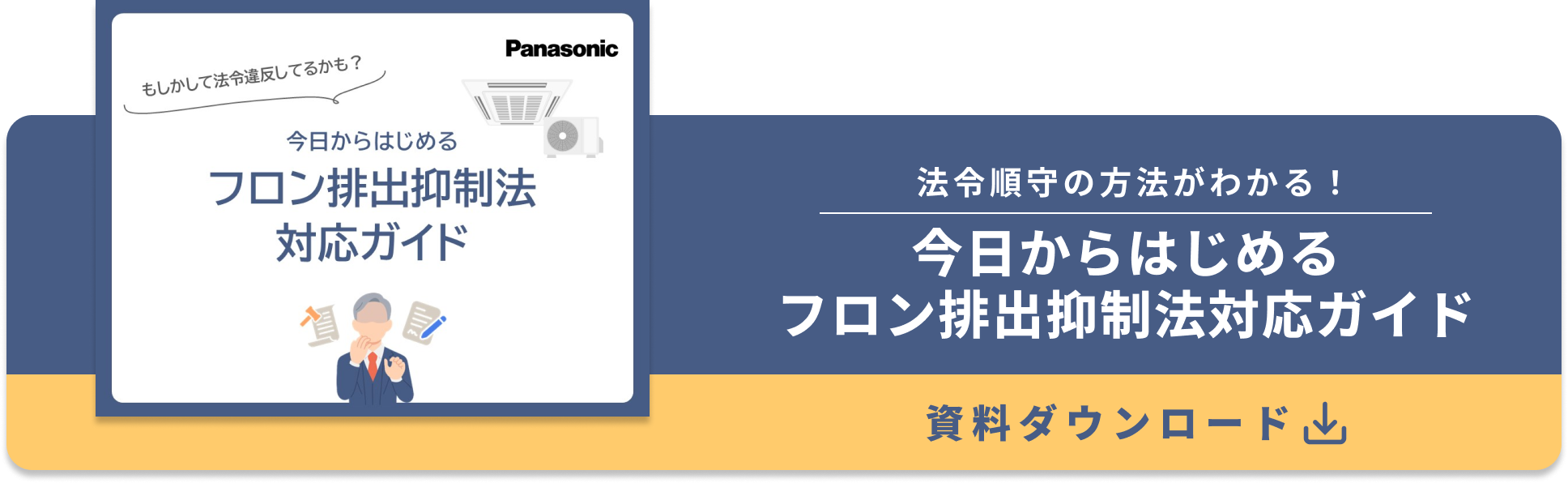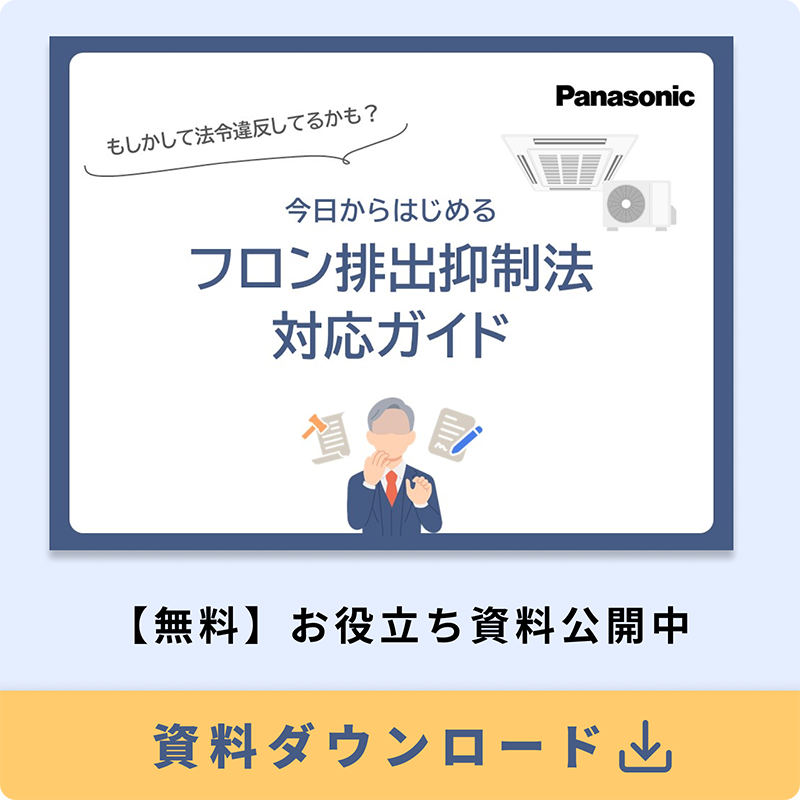冷媒とは冷凍・空調システムで熱を移動させるために使用される物質のことです。液体と気体の間で状態変化を繰り返すことで、効率的に熱を吸収・放出し、冷却や加熱を行います。
この特性を利用して、空調設備や冷蔵庫は冷却機能を働かせているのです。
(例)ヒートポンプにおける冷媒の働き
本記事では、冷媒の種類と、それぞれの特徴を紹介します。
この記事で
わかること
- 冷媒ガスの種類
- 各種冷媒ガスのオゾン層破壊係数
- 各種冷媒ガスの地球温暖化係数
冷媒ガスの種類
冷媒には以下の5種類があります。
- クロロフルオロカーボン(CFC)
- ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)
- ハイドロフルオロカーボン(HFC)
- ハイドロフルオロオレフィン(HFO)
- 自然冷媒
これらの冷媒は、オゾン層破壊や地球温暖化といった、環境問題に対応するために進化してきました。
以下の表は、各種類の代表的な冷媒のオゾン層破壊係数・地球温暖化係数・燃焼性を示しています。
|
項目 |
R12(CFC) |
R22(HCFC) |
R410A(HFC) |
R32(HFC) |
R-1233zd(E)(HFO) |
CO2(自然冷媒) |
|
オゾン層破壊係数(ODP) |
0.82 |
0.055 |
0 |
0 |
0.0002 |
0 |
|
地球温暖化係数(GWP) |
10,900 |
1,810 |
2,090 |
677 |
<1 |
1 |
現在では環境負荷の少ない、HFOや自然冷媒の注目度が高まっているものの、各冷媒で安全面や効率面等で課題があり、一概に最適といえるわけではありません。
ここでは、各冷媒の特徴や、導入の背景について紹介します。
クロロフルオロカーボン(CFC)
クロロフルオロカーボンは、初期の冷蔵庫や空調機器に導入された冷媒です。毒性がない、燃えにくい、分解されにくい、冷却効率が高いといった、優れた特性を持っています。
炭素、塩素、フッ素から構成される人工的な化合物であり、化学的に安定していることから、長期間大気中を漂う性質を持ちます。しかし、その安定性のために成層圏まで到達し、紫外線によって分解されると塩素原子を放出し、オゾン層を破壊することが発見されました。環境への悪影響が明らかになったのです。
そのため、1987年のモントリオール議定書により、クロロフルオロカーボンの段階的廃止が決定され、日本では1996年に全面的に生産が中止されました。
クロロフルオロカーボンに分類される冷媒は以下の通りです。
|
単一冷媒 |
R11 R12 R13 R113 R114 R115 |
|
混合冷媒 |
R500 R501 R502 R503 R505 R506 |
ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)
ハイドロクロロフルオロカーボンは、クロロフルオロカーボンの代替として開発された冷媒です。クロロフルオロカーボンと同様に炭素、塩素、フッ素を含み、さらに水素も加わった化合物となっています。
クロロフルオロカーボンよりも大気中での分解が早いためオゾン層破壊係数が低く、家庭用エアコンや業務用冷凍庫などの冷媒として使用されてきました。しかし、ハイドロクロロフルオロカーボンも塩素を含むため、オゾン層を破壊する性質があることに変わりはありません。
そのため、モントリオール議定書に基づいて、先進国では2020年までにハイドロクロロフルオロカーボンの全廃が決定されました。
ハイドロクロロフルオロカーボンに分類される冷媒は以下の通りです。
|
単一冷媒 |
R22 R123 R124 R141b |
|
混合冷媒 |
R401A R402A R403A R405A R406A R408A R409A R411A R412A R509A |
ハイドロフルオロカーボン(HFC)
ハイドロフルオロカーボンは現在主流の冷媒であり、クロロフルオロカーボンやハイドロクロロフルオロカーボンの代替フロンとして広く使用されています。
炭素、水素、フッ素を含む化合物で、塩素を含まないため、従来の冷媒と異なりオゾン層を破壊することがありません。
しかし、地球温暖化係数が高いという課題があり、2016年のキガリ改正ではハイドロフルオロカーボンの段階的削除が合意されました。
ハイドロフルオロカーボンに分類される冷媒は以下の通りです。
|
単一冷媒 |
R23 R32 R125 R134a R143a R152a R245fa |
|
混合冷媒 |
R404A R407C R407E R407H R407I R417A R448A R449A R452A R454A R454B R458A R463A R466A R513A R514A R410A R507 |
地球温暖化係数の高いハイドロフルオロカーボンが問題視されるなか、従来の主流冷媒R410Aと比較して地球温暖化係数の低い新冷媒R32が注目を集めています。
R32は、環境への負荷が少ないうえ、熱効率がよく省エネ性にも優れた冷媒です。ただし、微燃焼性があるため、安全に使用するためには漏えい対策など適切なアセスメントが必要となります。
R32については以下の記事でより詳しく紹介しています。
ハイドロフルオロオレフィン(HFO)
ハイドロフルオロオレフィンは、ハイドロフルオロカーボンの代替として開発された新世代の冷媒です。ハイドロフルオロカーボンと同様に炭素、水素、フッ素を含みますが、分子構造に二重結合を持つため、大気中での寿命が短くなっています。
そのため、オゾン破壊係数がゼロで、地球温暖化係数も非常に低いという特徴があります。
ただし、環境面での利点が大きい一方で、可燃性と毒性がそれぞれわずかにある点、これまでの冷媒と比較して効率がよくない点など、安全性と効率が課題です。
ハイドロフルオロオレフィンに分類される冷媒は以下の通りです。
|
単一冷媒 |
R1123 R1224yd R1234yf R1234ze R1233zd R1336mzz |
自然冷媒
自然冷媒とは、二酸化炭素、アンモニア、炭化水素(プロパンなど)、空気、水といった、自然界に存在する物質を利用した冷媒の総称です。
これらの自然冷媒は、オゾン層破壊や地球温暖化など、環境への影響が少ないことから注目されています。しかし一方で、それぞれに特有の課題があります。
二酸化炭素は無毒で不燃性ですが、高圧での運用が必要です。
アンモニアは効率は高いものの、毒性と可燃性があり、金属を腐食する性質があります。
炭化水素は可燃性が課題です。
空気は-60℃前後の超低温領域で使用できるため、超低温領域以外ではエネルギー効率が悪くなります。
水は0℃以下の冷却には使えず、エネルギー効率がそれほど高くありません。