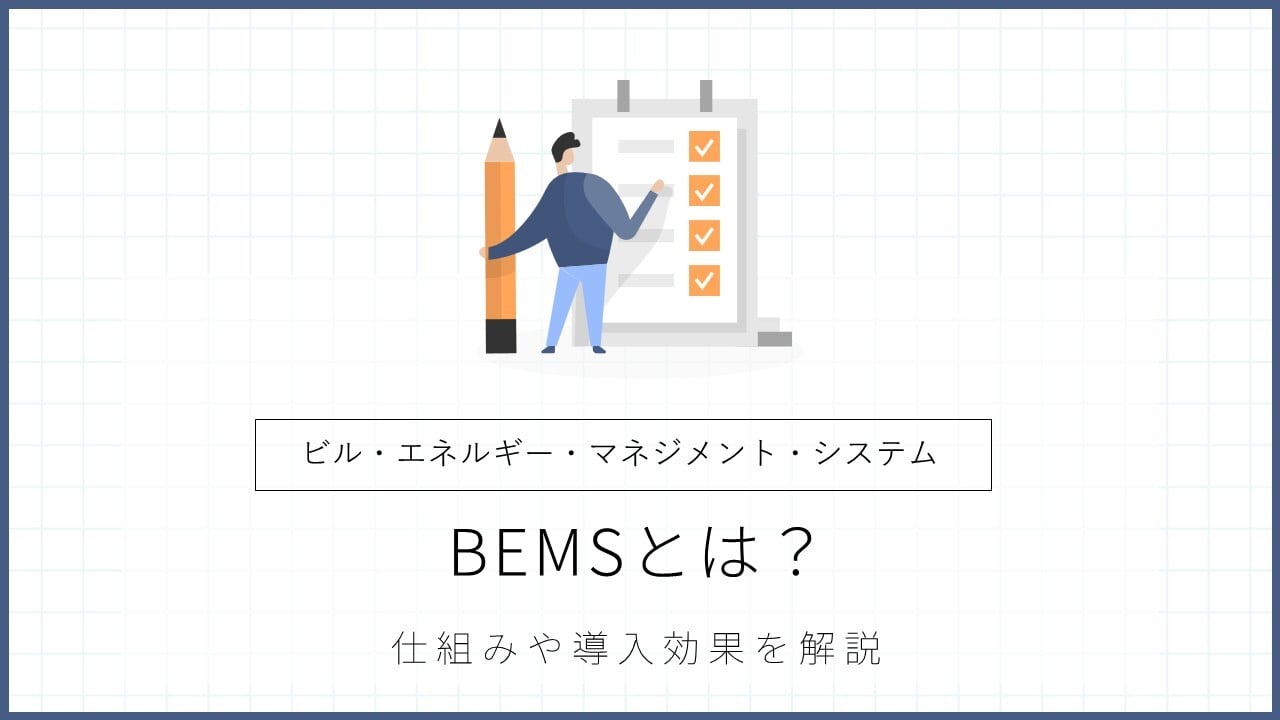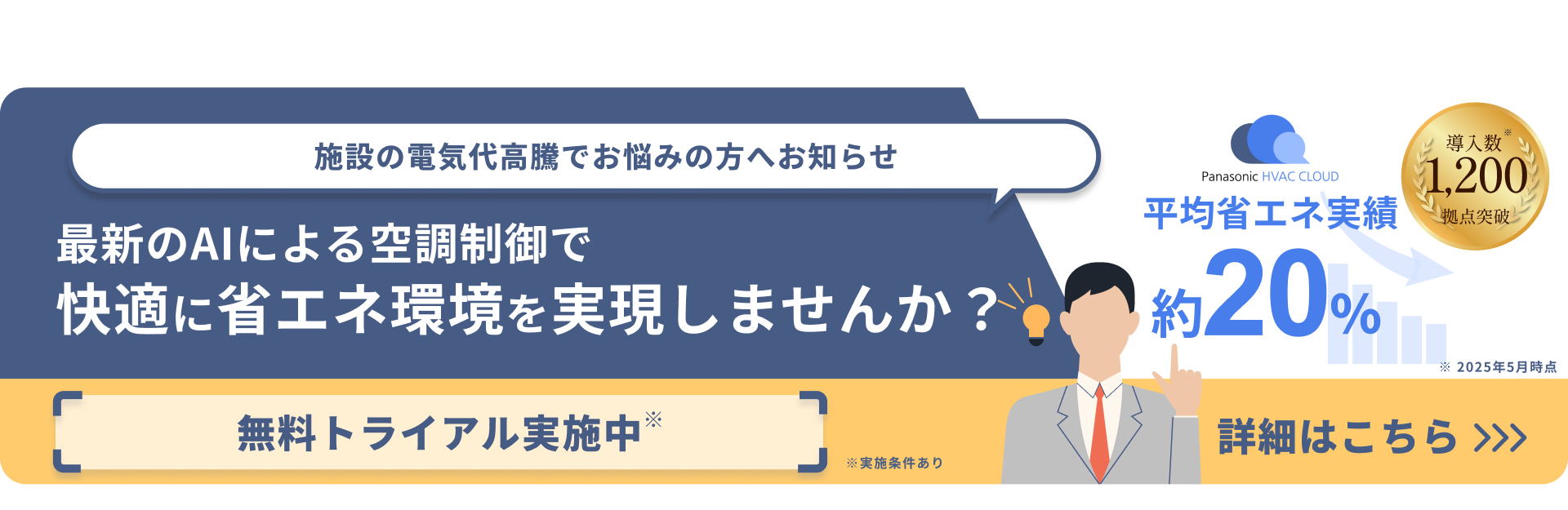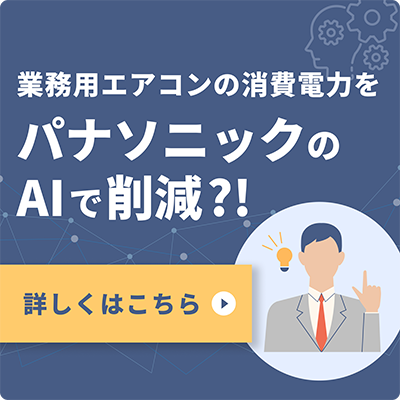BEMS(Building Energy Management System:ベムス)とは、建物内の空調や照明などのエネルギー使用状況を「見える化」し、効率よく運用するためのエネルギーマネジメントシステムです。
BEMSの導入により、「どの設備で、いつ、どれくらいの電力を使っているか」が明らかになるため、データに基づいた正確なエネルギーの削減が可能となります。近年では、エネルギーの安定供給や地球温暖化対策といった社会的背景から、BEMS導入による省エネ効果はニーズが増しています
本記事では、BEMSの定義や基本的な仕組み、導入による効果について、わかりやすく解説します。
この記事で
わかること
- BEMSの定義や仕組み
- BEMSのニーズが高まっている背景と導入時の課題
- BEMSの省エネ効果
BEMSの導入によりできること
BEMSを導入することで建物でのエネルギーの使用状況を把握し、そのデータをもとに受変電設備、空調・衛生設備、照明設備の運転を効率的に制御できます。ムダなエネルギー消費を抑え、環境負荷の低減とコスト削減が可能です。
例えば、以下図のように時間帯や設備ごとのエネルギー消費量を「見える化」することで、稼働にムダがある時間帯やエリアを発見し、対策を講じることができます。具体的には、始業前の無人時間に全館で空調が稼働している場合、人がいる場所だけに限定して運転することで、大幅な電力削減が見込めます。
引用:BEMS導入のススメ-事業所の省エネ・省コスト化へのみち|神奈川県ホームページ
また従来の省エネ対策では、「空調を弱める」「照明を間引く」など、我慢を前提とした方法になりがちでした。しかし、それでは快適性が損なわれ、業務効率の低下を招く恐れもあります。
一方で、BEMSを活用すればムダなエネルギーだけを削減しつつ、快適な室内環境を維持できます。
さらに、BEMSの導入によりエネルギー消費データを蓄積することで、設備の劣化や故障の兆候を把握できるのもメリットでしょう。とくに空調設備の故障は利用者の快適性に大きく影響するため、事前の対策が重要です。
このように、BEMSを導入することで「環境負荷の低減」「電気料金の削減」「快適な室内環境づくり」が可能になります。
BEMSの構成・仕組み
BEMSは主に「エネルギー管理共通基盤」「エネルギー情報システム」「エネルギー制御システム」の3つのシステムで構成されています。
|
エネルギー管理共通基盤 |
温度・湿度センサーや人感知センサー、エネルギー機器等が、フロアと室内ごとの温度や人の有無を感知し、データを収集・蓄積するシステム |
|
エネルギー情報システム |
収集・蓄積したデータの分析を行うシステム |
|
エネルギー制御システム |
分析に基づく需要予測等から設備を最適制御するシステム (状況に応じて自動で制御できるBEMSも多い) |
自動制御のBEMSの仕組みとしては、以下図が示すように、各フロアや部屋の情報がセンサーを通じて中央監視制御装置に集約されます。このデータをもとに分析・需要予測を行い、空調や照明などの設備を自動的に最適化します。
※BEMSの例
※引用:ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS) - 環境技術解説|国立研究開発法人 国立環境研究所
多くのBEMSは状況に応じた自動制御が可能です。また、設定された管理値を超えた場合には、アラーム機能で管理者に異常を通知し、迅速な対応を促すことも可能です。
BEMSのニーズの高まりと課題
BEMSのニーズが高まっている背景には、「エネルギーの安定供給」「地球温暖化対策」「電気代の高騰」の3つの側面があります。
一方で、中小規模の建物での導入が進んでいないという課題もあります。それらについて詳しく見ていきましょう。
BEMSのニーズが高まっている背景
BEMSのニーズが高まっている背景には、「エネルギーの安定供給」「地球温暖化対策」「電気代の高騰」の3つの側面があります。日本はエネルギーの自給率が低く、その多くを海外からの輸入に依存しているため、供給が滞ると国民生活や経済活動に大きな影響を及ぼします。
このような状況を受け、国は省エネ政策の制定・強化や再生可能エネルギーの普及に取り組んできましたが、依然として石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料に頼っているのが現状です(化石燃料の依存度は80.8% ※1)。
さらに、化石燃料はCO₂排出の大きな要因でもあります。政府は2030年までに、2013年比で温室効果ガスの46%削減を目標に掲げており、建物や施設における省エネ対策はその達成に向けた重要な取り組みの一つとなっています。
実際、日本国内のCO₂排出量を部門別に見ると「業務その他部門」が全体の19%を占め、そのうちの74%が電力使用によるものです(※2)。
※2
このように、建築物・業務部門におけるエネルギーの効率化は、喫緊の課題となっており、その解決策として、エネルギー使用の「見える化」による無駄の削減と、エネルギーの最適化を実現するBEMSの導入が注目されています。
なお、BEMSの普及が進んだきっかけは、東日本大震災の影響による電力供給のバランスの変化でした。
節電意識が高まったことで、企業を中心にEMS(エネルギーマネジメントシステム)の導入が進みました。その後、エネルギー価格の上昇も重なり、現在では再びBEMSへの注目が高まっています。
(※1)出典:令和5年度(2023年度)エネルギー需給実績を取りまとめました(速報)|経済産業省
(※2)出典:2022年度(令和4年度) 温室効果ガス排出・吸収量について|環境省
BEMS導入における課題
BEMSの重要性が注目されている一方で、中小規模の建物での導入が進んでいない現状があります。
BEMS活用においては大規模な建物と同様の対策が必要ですが、中小規模の建物では「費用面」と「技術的な問題」が導入の障壁となっているためです。大規模な建物であれば、BEMS導入によって得られる効果が大きく、費用対効果も見込めるでしょう。
しかし、中小規模の施設では、同じ規模・内容のBEMSを導入してもコストに見合う効果が得られにくく、また、運用・保守に必要な技術者が確保しにくいのが現状です。
そこでパナソニックでは、高圧小口需要家様向けに、使いやすさとコスト面を見直した「Emanage(エマネージ)」を提供しています。中小規模施設にも導入しやすいように設計されており、省エネ効果と運用のしやすさを両立できる新しいBEMSとして注目されています。
BEMS導入のコストと回収年数
BEMSの導入コストは、システムの機能性や建物の規模などによって大きく異なります。
例えば、神奈川県が補助事業として対応したBEMS導入事例では、そのコストが約60万~1,000万円(※1)と幅広いことが分かります。
また、導入コストはエネルギー削減によるコスト削減効果によって回収することができます。一般的に、BEMSの回収年数は8年未満であるケースが多く(※2)、導入事例によってはさらに短期間での回収も実現しています。
実際、補助事業を活用してBEMSを導入した事例では、補助額を引いた事業者の実質負担に対する回収年数は、事例Bで3.3年、事例Cで5.5年と比較的短期間で回収されていることがわかります。
※2
(※1)BEMS導入のススメ-事業所の省エネ・省コスト化へのみち|神奈川県ホームページ
(※2)BEMS導入支援事業全体の効果(データ管理)|内閣府
導入事例で見るBEMSの省エネ効果
実際のBEMS導入事例から、その省エネ効果を見ていきましょう。
複数のビルをまとめて管理した事例と、さらなる省エネ化を目指した事例の2つを紹介します。
【事例1】複数のビルをまとめて管理
この事例では、親ビルにBEMSを導入し、5つの子ビルをまとめて管理する体制を構築しました。BEMSは主に空調管理に活用され、運転状況や温湿度の制御、熱源搬送動力の低減のために空調機の台数や変流量の調整が行われました。
さらに、テナントの残業時間や外気温の変化といった外的要因も的確に捉えた、最適な運転と分析を実施しました。その結果、導入後4年間で全ビルで最大19.4%のエネルギー削減を達成しています。
※出典:BEMS導入支援事業全体の効果(データ管理)|内閣府
【事例2】さらなる省エネ化を目指して
続いて、パナソニックが提供する「Emanage(エマネージ)」を導入した事例を紹介します。
リコージャパン株式会社様は、これまでも全社規模での意識改革や、新電力への切り替えによるコスト削減、省エネ設備の見直しによるエネルギー使用の低減といった省エネ改革に取り組まれていました。そこで、さらなる省エネ化を目指して「Emanage」による運用改善を行いました。
具体的には、空調機の動作範囲を制限する「温度連動制御」や、電力使用量をコントロールして電力需要を抑える「デマンド制御」を実施。その結果、導入前と比較して冬季3カ月間の電力使用量と最大電力の削減に成功しました。
※出典:リコージャパン株式会社 埼玉支社宮原事業所 | 納入事例集 | 電気・建築設備 | Panasonic
BEMS導入のポイント
BEMSの導入において重要なのは、システムの設置だけで終わらせないことです。
取得したデータをもとに、運用状況の分析や課題の抽出を行い、改善策を立てて実行するというPDCAサイクルを継続的に回すことで、省エネ効果を最大化できます。
必要に応じて専門家による相談や診断を受けることも有効です。
まとめ
BEMSは、建物内のエネルギー使用状況を「見える化」し、データに基づいた効率的な運用を実現するためのシステムです。空調の使用を控えるといった「我慢の省エネ」ではなく、室内環境を快適に保ちながら効率的な省エネが実現できます。
そのため、BEMSは「エネルギーの安定供給」や「地球温暖化対策」といった社会的ニーズに応える仕組みとして、導入が進んでいます。
一方で、中小規模の建物では導入コストや技術的な理由から普及が遅れているのも現実です。そこでパナソニックでは、あらゆる規模に対応する「Panasonic HVAC CLOUD」に加え、中小規模の建物でも導入しやすく、使いやすい「Emanage(エマネージ)」を提供しています。
導入支援や補助金情報の提供も行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。