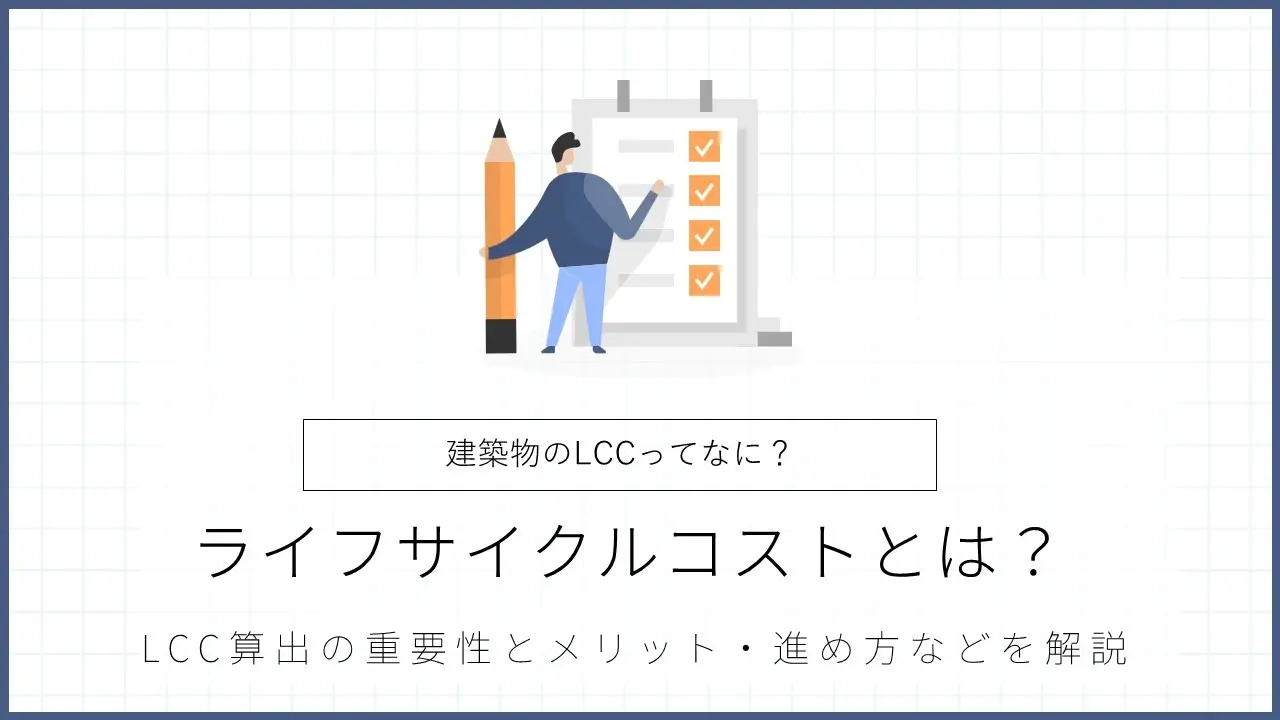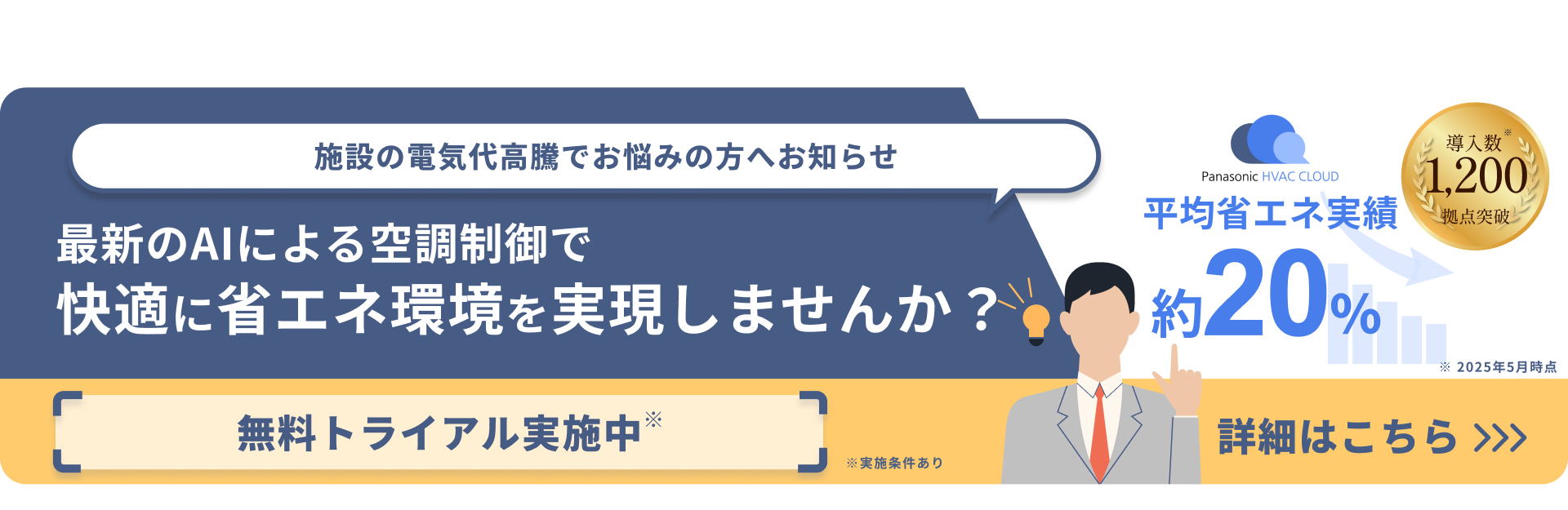建築物を建てる際には初期費用(建設費用)に注目しがちですが、実際にはその後にかかる費用も含めたライフサイクルコスト(LCC)が重要です。建築物におけるライフサイクルコスト(LCC)とは、建物の企画・設計から解体・廃棄するまでの総費用を意味します。
LCCの考え方を取り入れることで、建設時の初期費用だけでなく、建築後のランニングコストや修繕費などを総合的に見据えた、費用対効果の高い建物を計画・設計することが可能となります。これにより、長期的に見て経済的で持続可能な建築を実現でき、施主にとって大きなメリットとなるのです。
この記事では、ライフサイクルコスト(LCC)の概要や重要性、低減方法などについて詳しく解説します。
建築物のライフサイクルコスト(LCC)とは
建築物におけるライフサイクルコスト(LCC)とは、建築物の企画・設計段階から、建設、運用、修繕、そして最終的な解体・廃棄に至るまでのすべての段階でかかる総費用のことを指します。
ライフサイクルコストは大きく「初期費用」「運用・保守費用」「解体・廃棄費用」の3つに分けられます。それぞれを構成する要素には、以下のようなものがあります。
■初期費用
- 土地の取得費
- 現況測量費(土地や建物の現状を測定・評価する費用)
- 地盤調査費、その調査に基づく改良
- 解体費(土地に建物があり、取り壊す場合)
- 設計費
- 建設費
- 契約にかかる諸費用(仲介手数料、印紙代、水道分担金、司法書士手数料 など)
■運用・保守費用
- 水道光熱費
- 修繕費
- 保険費(火災保険、地震保険など)
- 税金(固定資産税など)
- 管理費(警備、清掃、点検など)
- 消耗品費(電球など)
- 広告費(テナントに空きが出た場合)
■解体・廃棄費用
- 解体費
- 廃棄費(建物の廃材処分にかかる費用)
ライフサイクルコスト(LCC)を考える重要性
ライフサイクルコストが重要である理由としては、主に以下の3点が挙げられます。
- 長期的な視点で見れば経済的なため
- 資産価値の維持・向上を図れるため
- 環境への回呂につながるため
それぞれ見ていきましょう。
長期的な視点で見れば経済的なため
ライフサイクルコストは、長期的なコスト削減を図るうえで重要な視点です。
建物の企画段階から解体・廃棄に至るまでのすべての工程にかかる総費用を指すライフサイクルコストですが、その内訳を見てみると、建設時にかかる初期費用は全体の20%以下に過ぎません。残りの約80%を占めるのが、建設後の運用・保守・修繕などに関わるコストです。
つまり、初期費用を抑えるために性能を妥協して建てた建物は、後々の修繕費やエネルギーコストなどがかさみ、かえって高コストになる可能性が高いということです。ライフサイクルコストを意識した建物は、初期投資こそ増えるかもしれませんが、長期的な視点で見れば経済的といえます。
資産価値の維持・向上を図れるため
ライフサイクルコストの視点を取り入れた建物では、生涯にわたって最適な状態を維持しながら、コストの低減を図っていきます。
具体的には、建物や設備の劣化、省エネ性能に優れた設備の登場などにより、2~3回程度の改修を計画的に行います。建物は常に良好な状態が保たれ、利用者にとって快適で安心できる空間を提供し続けることが可能となり、結果として資産価値の維持や向上につながるのです。
また、省エネ性能の向上によって、エネルギーコストの低減にも貢献します。
環境への配慮につながるため
ライフサイクルコストを重視することは、経済的なメリットだけでなく、環境への配慮にもつながります。
例えば、断熱性能に優れた建物は外気の影響を受けにくく、室内の温度を一定に保ちやすいため、冷暖房効率が向上します。これによりエネルギー消費量が削減され、地球温暖化の遠因の一つであるCO2排出量の削減にもつながるのです。
日本はエネルギー資源に乏しく、海外から輸入する化石燃料に依存している状態にありますが(※1)、その化石燃料は地球温暖化の原因の一つであるCO2を多く排出します(※2)。したがって、ライフサイクルコストを見据えて電力使用量の削減に取り組むことは、CO2削減に寄与することになります。
CO2の排出量削減に貢献することは、持続可能な社会の実現に貢献するため、企業や建物の資産価値の向上にもつながるでしょう。
(※1)出典元:1.安定供給|資源エネルギー庁
(※2)出典元:増大するCO2排出量(エネルギー・ミックス)| 北陸電力株式会社
ライフサイクルコスト(LCC)を低減するには
ライフサイクルコストの低減を図る方法は多くあります。ここでは主な方法として以下の6つを紹介します。
- 外皮性能の向上
- 省エネ性能に優れた設備の採用
- エネルギーマネジメントシステムの導入
- 計画的なメンテナンスの実施
- 老朽化や新技術への対応
- 再生可能エネルギーの導入
それぞれ見ていきましょう。
外皮性能の向上
建物の外皮とは、外壁、屋根、天井、床、開口部(ドアや窓など)、基礎を指します。外皮性能を向上させることで、熱の出入りを抑えられるため、冷暖房効率が良くなるのです。その結果、エネルギー消費を抑えられ、光熱費の削減につながります。
外皮性能を向上させる方法には以下のようなものがあります。
- 断熱性能に優れた断熱材を使用する
- 二重窓にする
- Low‐Eガラスを採用する
- 庇や軒をつくる
省エネ性能に優れた設備の採用
省エネ性能に優れた設備を採用すれば、光熱費の削減につながります。例えば、高効率空調設備、全熱交換器、LED照明の採用などが挙げられます。
とくに、空調は業務用建物において4~5割ものエネルギー消費を占めるため、省エネ性能による削減効果は大きくなるでしょう。

エネルギーマネジメントシステムの導入
エネルギーマネジメントシステム(EMS)とは、建物におけるエネルギーの使用状況を可視化し、設備の運転を最適化することで、省エネルギーとコスト削減を実現するシステムです。空調や照明といった設備の稼働状況を把握し、使用状況に応じて手動または自動で制御を行うことが可能になります。
例えば、パナソニックが提供する「Panasonic HVAC CLOUD」は、オフィスや店舗で使用されるエアコンにセットすることで、消費電力量の推移をグラフで可視化します。これにより、どの設備が、どの時間帯や曜日に無駄な電力消費が発生しているのかを把握できるようになり、具体的な省エネ対策を講じることが可能です。
さらに、本システムは業界初(※1)のAIを活用した省エネコントロール機能を搭載しています。施設情報・利用者の空調設定・気象情報・時刻設定を学習し、それに基づいて自動で外気温や時刻に応じた温度調整を行います。このAI省エネコントロール機能により、人による過剰な快適運用を減らすことでエネルギーのムダを防ぐことができ、実際の運用検証では、年間で約20%の消費電力削減が確認されました。(※2)
(※1)空調機業界において、当社調べ(2023年3月8日時点)
(※2)1年間、関東地方の2つの異なる物販店舗(約1,000㎡)の施設で検証。「設定温度自動リターン」機能(一定時間で指定した温度設定に戻る機能)との比較。
計画的なメンテナンスの実施
空調設備や換気設備、エレベーターなどの計画的なメンテナンスを実施することで、劣化によるエネルギー消費量の増加、突発的な故障による修繕費の増加を防ぐことが可能です。また、故障による業務への支障、経営への影響を未然に防ぐことにもつながります。
例えば、空調設備が突然停止すれば、オフィスでは業務に集中できず生産性が下がる可能性があり、店舗では顧客の滞在時間が短くなったり、来店自体を控えられるといった問題が起こり得ます。ライフサイクルコストを見据えた定期的なメンテナンスは、こういったトラブルの防止にも効果的です。
パナソニックが提供する「Panasonic HVAC CLOUD」なら、クラウドに接続した空調機の異常を知らせる警報通知をメールで受け取ったり、WEB画面で一括表示することができます。現地でリモコンを確認することなくエラーコードを把握できるため、適切な対処を速やかに行うことができるようになり、突発的な故障の見落とし防止に貢献します。
老朽化や新技術への対応
建物や設備は、時間とともに次第に劣化するものです。一方で、建築技術や設備の性能は日々進化しています。老朽化への対応と新技術の積極的な導入を計画的に行うことで、建物の価値や快適性を維持・向上させながら、ランニングコストを効果的に抑えることが可能です。
例えば、パナソニックの空調設備を旧製品(2012年モデル:PA-P80UM1SX)から、現行品(PA-P80U7SGB)に入れ替えた場合を比較してみると、年間あたりの消費電力量の削減効果は43%、電気代に換算すると27,100円の削減、その節約効果は実に57%に達します(※)。
このように、定期的な見直しと更新が、長期的なコスト削減と資産保全に大きく寄与するのです。
※
|
・1台あたりの試算です。 ・電気代は(社)日本冷凍空調工業会の統一条件のもとに運転した場合の計算値であり、地域やご使用状況により変わることがあります。(統一条件:規格 JRA4002:2013R/地区 東京/建物用途 事務所/使用期間 【冷房】4月19日〜11月11日【暖房】12月3日〜3月15日/使用時間 8:00〜20:00 6日/週 /電気料金単価 東京電力 低圧電力契約) ・電気代に基本料金は含まれていません。 ・旧製品の電気料金は、機器の経年劣化を考慮して算出しています。 |
再生可能エネルギーの導入
太陽光発電システムなどの再生可能エネルギーを導入することで、建物で使用する電力を自給自足できるようになり、電力会社から購入する電力量の削減が可能です。
蓄電池を併用することで、発電が難しい夜間や雨天時でも、日中に蓄えた電力を活用できるため、より安定的かつ効果的にコストを削減できます。
また、再生可能エネルギーの活用はCO2排出量の削減にも寄与します。地球温暖化防止や持続可能な社会の実現に貢献する取り組みとしても高い効果を期待できるでしょう。
ライフサイクルコスト(LCC)の初期費用への課題
ライフサイクルコストの一つである初期費用は、全体の割合としては小さいものの、額としてみれば大きいものです。そこで活用したいのが、国や自治体が実施している補助金制度です。
近年ではカーボンニュートラルの実現に向けて建物の省エネ化が求められており、それに対応する補助金も充実しています。
補助金に関する情報提供は、パナソニックにぜひお任せください。
まとめ
ライフサイクルコスト(LCC)は、建築物を計画・設計する段階から、その建物を解体・廃棄に至るまでにかかる総費用を意味します。
建物の建築コストはライフサイクルコストの20%以下にすぎないため、廃棄までを見据えた長期的な視点でコストを捉えることが経済的な選択につながります。また、ライフサイクルコストを考えることはCO2削減につながり、環境負荷の軽減にも貢献します。
ライフサイクルコストの低減を図るには、外皮性能の強化、省エネ性能に優れた設備の採用、エネルギーマネジメントの導入、計画的なメンテナンスや修繕といった方法があります。なかでも空調は業務用建物において4~5割ものエネルギー消費を占めるため、空調における省エネ対策はライフサイクルコストの低減に大きく貢献するでしょう。
パナソニックが提供する「Panasonic HVAC CLOUD」なら、空調設備の消費電力を可視化するだけでなく、業界初(※1)のAI省エネコントロール機能により外部環境と利用者の温度設定を学習し、快適性を損なわず省エネが可能です。クラウドシステムのため、「A店舗・B店舗・C店舗」のような複数の建物も任意のPCから一括管理が可能で、業務の省力化とエネルギー最適化を同時に実現できます。
「Panasonic HVAC CLOUD」の具体的な機能や導入方法については、お気軽にパナソニックまでお問い合わせください。
建物のライフサイクル全体を見据えたコスト管理は、長期的な視点に立ち、経済性と環境性を両立する賢明な経営判断といえます。
(※1)空調機業界において、当社調べ(2023年3月8日時点)
(※2)1年間、関東地方の2つの異なる物販店舗(約1,000㎡)の施設で検証。「設定温度自動リターン」機能(一定時間で指定した温度設定に戻る機能)との比較。